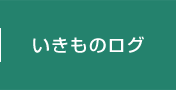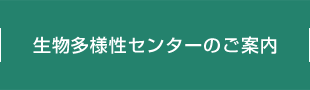-
洗濯業排水の鯉を用いた急性毒性試験(横浜市公害研究所報 第7号)
凝集処理効果を生物学的に評価する試みとして、捺染業に引き続き洗濯業を選択し、移動式魚類試験装置を用いて現場実験等を行った。総合排水の凝集処理前および後の水を用いて、鯉に対する75時間急性毒性試験を行った結果、凝集処理によって死亡率は100%から0%へ、内部および鯉形態の異常出現率は100%から50%とかなりの改善が認められた。しかし、処理後の水でも横転... -
Nitzschia palea(付着性ケイ藻)を用いたAGP測定法の検討(横浜市公害研究所報 第6号)
河川に広く分布し、有機汚濁の著しい都市河川で代表的な付着藻であるNitzschia paleaを用いたAGP測定法を確立するため、Gorham No.11... -
捺染排水の鯉を用いた急性毒性試験(横浜市公害研究所報 第6号)
排水処理における凝集処理効果を生物学的に評価する試みとして、捺染業を選択し、現場実験を行った。捺染工程の手捺染、自動捺染、水洗の各排水およびこれらの総合排水について、鯉に対する75時間急性毒性試験を行った結果、凝集処理によって死亡率および外部、内部、鰓観察結果の異常出現にかなりの改善が認められた。又、工程排水のうち自動捺染排水で鯉が死亡した主因物質はア... -
コイ(Cyprinus carpio)の幼魚のおける血液性状の研究(第2報)-血漿蛋白量とセルローズアセテート電気泳動法による血漿蛋白分画の基礎的研究-(...
本研究は、魚類の集団の健康状態を血液化学的観点から評価する手法を確立するために行った。供試魚は健康なマゴイ(1才魚)を用い、尾数は91尾であった。体重は88.1±30.9(g), 体長は14.5±3.7(cm),... -
東海道線・戸塚駅付近のボーリングコアより得たケイ藻群集(横浜市公害研究所報 第5号)
戸塚駅周辺部の地質・土質調査の一環として実施された深層ボーリングコアを用い、微化石層序の確定と堆積環境を推進するためケイ藻分析を行なった。22試料から38属191種のケイ藻が検出され、Navicula属、Pinnularia属、Gomphonema属の種が多く、淡水種が76%を占めもっとも多かった。分析を行なった各層のケイ藻群集はかなり異なっていた。戸... -
健全な供試魚確保のための魚病学的検討(横浜市公害研究所報 第5号)
鯉を用いた生物検定試験を行うに当って、その蓄養および試験期間中の発病を抑える為の予防方法を魚病学的に検討した。当研究所で購入した鯉がどのような発病因子を保持しているかを知る為に、現在までの発病状況の把握と共に昭和55年度購入魚の内の有症魚について寄生虫試験および細菌試験を行った。その結果、稚魚購入時の症状が最も多様であり、購入時に有症魚を選別除去しても... -
コイ(Cyprinus carpio)の幼魚における血液性状の研究(第1報)-正常値の検討-(横浜市公害研究所報 第5号)
コイの幼魚、70尾を用いて血液検査を行ない、その血液性状値について検討した。血液性状値の分布はヘモグロビン濃度、ヘマトクリット、赤血球数が正規型の分布を示した。成長量と血液性状との関係では体重、体長ともに赤血球数、平均赤血球数ヘモグロビン濃度、平均赤血球容積と相関があった。肥満度は血しょう総タンパク量のみと相関があった。血液性状値間ではヘモグロビン濃度... -
コイ(Cyprinus carpio)における麻酔剤の血液性状に及ぼす影響(横浜市公害研究所報 第5号)
魚の取り扱いに関する基礎的資料を得ることを目的として、コイの血液性状に及ぼす2種類の麻酔剤、オイゲノール、MS222の影響について検討した。コイの麻酔所用時間は、オイゲノールの1/5,000は、3分20秒~5分、1/2,000は、55秒~1分30秒、MS222では、1/20,000は、3分~6分35秒、1/10,000は、1分15秒~2分であった。血液... -
コイ(Cyprinus carpio)における摂餌率と飼料効率について(横浜市公害研究所報 第5号)
本市が公害防止契約で魚類を用いて工場排水の安全性を評価していくことが規定されているが、その評価項目の一つに成長量があげられる。その成長量に反映するものとして、一つには摂餌量があり、他の一つにはそれぞれが体重増に果す割合、いわゆる飼料効率がある。今回、成長の制限因子を明らかにする一環として、まず、摂餌率と飼料効率の関係について検討した。その結果、日間平均... -
コイ(Cyprinus carpio)に及ぼす塩化ナトリウムの急性、亜急性影響(横浜市公害研究所報 第4号)
塩化ナトリウム(NaCl)のコイ(Cyprinus carpio)に対する急性、亜急性影響試験を0(対照)、2,500, 5,000, 10,000㎎/ℓの濃度段階で行なった結果、以下の成績を得た。急性影響としては、曝露後1日目、5,000,... -
酸素欠乏・過多、及び残留塩素曝露時におけるコイ(Cyprnus carpio)の鰓の形態学的変化について(横浜市公害研究所報 第4号)
魚の健康状態に係わる簡便な検査項目の一つとして、実体観察による鰓組織像が注目される。今回、コイの鰓組織に与える酸素の欠乏・過多及び残留塩素の影響を実体観察により検討した。酸素の欠乏時においては、鰓弁および二次鰓弁の上皮が収縮する、すなわち二次鰓弁の呼吸面積が広がる傾向が見られ、死亡時点でも同様な像を示す傾向が明らかになった。また、残留塩素に曝露された場... -
摂餌の飼育水に及ぼす影響(横浜市公害研究所報 第4号)
生物検定に関する蓄養あるいは投餌を必要とする長期試験時に、安定かつ良質な飼育水を維持する為の基礎研究として、150ℓの水に500㎖/min... -
平成26年度水域生物多様性に関する調査業務委託報告書
河川生物モニタリング調査によって生物生息状況を把握し、生物指標を用いて水質評価を行うとともに、水環境を考える基礎資料とすることを目的とした。 -
ボーリングコア分析による鶴見川低地の地質について(横浜市公害研究所報 第3号)
本市は1977年に、新横浜駅前の観測井設置に伴なう試錐を行なった。それによって得られたコアのケイ藻・花粉・貝の化石分析と鉱物分析を行なった。またこの試錐地点を通る鶴見川谷の地質横断面図を作成した。目的は、化石分析によって堆積環境を復元し、鉱物分析で鍵層となる火砕層の鉱物組成を確定し層相区分及び周辺地域における地層の対比の資料を得ることにある。結果は以下... -
大岡川源流部の氷取沢における付着藻類植生(横浜市公害研究所報 第3号)
大岡川の源流部の、円海山・北鎌倉近郊緑地保全地区の北部を流れる氷取沢の、付着藻類の調査を、1976年9月より1978年3月までに6回行なった。その結果、藍藻類、緑藻類、紅藻類がそれぞれ1種、ケイ藻類が57種、計60種の藻類が検出された。紅藻類のベニイトモChantransia sp.... -
横浜市沿岸水域における化学物質汚染状況調査 -TBP, BHT, TP-(横浜市公害研究所報 第3号)
横浜市沿岸水域におけるTributyl-phoshate (TBP), 2, 6-ditertbutyl-p-cresol (BHT), o-Terphenyl (o-TP), m-Terphenyl (m-TP), 及びp-Terphenyl (p-TP) による汚染状況を、水質、底質及び生物質(魚類)について、昭和52年11月に調査した。BHT,... -
生物指標による水質汚濁の評価方法(1) -多様性指数の適用- (横浜市公害研究所報 第2号)
従来の生物を用いた水質汚濁評価は、主に汚水生物体系(Saprobiensystem)や、生物指数(Biotic Index) により行われてきた。近年、これら定性的情報による方法とは別に、群落構造により決定される定量的情報である多様性指数(Diversity... -
溶存食塩の鯉個体群の成長に及ぼす影響について(横浜市公害研究所報 第2号)
工場排水中に含まれる無機塩が、どのように魚類の成長に影響を与えるかということについて検討することを目的とした。なお、実験においては、一般的にも工場排水に含まれる可能性が高く、比較的、魚類の生理的な機作が明らかな食塩を無機塩の典型として、使用した。 -
魚類の飼育技術に係る研究(横浜市公害研究所報 第2号)
昭和52年12月末日において、「工場等の排水に係る魚類飼育指針」を公表した。この指針作成の目的は、工場排水の環境に対する安全性であり、(1)全汚染物質について(2)微量の濃度まで(3)連続的に(4)長時間にわたり魚類を指標にし、その影響による反応を見る方法により、総合的に工場排水を評価することにある。指針の対象工場としては、今日の水質汚濁の主要な発生源... -
平成28年度陸域生物多様性に関する調査業務委託報告書
環境施策を立案・推進するにあたり、市域における生物について、定期的に定量的・定性的な情報を把握しておくことが重要である。そこで、市域における陸生生物相について調査を行い、環境変化や地域特性による生物相の違いについて、解析・検討を行って、基礎資料を作成することとした。調査地点は大岡川流域から選定、4年ぶりの調査。