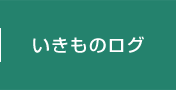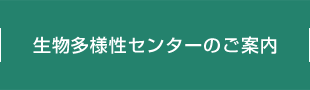-
河川における環境基準達成のための要因に関する研究(第1報) -中堀川-(横浜市環境科学研究所報 第27号)
横浜市内においてBODが環境基準を上回る小河川の例として中堀川を取り上げ、水質・底質・付着物・付着藻類について流程調査を行ったところ、本流の2割以上の流量を占める支流の流入点より下流で水質が悪化していた。底質は流入点の直下の淵で酸化還元電位が0mV付近まで低下しており、付着物は流入点より下流の地点で強熱減量や総リンが高い傾向にあった。付着藻類による水質... -
横浜市内河川の重金属濃度とミジンコの生存率について(横浜市環境科学研究所報 第26号)
横浜市内において、平成9年7~12月河川水を採水し、重金属(銅、カドミウム、亜鉛、鉛)の調査を行うとともに、ミジンコを用いて河川水中の生存率を調べた。河川水に含まれる重金属の分析を行った結果、カドミウムはいずれの試料も1㎍/ℓ... -
横浜の森林土壌の酸性化の実態と酸中和能(1) -スギ林、広葉樹林、森外土壌の調査-(横浜市環境科学研究所報 第26号)
1999年11月~2001年3月の寒候期、横浜市内において、スギ林土壌38、広葉樹林土壌52、林外(裸地)土壌22、合計112の土壌試料を採取し、土壌pH、交換性塩基、交換性Al、水溶性Al等を調べた。スギ、広葉、林外の平均pH(H₂O)は、それぞれ4.70、5.57、6.49、であり、スギ林土壌が低く、特に道路近傍のスギ林土壌は平均が4.34とかなり... -
身近な生きものについてアンケート調査結果(第2報)(横浜市環境科学研究所報 第26号)
本調査は、現在の小学生の身近な生きものについての意識、経験、知識及び考え方を把握するため、小学生を中心に中学生、高校生、大学及び保護者を対象にアンケート調査を実施したものである。昨年度までの解析では、身近な生きものとのふれあい、知識及び意識、考え方などについて年代別男女別の特性を確認した。本報告では、昨年度の解析結果を基に、身近な生きものの好き嫌いと体... -
横浜市沿岸のプランクトン相調査(第2報)(横浜市環境科学研究所報 第26号)
1998年から2000年までの過去3年間のプランクトン相の月別特徴を中心に報告した。この3年間の調査の中で、珪藻のCoscinodiscus spp. や渦鞭毛藻のGymnodinium sp.など外洋のプランクトンが観察されるようになってきたこと、今まで東京湾ではほとんど見られなかった有害プランクトン渦鞭毛藻のAlexandrium... -
池改修による魚類・甲殻類(十脚目)相の変化に関する研究(横浜市環境科学研究所報 第26号)
池の改修後における魚類、甲殻類相の再生、回復の状況を解析するために5池を対象に調査した結果を報告した。改修前の魚類相は、御手洗池を除いてモツゴ、トウヨシノボリが多く出現していた。もえぎ野公園池、白幡池の例では、改修後の放流1、2ヶ月後、フナ属が顕著に増加し、モツゴも比較的多く増加した。トウヨシノボリの増加は若干遅かった。放流後1から4年後では、特にフナ... -
横浜市内の池における水環境と魚類相、甲殻類(十脚目)相の調査報告(横浜市環境科学研究所報 第26号 25周年記念号)
横浜市内における池の魚類、甲殻類相の現状を把握するために、1994~1997年に行った調査結果を報告する。対象とした池は、ため池が17、公園池が39、遊水地が23、養魚池が1の計80地点であった。池面積は25~46200㎡の範囲であった。水質環境は、栄養型区分から見ると、公園池が過栄養型、その他は富栄養型で、水の色では、茶色、緑色、灰色の順に多く、透明... -
身近な生きものについてアンケート調査結果(第1報)(横浜市環境科学研究所報 第25号)
本調査は、現在の小学生の身近な生き物についての意識、経験、知識及び考え方を把握するため、小学生を中心に中学生、大学及び保護者を対象にアンケート調査を実施したものである。調査の結果、小学生の身近な生き物とのふれあいについては、保護者や大学生に比べ減少しているが、知識や意識はそれほど相違がないことが把握できた。考え方については、大学生や保護者に比べブラック... -
人工衛星データを用いた横浜市内の常緑樹林と落葉樹林の分布状況(横浜市環境科学研究所報 第25号)
ランドサット衛星データより横浜市内の常緑樹林と落葉樹林の分布を調べるアルゴリズムを開発した。1997年のデータより、横浜市内の10アール以上の森林は16%であり、その内落葉樹林が10%、常緑樹林が6%と推測された。また市内の落葉樹林の面積は4500ha程度であり、常緑樹林は3170ha程度と見積もられた。 -
飼育水槽におけるヌカエビの繁殖様式(横浜市環境科学研究所報 第25号)
ヌカエビの繁殖生態を解析するために室内飼育による繁殖様式と交尾行動を観察した。繁殖様式では、雌の同一個体が多数回産卵し、5月から9月まで最大5回、10月までは7回行なっていた。雌の抱卵日数は、平均16日、抱卵からつぎの抱卵まで約10日前後であった。繁殖期間中の体重の変化は雄が増加を示したが、雌は変化がなかった。同一個体の抱卵回数によるフ化個体数は1回目... -
谷戸におけるヌカエビの生息場所と生態との関係 -生物多様性の保全に向けて-(横浜市環境科学研究所報 第25号)
大岡川源流部に生息するヌカエビの地域個体群を対象に、生息環境と生態との関係を検討した。池集団の頭胸甲長の季節変化は、雌の繁殖期が5、6月から8月の下旬までで、生長パターンは、新年級群が8月に出現し、11月まで生長、12月から翌年の2月までは生長が停止した。3月から5月まで再び生長し繁殖集団に加わると思われた。この年級群は、2、3の山を形成する。雄は、雌... -
植物プランクトンの増殖に伴うN/P比の変化に関する理論的考察および東京湾におけるN/P比の空間分布の季節別特徴(横浜市環境科学研究所報 第24号)
まず、植物プランクトンの増殖に伴う海水のN/P比(無機態の窒素とリンの重量比)の理論変化について考察した。その結果、N/P比を大きく変化させる因子として、海水の栄養塩濃度が低いこと、海水のN/P比とレッドフィールド比との差が大きいことの2つが挙げられ、前者のほうが大きく影響すると示唆された。次に、東京湾内41地点の1985年4月から1990年3月までの... -
アロザイム分析によるヌカエビ集団の遺伝学的および形態学的研究 -生物多様性の保全に向けて-(横浜市環境科学研究所報 第24号)
ヌカエビを対象にアロザイムの分析条件の検討を行った。これをもとに大岡川集団の遺伝子組成の把握および集団内の遺伝的変異を解析した。その結果、試料は腹部筋肉、アロザイム分析は、グルコース6燐酸イソメラーゼ(Gpi)、マンノース6燐酸イソメラーゼ(Mpi)、ホスホグルコムターゼ(Pgm)の3酵素で行った。本水系内の分集団間で遺伝子頻度に差がなかった。いたち川... -
横浜市内河川の魚類における寄生虫の感染状況(横浜市環境科学研究所報 第23号)
「自然環境の回復と生態系に関する研究」の一環として1996年度に、横浜市内4水系の魚類の寄生虫の実態把握、河川間での比較、環境指標種としての検討、公衆衛生面での問題点などについて調査した。本報告では、調査の概要について紹介した。検査に供した魚は5科11種で、その内アユ、マハゼ、ボラを除く8魚種から寄生虫が確認された。確認された寄生虫は、原虫類1種、単生... -
横浜市域における地表温度予測モデル(その2) -1995~1997年の解析結果-(横浜市環境科学研究所報 第23号)
都市でのヒートアイランド現象の推定のため既報で構築した地表温度予測モデルを用いて1995年から1997年までの3ヵ年間について、植生の減少に伴う横浜市域での地表温度の上昇予測をおこなった。その結果、横浜市内の現状の植生域(森林、田、畑、公園など)が将来全て市街域(宅地、工場など)に変わった場合、横浜市全域の年平均地表温度は0.1~0.3℃程度上昇するも... -
ダイアジノンの密封系における分解とミジンコへの生態影響について(横浜市環境科学研究所報 第22号)
ダイアジノンは、有機リン系の殺虫剤で一般的に使用されており、平成8年に初貝らが行った横浜市内の河川調査においても、寺家川、平戸永谷川をはじめ、多数の河川から指針値以下(要監視項目、0.005㎎/l)の濃度であるが検出されている。また、土壌中においては速やかに分解するものの、水溶液中では、残存性を示したことから、生態系への影響が懸念されるところである。そ... -
横浜市沿岸域のプランクトン相(横浜市環境科学研究所報 第22号)
横浜市沿岸域のプランクトン調査は、1974年の福嶋・吉武による調査にはじまり、その後、3年に一度の頻度で調査は行われ、1989年以降は富栄養化発生の把握手法検討のための調査の一環として人工衛星運行日に合わせて毎年調査をおこない、1994年までの結果はすで報告している。今回の調査は1995年度に人工衛星運行日に合わせて行われたものである。 -
キショウブ(Iris pseuda-corus L.)による窒素・りんの濃度と除去速度(第3報)(横浜市環境科学研究所報 第22号)
キショウブ(Iris Pseuda-corus L.)... -
キショウブ(Iris pseuda-corus L.)による窒素・りんの除去速度と原水濃度(第2報)(横浜市環境科学研究所報 第21号)
キショウブ(Iris Pseuda-corus L.)... -
キショウブ(Iris pseuda-corus L.)による窒素・りんの除去速度と原水濃度(第1報)(横浜市環境科学研究所報 第20号)
キショウブを水耕法により植栽した人工水路で水耕培養液を供試液として栽培実験を行ったところ、窒素、りんの除去速度は供試液中の窒素、りんの濃度によって変動し、全窒素(T-N)の濃度範囲が13~50mg/ℓの場合、T-Nの除去速度はキショウブ一株について22.69mg/株/日、植栽水路の単位面積(約94株)について2.14g/㎡/日であった。また、T-Nの濃...