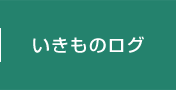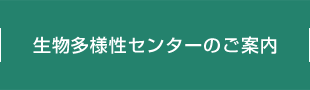-
東京湾で観察された、渦鞭毛藻 Alexandrium minutum Halim (横浜市環境科学研究所報 第30号)
横浜市では、1987年から赤潮発生時期を中心に毎年、プランクトン調査を実施している。この調査の中で1999年に渦鞭毛藻のAlexandrium属の種が初めて東京湾、横浜市沿岸で観測された。... -
分水路取水庭の河川機能に及ぼす影響に関する研究(横浜市環境科学研究所報 第30号)
都市河川の大岡川水系において治水用の分水路取水庭を中心として水質・底質・付着物・シオグサ・魚類の調査を行った。その結果、日野川の取水庭で水質のBODが上流より約4割減少し、滞留による浄化作用がみられた。2箇所の分水路取水庭の底質は源流域からの土壌や植物由来有機物の多寡によるとみられる違いがみられた。また、冬季の取水庭の浚渫によって流出した土砂が下流の河... -
横浜の森林土壌の酸性化の実態と酸中和能(3) -市内森林土壌の酸中和能(ANC)の状況-(横浜市環境科学研究所報 第29号)
横浜市内の森林土壌のANC( 酸中和能)の状況を把握することを目的に、前報で得た交換性塩基データ及び、交換性塩基総量(交換性Ca+交換性Mg+交換性Na+交換性K) とANCの関係式(黒ボク土: Y=1.15X-1.06 (R²=0.9956)、褐色森林土: Y=0.82X-2.35 (R²=0.9963)... -
横浜の森林土壌の酸性化の実態と酸中和能(2) -人工酸性雨・カラム試験による酸中和能の測定-(横浜市環境科学研究所報 第29号)
横浜市内の森林土壌が持つANC(酸中和能)の状況を把握することを目的に、前報で得た土壌試料のうち、地域、土壌型、樹種、土壌理化学特性等、種々異なる11試料を選び、人工酸性雨-カラム試験によりANCを測定した。その結果、11の試料のANCは0.8~18.2meq/100gの範囲内にあり、これを地域、樹種別で比較すると、林外(平均=18.1、n=2)、道路... -
横浜市におけるヒートアイランド現象が及ぼす熱中症や動植物への影響(横浜市環境科学研究所報 第29号)
横浜市におけるヒートアイランド現象の影響を把握するため、気温の経年変化を踏まえた上で、熱中症や動植物への影響について検討した。横浜地方気象台の観測データ(1928~2000)を基に、横浜の年平均気温の上昇率を算出した結果、約2.6℃/100年であった。都市化の影響が少ない中小都市の上昇率が約1.0℃/100年であることから、その差約1.6℃はヒートアイ... -
港北区役所屋上緑化での温度低減効果 -2004年夏期の解析-(横浜市環境科学研究所報 第29号)
港北区役所屋上緑化での2004年夏期の大気気温、屋上緑化部分地中3cm,10cm,20cm、屋上コンクリート表面温度、日射量、風向風速について観測した結果を解析した。その結果、夏期のコンクリート表面温度は最高で50℃以上にも達するが、緑化部分の地中3cmでは最高でも40℃程度であり、地中20cmでは30℃前後でほぼ一定なことがわかった。日射量と温度との... -
大岡川の河川構造物が魚類流程分布に与える影響に関する調査報告(横浜市環境科学研究所報 第29号)
大岡川を対象に河川構造物が魚類流程分布に与える影響を解析するために周年調査を行い、以下の結果を得た。床固工(落差工)等の構造物は33基が設置され、高さ1m以上の落差工が上流域に4基(D3~6)、中流域に1基(D29)が設置されていた。淵型はF型の落ち込み淵が最も多く、ついでS型の基質変化型が多かった。... -
瀬谷狢窪公園(横浜市)の水域生態系(横浜市環境科学研究所報 第29号)
瀬谷狢窪公園および近接地を流れる水路と、和泉川の公園に近接する部分を対象に、水環境と水域および陸域生物の調査を行った。公園内の湧水の硝酸態窒素濃度が高い傾向がみられたが、水環境は良好な状態が維持されていた。両水域の生物群集はそれぞれの環境特性を反映し、水路にはホトケドジョウ、サワガニ、オニヤンマ、オナシカワゲラ属、ヘビトンボ類、カワニナ、モズクなどの源... -
河川における環境基準達成のための要因に関する研究(第3報) -鶴見川水系-(横浜市環境科学研究所報 第29号)
横浜市北部の鶴見川水系のおいて河川の環境基準に影響の大きい流入源として下水処理場を取り上げ、その上下流で水質・底質・付着物・付着藻類について調査を行った。その結果、河川水量の半分程度を下水処理場放流水が占め、水量確保の面では処理場放流水の貢献は大きかった。水質のBODは冬季に硝化の影響により処理場の下流等で環境基準を超えており、また処理場はリンの主たる... -
エコロジカルネットワーク調査『トンボはドコまで飛ぶか』調査結果(横浜市環境科学研究所報 第28号)
京浜臨海工業地帯に立地する5事業所敷地内の池及び樹林地において、企業、市民、行政、専門家の協働によるトンボの移動調査を2003年9月17日及び18日の2日間にわたり実施した。その結果、361匹11種のトンボを捕獲し、内51匹は再捕獲されたものであった。このうち、1匹は、事業所間約2kmを移動して再捕獲されたものである。このことは、京浜臨海部の工場事業所... -
横浜市沿岸域で発生した Mesodinium rubrum による赤潮(横浜市環境科学研究所報 第28号)
2003年5月に東京湾奥から横浜市沿岸域にかけて大量のMesodinium rubrum... -
河川における環境基準達成のための要因に関する研究(第2報) -柏尾川水系-(横浜市環境科学研究所報 第28号)
横浜市南部の柏尾川水系において河川の環境基準に影響の大きい流入源として下水処理場を取り上げ、その上下流で水質・底質・付着物・付着藻類について調査を行った。その結果、河川水量の半分以上を下水処理場放流水が占め、水量確保の面では処理場放流水の貢献は大きい。水質のBODは硝化の影響が加わって処理場の下流で高くなる傾向があり、またリンの主たる排出源となったいた... -
ヒートアイランド対策としての屋上緑化の温度低減効果調査 -2000年5月~2001年4月の結果-(横浜市環境科学研究所報 第27号)
屋上緑化の温度低減効果の調査を2000年5月から2001年4月の一年間について行った。その結果、夏期の晴天日では屋上コンクリート面では最高60℃にも達するが、屋上緑化の地中20cmでは30℃以下であり、屋上緑化による温度低減効果は夏期に集中していることがわかった。またヒートアイランド対策としての屋上緑化のためにはその土壌の厚さは通常20cm程度必要であ... -
閉鎖水域の日本丸ドック(横浜港)における水質状況(横浜市環境科学研究所報 第27号)
調査期間中、海水循環ポンプ停止に伴うドック内の水質悪化は見られず、ドック内の透明度は、ドック外に比べて、常に高く、赤潮の発生しやすい春季から夏季においても、ドック外の透明度が1.5mに対して、ドック内では5.7m以上であった。ドック内は、ドック外に比べて閉鎖的な水域であり、赤潮の発生しやすい時期においても、赤潮が発生しないという現象は、閉鎖的な水域の浄... -
アロザイム分析によるヌカエビ集団の遺伝学的および形態学的研究(第2報) -横浜市域および三浦半島の集団間の比較-(横浜市環境科学研究所報 第27号)
神奈川県東部の横浜市域および三浦半島に分布するヌカエビを対象に遺伝的特徴、形態等について集団間の比較検討を行い、以下の成績を得た。酵素としてグルコース6燐酸イソメラーゼ(Gpi)、マンノース6燐酸イソメラーゼ(Mpi)、ホスホグルコムターゼ(Pgm)の3酵素で解析を行った結果、集団間の遺伝子頻度に差が認められ、Mpi、Pgmの遺伝子座は集団間で差が大き... -
河川における環境基準達成のための要因に関する研究(第1報) -中堀川-(横浜市環境科学研究所報 第27号)
横浜市内においてBODが環境基準を上回る小河川の例として中堀川を取り上げ、水質・底質・付着物・付着藻類について流程調査を行ったところ、本流の2割以上の流量を占める支流の流入点より下流で水質が悪化していた。底質は流入点の直下の淵で酸化還元電位が0mV付近まで低下しており、付着物は流入点より下流の地点で強熱減量や総リンが高い傾向にあった。付着藻類による水質... -
横浜市内河川の重金属濃度とミジンコの生存率について(横浜市環境科学研究所報 第26号)
横浜市内において、平成9年7~12月河川水を採水し、重金属(銅、カドミウム、亜鉛、鉛)の調査を行うとともに、ミジンコを用いて河川水中の生存率を調べた。河川水に含まれる重金属の分析を行った結果、カドミウムはいずれの試料も1㎍/ℓ... -
横浜の森林土壌の酸性化の実態と酸中和能(1) -スギ林、広葉樹林、森外土壌の調査-(横浜市環境科学研究所報 第26号)
1999年11月~2001年3月の寒候期、横浜市内において、スギ林土壌38、広葉樹林土壌52、林外(裸地)土壌22、合計112の土壌試料を採取し、土壌pH、交換性塩基、交換性Al、水溶性Al等を調べた。スギ、広葉、林外の平均pH(H₂O)は、それぞれ4.70、5.57、6.49、であり、スギ林土壌が低く、特に道路近傍のスギ林土壌は平均が4.34とかなり... -
身近な生きものについてアンケート調査結果(第2報)(横浜市環境科学研究所報 第26号)
本調査は、現在の小学生の身近な生きものについての意識、経験、知識及び考え方を把握するため、小学生を中心に中学生、高校生、大学及び保護者を対象にアンケート調査を実施したものである。昨年度までの解析では、身近な生きものとのふれあい、知識及び意識、考え方などについて年代別男女別の特性を確認した。本報告では、昨年度の解析結果を基に、身近な生きものの好き嫌いと体... -
横浜市沿岸のプランクトン相調査(第2報)(横浜市環境科学研究所報 第26号)
1998年から2000年までの過去3年間のプランクトン相の月別特徴を中心に報告した。この3年間の調査の中で、珪藻のCoscinodiscus spp. や渦鞭毛藻のGymnodinium sp.など外洋のプランクトンが観察されるようになってきたこと、今まで東京湾ではほとんど見られなかった有害プランクトン渦鞭毛藻のAlexandrium...