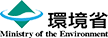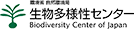モニタリングサイト1000では、2003年に事業を始め、15年以上が経過し、多くのことが明らかになってきました。その中の一部をご紹介いたします。
2021年3月時点
| 生態系 |
調査内容 |
分かってきたこと |
| 高山帯 |
高山帯調査 |
- 前年の気温が影響を及ぼすハイマツの年枝伸長量の経年変化が、全国的に増加傾向
- マルハナバチの季節活性の年変動に比べて、雪田群集の開花時期の変動はさらに大きい
→雪解け時期が早まり、雪田群集の開花時期が早まるような状況が頻繁に起こると、マルハナバチの個体群維持や、引いては高山帯生態系に深刻な影響が及ぶことが懸念
- 風衝地と雪田の植生間には同一山域内で比較しても大きな違いが見られ、雪田植生は山域間において類似性が高く、一方で風衝地植生は山域固有性が高い
|
森林・草原 |
森林・草原調査 |
- 調査地の年平均気温が高い年ほど、秋季の落葉時期が遅くなった
- コナラ属、カエデ属、カバノキ属では、気温が高いほど種子の落下時期のピークが遅い傾向
- 樹種タイプ組成から、より温暖な気候に生育する樹種タイプの個体数が増加している傾向
|
| 陸生鳥類調査 |
- 南方性種の北上傾向・分布拡大傾向
(リュウキュウサンショウクイ)
- 外来鳥の分布拡大(ソウシチョウ、ガビチョウ)
- ニホンジカの林床食害による影響
(藪を利用する鳥類の減少:ウグイス、コルリ等)
|
| 里地 |
里地調査 |
- 里地における身近なチョウ類(ミヤマカラスアゲハやミヤマセセリ等)の減少傾向
- 里地における、水辺・草地の指標種(ホタル類やカヤネズミ等)や里地に生息する普通種(ハシブトガラスやヒヨドリ等)の記録個体数減少傾向
- 外来生物(アライグマやガビチョウ等)や大型哺乳類(ニホンジカやイノシシ)の、記録個体数の増加傾向及び分布の拡大傾向
- 南方系チョウ類(ナガサキアゲハ等)の分布北上傾向
- アカガエル類の産卵ピークの早期化
- カヤネズミの生息面積及び利用可能草原面積の減少
|
| 陸水域 |
湖沼・湿原調査 |
- 湖沼における国外外来魚(ブラックバスやタイリクバラタナゴ等)、国内外来魚(琵琶湖・淀川水系原産のゲンゴロウブナやハス等)の生息状況
- 国内希少野生動植物種の再記録(塘路湖におけるカラフトグワイ、約30年ぶり)
|
| ガンカモ類調査 |
- ハクチョウ、ガン、カモ、カイツブリ、オオバンの仲間の個体数増減傾向
- 希少なガンカモ類の個体数増加傾向(ハクガン、シジュウカラガン)
- ハクチョウ類の幼鳥率の地域差
|
| 砂浜 |
ウミガメ類調査 |
- ウミガメ類(アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ)の上陸・産卵状況
- 性決定等ウミガメ類の卵の発生に影響を及ぼす砂中温度の経年変化
- 哺乳類による卵食害の状況把握(リュウキュウイノシシ、タヌキ)
|
沿岸域 |
磯調査
干潟調査
アマモ場調査
藻場調査 |
- 各生態系における生物相及び生物量の動態
(台風等の影響によるアマモ場の衰退;指宿サイト、アントクメ藻場の消失;薩長摩長島サイト)
- 東日本大震災による生態系への影響や回復状況
(干潟底生生物の生息密度の激減及び回復;松川浦サイト、アマモ場の消失及び浅場を中心とした被度回復;大槌サイト、地盤沈下による藻場群落の消長;志津川サイト)
- 新種の発見(カビラスナシャコエビ;石垣川平湾サイト、バンズマメガニ;盤洲干潟サイト)
- 調査サイトにおける希少種及び外来種の初記録
(シカメガキ;中津干潟サイト、ヒガタアシ;汐川干潟)
|
| シギ・チドリ類調査 |
- 全調査期間(春期・秋期・冬期)における、国内に渡来するシギ・チドリ類の最大個体数の減少傾向(1975年~2017年で約40%の減少)
- 日本のシギチ類の中継地としての重要性
- 種毎の個体数の増減傾向評価(例:シロチドリ・タマシギ・ハマシギの顕著な減少等)
- 地域別・海域別の個体数の増減傾向評価
(例:東京湾、伊勢・三河湾において減少傾向だが、有明海では安定している)
- シギ・チドリ類の渡来個体数に影響を与えている可能性がある要因
(例:繁殖地(ロシア高緯度地域)の気候が、秋期に渡来するシギ・チドリ類に影響をあたえている可能性が示唆された。)
|
| サンゴ礁 |
サンゴ礁調査 |
- 2003年から2017年までの全国の平均サンゴ被度が減少傾向
- 主なサンゴ礁域において広く優占するミドリイシ類の割合が、年々減少傾向
- 主なサンゴ礁域におけるオニヒトデの食害状況について、2011年には多くのサイトで大発生が見られたが、その後減少傾向になり、2015年以降は通常分布状態
|
| 小島嶼 |
海鳥調査 |
- 繁殖地において海鳥の生息を妨げるおそれのある環境要因
- 希少種、南限・北限種等の調査対象種の推定巣数(密度)の増減傾向
|
| 各生態系共通 |
- 調査サイトにおける生物相・生物量・分布の傾向
- 希少種の出現状況
- 外来種の分布拡大
|