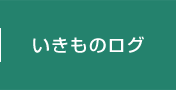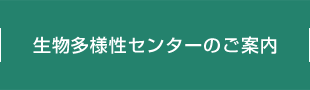-
境川・引地川の淡水魚類、底生動物、藻類について(横浜市公害研究所報 第15号)
境川、引地川の魚類、底生動物、藻類の分布状況を夏期、冬期に調査し、河川環境と水質汚濁との関係について検討した。魚類の出現種類は、境川で8科16種、引地川が5科8種であった。分布状況は、境川が自然環境が残る源流部でカジカが出現し、アブラハヤが優占種であった。上流~下流は出現魚種が少なく、下流になると回遊魚、周縁性魚が出現した。引地川は全体に少なかった。魚... -
鰓の形態観察による酸欠死の有無の推定方法(横浜市公害研究所報 第15号)
魚の死亡原因究明法の一つとして、鰓の形態観察による酸素欠乏死の推定方法について検討した。検討の結果、鰓の形態観察が、酸素欠乏による死因の推定に有効であることが明らかになった。 -
赤潮の消長における気象因子の影響(横浜市公害研究所報 第15号)
光学的自動測定機を組み込んだブイを横浜市沿岸海域に設置して、夏期の約3ヶ月間、水質の連続観測を行い、植物プランクトンの消長に対する気象因子の影響を検討した。その結果、植物プランクトン量の増減は水温変動と密接に対応しており、特に降雨後の水温の上昇はその増殖速度を高めること、また水温が高めに維持されると成層構造が発達し栄養塩の豊富な河川水が海域上層に保持さ... -
紫外部吸収、濁度、蛍光強度の連続測定による横浜市沿岸海水の有機汚濁状態の観測(横浜市公害研究所報 第14号)
富栄養化した海域では、植物性プランクトンの増殖に伴う海水中の有機物の増加が、水質の有機汚濁の一因とされている。しかし、植物プランクトン群集の出現する種類、出現頻度、現存量、消長の期間等は、その海域の富栄養化状況の程度をはじめとして、潮流、海水温、水塊構造等の海象、さらには日射量、気温、風向風力、降雨等の気象条件の影響を受け、大きな変動を余儀なくされてい... -
横浜市内河川における従属栄養細菌 -大岡川-(横浜市公害研究所報 第14号)
横浜市内河川(大岡川)の水質を調査したところ、源流部(氷取沢)においてはBOD 0.8mg/ℓ、従属栄養細菌数 1.0 x 10⁴ ml⁻¹、中流部(日下橋)においては BOD 4.1mg/ℓ、従属栄養細菌数 2.4 x 10⁵ ml⁻¹ となり、BOD... -
魚類へい死原因究明のための研究I -コイの溶存酸素低下時における血液性状の変化-(横浜市公害研究所報 第14号)
市内河川で発生する魚類のへい死事故の原因究明の一助とするために、コイの溶存酸素量低下時の生理学的反応を検討した。実験条件は、流水式の実験装置を用いDO量低下速度が約3時間で1mg/ℓ... -
横浜港における底質の堆積要因(横浜市公害研究所報 第14号)
横浜港の内港地区における底質の堆積要因及び堆積速度について明らかにするため、セディメントトラップによる調査を約1年間行った。その結果、帷子川の河口前面にあたる地点では底質に堆積する沈降性粒子のうち、河川流入負荷の寄与率が約29%程度であると推察された。また、生物生産は7~9月にかけて増大し、水深3m程度の表層においては珪藻による生物生産負荷が沈降性粒子... -
水生植物と接触ばっ気法の組合せによる水質浄化法の検討(第2報)(横浜市公害研究所報 第14号)
固定床式接触ばっ気装置と水生植物植栽水路(アシ、マコモ、キショウブ)との組合せによる水質浄化実験を実際の池水を用いて行った結果、植物としてキショウブを植栽することにより透視度、SS、COD、T-N及びT-Pについて年間を通して良好な処理効果が得られた。植物の生長は、マコモ及びキショウブで良くアシでは悪かった。また植物体の回収については、マコモ及びアシで... -
横浜港における水質の推移 -横浜検疫所の1956年から1972年までの調査結果-(横浜市公害研究所報 第13号)
横浜検疫所が行った1956年から1972年までの、横浜港4地点における水質調査結果を解析した。その結果、過マンガン酸カリウム消費量の濃度は1956年に比較して、1958年には約2倍に、1956、66年には約6倍にも増加しており、経済の高度成長に伴い水質汚濁が進行していった状況をよく表していた。アンモニア性窒素は全体としては増加傾向を示していた。また、沿... -
水生植物と接触ばっ気法の組合せによる水質浄化法の検討(第1報)(横浜市公害研究所報 第13号)
池や小河川等比較的小規模な水域の水質浄化方法の一つとして、SSの除去を目的とした固定床式接触ばっ気装置と修景効果のある水生植物を植栽した人工水路との組合せによる処理実験を実際の池水で行ったところ、SSの除去率80%以上、処理水の透視度100度以上の結果が得られた。また、池水中の全窒素、全りんの濃度は低かったが、この実験装置により、それぞれ36%、73%... -
魚類へい死事故に関する調査(第2報) -アカヒレを用いた大岡川河川水の濃縮毒性-(横浜市公害研究所報 第13号)
魚類のへい死原因究明に関する研究の一環として、1986年の柏尾川調査に引き続き1987年に大岡川について調査を行った。その結果、柏尾川の場合と同様、毒性の強さはNH₄-N 濃度と対応しており1日の中では24時頃、季節としては冬期に毒性が強いことが明らかとなった。しかし、実際の河川の中においては、NH₄-N... -
海水中の高級脂肪酸とSkeletonema costatum の増殖との関係について(横浜市公害研究所報 第13号)
海域における高級脂肪酸の消長を検討するため、珪藻のSkeletonema costatumの培養実験により脂肪酸濃度とSkeletonema costatumとの関係を検討した。Skeletonema costatumの増殖により脂肪酸が生成された。脂肪酸は海水中でその濃度が減少した。また脂肪酸が存在する海水中ではSkeletonema... -
Skeletonema costatumの培養試験による横浜市沿岸域の藻類増殖潜在能力の評価(横浜市公害研究所報 第13号)
東京湾で代表的に出現する植物プランクトンのSkeletonema... -
残留塩素のコイの鰓呼吸に及ぼす影響(横浜市公害研究所報 第12号)
1.5ℓ容量のガラス製気密容器を用いた呼吸量測定方法による、残留塩素のコイ呼吸量に及ぼす影響について検討を行った。0~1.0mg/ℓ濃度の残留塩素に5分間曝露した後、その呼吸量を測定した結果、対照群の319±8㎍/g ・hrに対して、0.3mg/ℓでは257±14㎍/g ・hr... -
魚類の簡易呼吸量測定法(横浜市公害研究所報 第12号)
1.5ℓ容量のガラス製気密容器を用いた、水中溶存酸素消費量による魚類の呼吸量の簡易な測定法について、コイを用いて試みた結果、最終溶存酸素濃度を5.0mg/ℓ以上で、測定時間20分にして測定し、319±8㎍/g ・hr と、精度も良く、安定した測定結果を得ることができた。水質汚濁の魚類の鰓呼吸に与える影響を知る方法として有効であることがわかった。 -
飼育コイを指標とした河川水質のモニタリング(横浜市公害研究所報 第12号)
河川水のモニタリング方法として、河川水の流水方法で、試験用の孵化後約1ケ月のコイを1年間飼育し、その体内の蓄積物質を測定する方法を試みた。この結果、重金属類の蓄積量は対照群と実験群の間にほとんど差は認められなかったが、有機塩素化合物では差が認められた。PCBは対照群の70ng/gに対し、実験群では330ng/gであり、同様にPP'-DDEは0.070n... -
魚類へい死事故に関する調査 -柏尾川-(横浜市公害研究所報 第12号)
魚のへい死がしばしば派生する横浜市南部を流れる柏尾川において、降雨時とその後の水質変化および魚に対する濃縮毒性の変化を調査した。その結果、毒性の強さはNH₄-Nと対応していることが明らかとなった。また柏尾川水系4地点で水質および濃縮毒性の季節変化を調査した結果、地点により毒性の強さは異なるとともに、季節的にも異なっていた。そして、濃縮毒性がアンモニア(... -
底質柱状試料からみた横浜港の汚染の変遷(横浜市公害研究所報 第12号)
横浜港における底質柱状試料の金属類、油分、科学物質および珪藻について調査し、過去の連続的、多面的な水質汚濁の変遷について推察した。また、東京湾における同様な調査結果、石油などの生産量のデータと対比させることにより、堆積年代の推定を試みた。その結果、次のことが明らかとなった。... -
横浜市における魚類へい死事故について(横浜市公害研究所報 第11号)
昭和51年度から59年度に横浜市水域で発生した魚類へい死事故について、事例解析を行った結果、以下のことがわかった。 (1)へい死事故は昭和51年度から59年度の間に85件発生し、原因別に酸欠(豪雨に伴う汚染底質の巻き上げや赤潮など気象条件に関係するもの)・工場(工場および工事排水)・原因不明が各々56、13、31%を占めた。... -
横浜市における魚類を指標とした工場排水の規制手法に関する研究(その2)(横浜市公害研究所報 第11号)
本報告では指針に基づく実際の工場の飼育状況や検査結果、排水の評価について、昭和54年度から昭和58年度までの5ヶ年間について5工場を対象に検討した結果を示した。その結果、水質分析では把握できない排水の生物への影響について一定の評価が可能であることが示唆された。