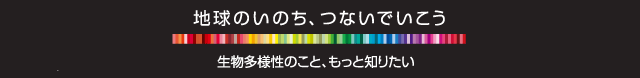事業活動と生物多様性にはどんな関係があるのか?
生物多様性の保全のために、企業は何をすればいいのか?
そんな悩みを抱える事業者のために「生物多様性民間参画ガイドライン」を発行しました。ここでは、策定の背景や、経緯、位置づけ、対象を紹介しています。
生物多様性民間参画ガイドライン
ガイドラインの目的
本ガイドラインは、生物多様性に関する活動への事業者の参画を促すことを通じて、生物多様性の保全と持続可能な利用を促進することを目的としています。
なお、事業者による生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取組は、業種や業態、生物多様性との関わり方に基づいて、事業者が主体的に考え、自主的な取組の一環としてなされるべきものです。このため、本ガイドラインは法律の義務規定の詳細を定めるような規制的なものではなく、生物多様性基本法の責務規定等に基づき、事業者が主体的に取り組む際の指針を提供するものとしています。
ガイドラインの対象
本ガイドラインは主に事業者を対象としています。なかでも、初めて生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取組を行おうと考えている実務担当者に活用いただくことを期待し、事業活動と生物多様性の関係を紹介するとともに、事業者が社会からどのような取組を期待されているのかを具体的に解説しています。
また、既に先進的・模範的取組を実施している事業者にとっても、その内容の確認やさらなるレベルアップのための「参考書」として活用いただける構成としています。
策定の背景・経緯
環境省では、生物多様性の保全と持続可能な利用を進めていく上で、企業活動が重要な役割を担っているという認識の下、事業者向けに、基礎的な情報や考え方などを取りまとめた「生物多様性民間参画ガイドライン」第1版を 2009 年に策定し、 2017 年に改訂版である第2版を発行しました。
その後、ビジネスと生物多様性に関する国内外の多くのイニシアチブが発足し、影響評価や情報開示に関する枠組みの検討が活発に行われています。また、 2021 年に G7 で合意された「自然協約」を踏まえ 、 我が国では 陸と海の保全に関する 「 30by30 目標 」 が設定され、 企業等 の保有地等も生物多様性保全に貢献する地域としてその一部に組み込むなど、 民間による生物多様性保全への期待は年々高まっています。さらに昨年 12 月に決定された生物多様性 に関する 新たな 世界目標 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」には、事業者に関する多くの目標が含まれています 。
こうした背景を踏まえ、 2021 年度に有識者からなる「生物多様性民間参画ガイドラインの改訂に関する検討会」での議論を踏まえ、2023年に改訂版である第3版を出版しました。
●第1版作成
2008年11月10日~2009年7月24日
生物多様性民間参画ガイドライン検討会 計5回開催
2009月 5月13日~6月12日
パブリックコメント
○2009年8月20日
生物多様性民間参画ガイドライン(第1版)公表
●第2版作成(改訂)
2016年10月26日~2017年12月6日
生物多様性民間参画ガイドラインの改定に関する検討会 計4回開催
2017年10月24日~11月23日
パブリックコメント
○2017年12月8日
生物多様性民間参画ガイドライン(第2版)公表
●第3版作成(改訂)
2021年8月24日~2023年1月27日
生物多様性民間参画ガイドラインの改定に関する検討会 計6回開催
2023年2月10日~2月28日
パブリックコメント
○2023年4月7日
生物多様性民間参画ガイドライン(第3版)公表
生物多様性民間参画ガイドライン(第3版)の構成
ガイドラインに関係する資料は以下の4種類です。
改定前
生物多様性民間参画ガイドライン(第2版)の構成
ガイドラインに関係する資料は以下の3種類です。