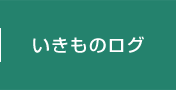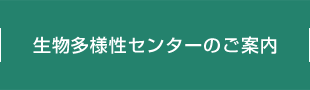| メタデータのファイル識別子 |
gxyh_yokohama_BD_501 |
| 題名 |
鶴見川水系における谷戸水路と河川の人工構造物と魚類流程分布との関係(横浜市環境科学研究所報 第31号) |
| 公開日 |
2007年03月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 |
|
| 管理者情報/管理者組織名 |
横浜市環境創造局環境科学研究所 |
| 管理者情報/管理者職務名 |
|
| 管理者情報/責任者職務コード |
003 |
| 管理者情報/国 |
日本 |
| 管理者情報/郵便番号 |
221-0024 |
| 管理者情報/都道府県 |
神奈川県 |
| 管理者情報/市区町村 |
横浜市 |
| 管理者情報/所在地 |
神奈川区恵比須町1番地
澁澤ABCビルディング1号館5階 |
| 管理者情報/電話番号 |
045-453-2550 |
| 管理者情報/ファックス番号 |
045-453-2560 |
| 管理者情報/電子メールアドレス |
ks-kanken@city.yokohama.jp |
| 管理者情報/案内時間 |
9:00-17:00 |
| 管理者情報/問い合わせの手引き |
土日祝日休業 |
| オンライン情報源のURL |
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/kansoku/science/shiryo/syohou.html |
| 地表の範囲名称 |
神奈川県-横浜市 |
| 西側境界経度 |
139.464783 |
| 東側境界経度 |
139.725328 |
| 北側境界経度 |
35.592661 |
| 南側境界経度 |
35.312502 |
| 時間範囲 |
|
| 解像度コード |
|
| データセット言語コード |
ja |
| データセットの文字符号集合 |
N/A |
| 要約 |
谷戸生態系の生物多様性の保全、再生のための基礎資料を得るために、鶴見川流域の谷戸と支川、本川との魚類流程分布と人工構造物との関係について検討した。対象水域は、A、B谷戸の4水路、小溝には堰、落差工が設置され、その落差高の平均値は20cm以上、流れ幅が0.2~1.8mであった。谷戸水路と支川Cとの合流点は2ヶ所あり、1m以上の落差高だった。支川Cには落差工が5ヶ所、可動堰1ヶ所であった。水温は谷戸水路ではAR、BRの水路で低かった。 出現した魚類は、7科17種、魚類別の採集割合は、谷戸水路ではホトケドジョウが90%、池ではモツゴが高い割合、Cはオイカワが40%、カワヨシノボリが24%の高い率であった。魚類別の流程分布は、ホトケドジョウが小溝、水路に広く分布し、春から夏にかけてCの下流まで分布を広げていた。アブラハヤはCと本川Dの合流点、オイカワがCとDまでの分布範囲を示していた。カワヨシノボリはCと水路下流まで分布していた。ホトケドジョウの体長分布の季節変化から、5月上旬、水路の上流に2005年級群が出現し、6月に中流とCにも同年級群が出現し、生長段階によって移動分散の範囲が異なっていた。谷戸水路の特徴として水田等が少ないために流下する個体も多かった。人工構造物が双方向移動に影響を及ぼしていると思われた。以上から、地域個体群の保全、再生していくためには、丘陵地、谷戸水路、小溝の保全、水田等の水域面積の拡大、谷戸間の双方向移動を可能にする河川形態、支川と川との関係の修復が必要なことと思われた。 |
| 主題 |
|
| キーワード |
河川構造物、魚類、ホトケドジョウ、谷戸水路、鶴見川 |
| アクセスの制約 |
URLをご参照ください。 |
| 使用の制約 |
著作権は原則として横浜市に帰属します。詳細についてはお問い合わせください。 |
| 空間表現型コード |
|
| フォーマット名 |
|
| 配布に使用するメディア |
|
| メタデータの言語コード |
ja |
| メタデータの日付 |
2020年01月31日 |