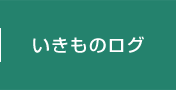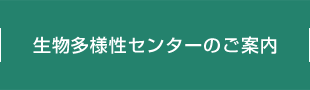| 要約 |
1991年3月~1992年4月までの約1年間、横浜市磯子区で、ヒノキを対象樹木として、樹木内外の降下物、樹幹流を一降水毎採取し、その成分濃度を分析した。その結果得られた樹幹流初期1ℓの分画データと調査地点付近のSO₂, NO₂, SPM, Oxなどの常時監視局データを比較し、樹木汚染と大気汚染物質との関係を検討した。その結果、次の事がわかった。 1)樹幹流の成分濃度と降水間隔の関係を検討した結果、ほとんどの成分は有意な正の直線関係を示し、降水間隔が長くなるほど、樹木の汚染が進んでいくことがわかった。 2)樹幹流のSO₄²⁻, NO₃⁻ 濃度と大気汚染物質の関係を検討した結果、SO₄²⁻ はその前駆物質であるSO₂ の累積濃度及びSPM の累積濃度と有意な関係を示したが、NO₃⁻ はその前駆物質であるNO₂ の累積濃度及びSPM の累積濃度と有意な関係を示さなかった。 3)Ox が60ppb以上を示した時間数と樹幹流のNO₃⁻, SO₄²⁻ 濃度との関係を検討した結果、これらは共に非常に有意な相関を示した。これより、光化学反応により生成されたHNO₃ ガス、H₂SO₄ ミストが樹木に多量に沈着していることが推測された。 4) 非光化学時における樹幹流のSO₄²⁻, NO₃⁻ 濃度と大気汚染物質の関係を検討した結果、NO₃⁻, SO₄²⁻ ともに、 NO₂, SO₂ 及びSPM の累積濃度と有意な関係を示した。これより、光化学スモッグの影響があまりない時期(秋、冬及び春、夏でも日射量の少ない時期)のNO₃⁻, SO₄²⁻ の樹木汚染は、その前駆物質であるNO₂, SO₂ が樹木に吸着して、そこで酸化されてNO₃⁻, SO₄²⁻ になる過程及び、大気中で生成された粒子状のNO₃⁻, SO₄²⁻ が樹木に沈着していく汚染されていく過程が考えられた。 5)筑波における樹幹流のNO₃⁻/SO₄²⁻ 比の季節変化を調べた結果、その挙動は光化学スモッグの影響を示す、春から夏に大きくなる特徴を示した。このことから、東京、川崎等の都市・工業地帯から排出された汚染物質が光化学反応でHNO₃ ガス、H₂SO₄ ミストなどに二次生成されながら内陸部に輸送され、そこでこれらが樹木に沈着されていることが示唆された。 |