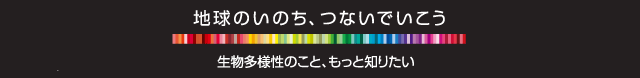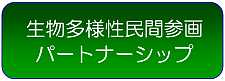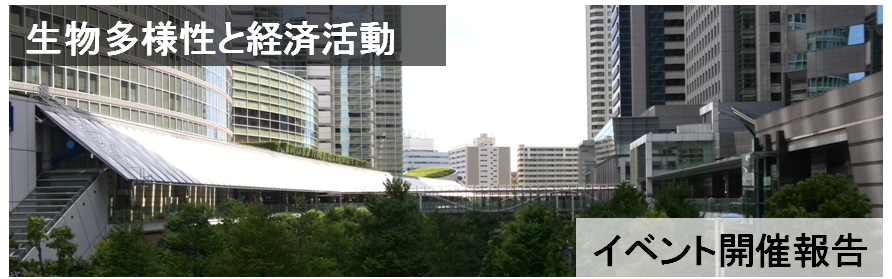
生物多様性民間参画シンポジウム in 札幌の開催結果について
環境省は、9月16日(水)に札幌市内において、生物多様性の取組に関心のある事業者、NPO/NGO及び自治体の方々を主な対象とし、「生物多様性民間参画シンポジウム」を開催しました。
日経エコロジー編集&日経BP環境経営フォーラムの生物多様性プロデューサーの藤田香氏による講演のほか、環境省による生物多様性の民間参画の推進に向けた施策紹介、札幌市による生物多様性保全に関する取組紹介、事業者による事例紹介を行いました。交流会では、登壇の事業者を含む9のブースが出展され、参加者との情報交流が活発に行われました。
その後のパネルディスカッションでは、北海道大学大学院農学研究院教授の中村太士先生をコーディネーターに迎え、生物多様性の民間参画についての意見交換を行いました。
開催概要
「生物多様性民間参画シンポジウム in 札幌」開催概要は以下の通りです。| 日時 |
平成27年9月16日(水)13:30~17:30 |
|---|---|
| 会場 |
札幌国際ビル8階 国際ホール(札幌市中央区北4条西4丁目1番地) |
| 主催等 |
主催:環境省 共催:北海道、札幌市、北海道生物多様性保全活動連携支援センター(HoBiCC)、国連生物多様性の10 年日本委員会(UNDB-J) 後援:札幌商工会議所 |
| 出席者数 |
約100名 |
主催側から環境省が、共催者を代表して札幌市から開会の挨拶がありました。
 |  |
| 徳丸 久衛 (環境省 北海道地方環境事務所長) |
谷江 篤 氏 (札幌市 環境局長) |
2.企業は生物多様性にどのように取り組むか ~最近の動向から~
藤田 香 氏
(日経エコロジー編集&日経BP環境経営フォーラム 生物多様性プロデューサー)

藤田氏からは、すでに省エネ法や水質汚濁防止法等いろいろな規制があり、これらに配慮することで生物多様性に貢献しているにもかかわらず、なぜ、さらに生物多様性が重要といわれているのかについて、生物多様性を取り巻く企業への変化とその特徴、取組を行わない場合のリスクと取組により得られるチャンスを示しつつ、ご説明いただきました。
これまでは社会貢献の一環であった生物多様性への取組が本業でも必要とされており、自然資本として捉えられるようになってきたという大きな変化があり、その特徴としてサプライチェーン全体で考えることや、環境・社会・ガバナンスといった非財務情報開示の流れにより、生物多様性が投資家や消費者によって評価の対象となってきていることをご説明いただきました。また、リスクとして法律違反や企業評価悪化のリスクに加え、自然資源の枯渇・減少による原材料の価格高騰を挙げられました。反対に、ブランドイメージの向上や、認証商品の販売拡大、金融機関からの投資の優遇によって持続可能な企業活動が可能となるといったチャンスがあることを、具体的な事例を交えながらご紹介いただきました。
また、最近の新しい動きとして、ISO14001の改訂、ABS等に関する動向についてもご紹介いただきました。
3.施策紹介 環境省 「生物多様性の民間参画の推進に向けて」
鈴木 宏一郎
(自然環境局 自然環境計画課 生物多様性施策推進室 室長補佐)
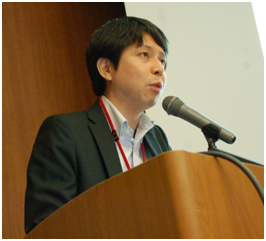
生物多様性に関する事業者の取組状況に関しては、着実に進展しており、例えば生物多様性民間参画パートナーシップの会員のなかでは、生物多様性を経営理念に入れている会員の割合が増加している旨の紹介をしました。一方、愛知目標の達成状況に関して地球規模生物多様性概況第4版(GBO4)では、ほとんどの目標において進展はあったものの不十分との評価にとどまっている旨の紹介をしました。このような状況を踏まえた環境省の施策として、事業者の取組に関する事例集やマニュアルの整備、優良事例の発掘・発信や表彰、業界全体の取組を底上げするための事業者団体の取組を支援するモデル事業の実施等について紹介しました。今後、生物多様性の更なる主流化に向けて、環境省がこれらの取組を進めていくにあたっては、業界団体やNGO等との連携が必要であると述べました。
4.事例紹介 (1) サッポロビール株式会社 「生物多様性に配慮した事業活動」
清水 周子 氏
(サッポロビール株式会社 北海道本社 北海道戦略営業部 副部長)

サッポロビール株式会社の生物多様性への取組は、北海道に根差した共通価値の創造(CSR)を果たすものであり、社会課題の解決と企業の競争力向上の両立であることをお話頂きました。
北海道、コープさっぽろと共同で、カーボンオフセットの取組である「北海道の森を元気にしよう!」キャンペーンを実施しており、一缶につきCO2約66gにあたる1円を相殺するカーボンオフセットにより、北海道の森林保全活動やコープ未来の森基金への寄付を実施した事例をご紹介いただきました。また、こういった活動が北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)での記者発表につながり、広告換算すると800万円強の効果があったことをご説明いただきました。
(2) 生活協同組合コープさっぽろ 「コープさっぽろの生物多様性の保全に向けた環境負荷低減活動の取組」
鈴木 昭徳 氏
(生活協同組合コープさっぽろ 経営企画室 マネージャー)

生活協同組合コープさっぽろからは、社会貢献活動を通じて北海道への貢献を決意されるまでの経緯をご説明いただくとともに、様々な取組事例をご紹介いただきました。
地球温暖化対策として、コープのキャラクターとなっているホッキョクグマを守るための応援プロジェクトを、北海道内のホッキョクグマのいる4動物園と協定を締結して実施しており、地球温暖化の防止は生物多様性保全へもつながるとご説明いただきました。そのほかにも、レジ袋を辞退すると植樹活動に使用する基金に積立をする取組や、グリーンポリエチレンを配合することで北海道内の流通業者で初めてバイオマスマークを取得したレジ袋の使用、事業所・店頭・宅配から回収されたゴミを再資源化するエコセンターの設立といった取組事例をご紹介いただきました。
(3) 株式会社札幌ドーム 「緑豊かな札幌ドームから発信する生物多様性への取組」
江口 修司 氏
(株式会社札幌ドーム 経営企画室長)

株式会社札幌ドームにとって、事業活動の成果は市民道民の皆様や地域社会に還元されていくべきものであり、CSRとは事業活動そのものであるとの考えをご説明いただきました。
札幌ドームは自然と都市を融合させた「スポーツの庭」をコンセプトとして設計されており、敷地内にはボタニカルゾーンやビオトープが設置されていること、これらを利用した巣箱作り教室や札幌ドーム生き物探検隊といった環境啓発活動の取組をご紹介いただきました。また、札幌ドームでは、開業20周年を迎える2021年に向けた環境目標に「生物多様性の保全と環境啓発活動の推進」を位置づけており、その数値目標を「30種以上の鳥が訪れる環境の維持」と「環境啓発企画への参加者を延べ10万人」としているとご説明いただきました。
(4) 大成建設株式会社 「建設業における生物多様性への取組」
埴田 直子 氏
(大成建設株式会社 環境本部 環境計画部 生物多様性・アセスメント室 室長)

大成建設株式会社は、愛知目標のうち建設業と関わりの深い項目として、特に目標14「自然の恵みが提供され、回復・保全される」にハイライトしており、生物多様性に配慮した計画手法である「エコロジカルプランニング」を用いて「スポーツの庭」をコンセプトとした札幌ドームの設計・施工に携わった事例をご紹介いただきました。これにより、札幌ドームでは長期的なモニタリングの結果、生物確認種数が増加傾向にあり経年的に環境が良くなっていることをご説明いただきました。また、皇居近くのオフィス街の中心地に位置する「大手町の森」の整備事例では、生態系ネットワークの形成に貢献するだけでなく、シミュレーションの結果、敷地内の平均気温を1.7℃低下することができ、地域のクールスポットとなったとのご説明をいただきました。
(5) 住友林業緑化株式会社 「生物多様性を切り口にした緑化事業」
伊藤 俊哉 氏
(住友林業緑化株式会社 環境緑化事業部 生物多様性推進室 室長)

住友林業緑化は、木という豊かな生物多様性の恵みを得て事業を行っており、生物多様性が豊かでないと、事業の基盤を失ってしまうため、健全な生物多様性を維持する責務があるとの考えをお話しいただきました。
自然との共生を実践するための取組として、愛知県豊田市のトヨタの森で実施した「トヨタの森里山再生プロジェクト」による企業緑地における里山再生、愛知県知多市の知多半島グリーンベルトで実施した「知多グリーンベルト再生計画」による生産工場外周緑地における生態系ネットワークづくり、東京都千代田区の駿河台地区再開発で実施した「三井住友海上駿河台地区再開発計画」による生物多様性に配慮した都市再開発、そして北海道のクッチャロ湖で実施した「大同の森クッチャロ湖畔自然林再生プロジェクト」の事例をご紹介いただきました。
(6) 札幌市環境局 「事業者の皆様へ向けた生物多様性保全に関わる札幌市の取組」
米森 宏子 氏
(札幌市環境局 環境都市推進部 環境共生推進担当課長)

札幌市では生物多様性保全の基本指針として2013年3月に生物多様性さっぽろビジョンを策定しており、このビジョンの趣旨や体系についてご説明いただきました。また、札幌市役所では省エネルギー、省資源といった環境マネジメントシステム(EMS)を実践しており、これらの取組はいずれも生物多様性保全につながるということをお話しいただきました。
そのほかにも生物多様性保全への理解浸透に向けた活動連携である「生物多様性さっぽろ活動拠点ネットワーク」や、企業に向けた取組であるさっぽろ環境賞における生物多様性保全部門の新設、環境に配慮した取組を行っている事業所を「さっぽろエコメンバー」として登録する制度といった様々な取組をご紹介いただきました。
5.交流会
交流会では、事例紹介で登壇された事業者を含む9のブースが出展され、それぞれの取組を紹介しました。各ブースでは、取組に対しての質問や意見など、参加者との情報交流が活発に行われました。


交流会の様子
6.パネルディスカッション


パネルディスカッションでは、コーディネーターに北海道大学大学院農学研究院教授の中村太士先生をお迎えし、前半の講演・事例紹介の内容の振り返りを交えながら、パネリストの皆様と、いかにして生物多様性の主流化を進めるべきか議論を行いました。
まず、取組によって得られた(又は想定していた)メリット等について議論しました。例えば、「環境にやさしい」というイメージを持ってもらうことによるブランド力向上を期待していた、事業によって何らかの環境の改変が生じることから生物多様性の保全の取組は企業としての責務と捉えていたといった意見がありました。
続いて、中小企業の取組に関する議論が行われました。中小企業が取り組むにあたってのポイントとして、衣食住といった自らの生活や身近な事業から考えること、ISO14001のような環境マネジメントシステムに生物多様性を組み込むこと、事業所と地域住民との関係は重要であることから事業所周りの緑化から始めること等が指摘されました。緑化については、モニタリングとあわせて環境教育も行えることから、中小企業にとっても持続可能な取組であるとの指摘もありました。さらに、「生物多様性」という言葉を難しく考えず、これまで多く取り組まれている省エネ活動等も生物多様性につながっていることを理解することが必要ではないかとの意見が示されました。
また、企業とNPOとの連携の好事例として、CSRとして取り組んでいる田んぼ再生や森林保全の活動において、生産した米を販売、間伐材を住宅建材として活用し、地域課題の解決に結びつけた事例が示され、継続的な取組には「出口」をつくることが必要との指摘がありました。
これらの議論を踏まえ、パネルディスカッションの最後に、「生物多様性を企業としてどう考えていけばいいか」について議論しました。企業活動は生態系に何らかのインパクトがあることから、可能な限り減らしていくことが重要であるとの発言がありました。最近は認証商品を扱うメーカーが増えており、普通のことになりつつあることを認識すべきとの発言がありました。地球温暖化対策等として取り組んできたことについて、生物多様性保全に改めて位置づけ直すことも効果的ではないかとの発言がありました。サプライヤーに対する環境教育等、中小企業への働きかけも重要ではないかとの発言がありました。企業は褒められることで積極的に取り組むため、表彰等による動機付けも効果的との発言がありました。最後にコーディネーターが、生物多様性への民間参画に関する議論は、生物多様性という言葉のみに囚われるのではなく、最終的に地域を元気にするということを見据えて取り組む必要があり、生物多様性からの恵み(生態系サービス)と地域・社会・経済をどう結びつけて取り組むかを考える必要がある、とまとめました。