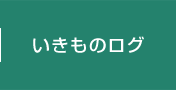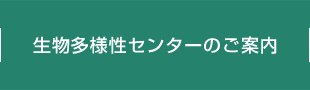参考情報
本サイトの内容をより理解していただくために、「藻場調査(2018~2020年度)」に関連する基礎的な用語や専門用語の解説を以下にまとめています。サイトの利用にあたって参考にしてください。
| 用語 | 解説 |
| 磯焼け | 底質の岩石や岩盤から海藻類が消滅した現象をいいます。北海道の例では、海底を白ペンキのような石灰藻(紅藻サンゴモ科の暖水系の藻類)が覆ってしまい、海藻類が生育できない状態で、白い海底とウニのみが見られる景観となっています。このような石灰藻による生育基盤の消失のほか、ウニ類(キタムラサキウニ、ガンガゼ等)、魚類(アイゴ等)など植食性の動物による藻類の食害、水の濁りや海水温の上昇、さらにはこれらの複合など、場所により磯焼けの要因もさまざまです。 |
| 海区 | 藻場調査(2018~2020年度)では、全国を8つの海区に区分しています。海区区分は、これまで考案されてきた以下に示す区分も参考にして検討会で設定しました。 ① 海藻の分布に着目した区分(谷口(1961)、新崎(1984)) ② モニタリングサイト1000(藻場調査)における区分 ③ 第7回自然環境保全基礎調査浅海域生態系調査(藻場調査)ブロック区分 ④ 世界の海洋生態域(Spalding MD et al.(2017)) |
| 海中林 (かいちゅうりん) | コンブ類、ホンダワラ類など大型の藻類がまとまって生育している場所のことで、陸上の森林に対比して「海の森」を海中林と呼びます。海中林を形成する海藻は、北海道ではコンブ類とアマモ、東北太平洋ではアマモ、コンブ、ホンダワラ、東北日本海側ではホンダワラ、中部太平洋ではアラメ、四国九州ではアラメ、ホンダワラなど地域で異なります。海中林は魚類の産卵場、稚魚の成育場、多様な生物の生息場としての機能のほか、海水の浄化などにも役立っています。 |
| 解像度 | 画像データを構成する画素の単位です。藻場調査(2018~2020年度)では、複雑な地形に囲まれた水域を解析するために解像度50cmで一般に高解像度といわれる画素の細かいものを用いました。他に中解像度、低解像度といわれるより粗い画像データがあります。古くから用いられてきたLANDSAT は中解像度、お天気衛星としても知られるMODIS、Terra Aquaは低解像度にあたる衛星データです。 |
| 環境影響評価 | 一般に環境アセスメントとも言われます。事業による環境への影響を調査、予測、評価し、影響を回避、低減、最小化させるための措置につなげる手続きで、法的根拠としては、環境影響評価法、および自治体の条例などがあります。 |
| 基質 (きしつ) | 藻場を構成する藻類が付着する基盤となるものを指します。岩礁、礫、砂泥のほか、他の海藻や貝などの他の動物、ブロック等人工物なども基質となります。藻場調査(2018~2020年度)では、海藻藻場、スガモ場を構成する藻類はおもに岩礁や礫、アマモ場を構成する海草(うみくさ)類は砂泥を基質としています。基質に付着する部分は、陸上植物では「根」にあたるものを、海藻の場合は付着根とよびます。 |
| 教師なし分類 | 衛星画像解析の手法の一つで、分類クラスをあらかじめ特定せずに、画素をグループ化する手法の総称で、最終的に分類結果と実際の解析対象を対応づけて分類図を作成します。藻場調査(2018~2020年度)での解析法は、教師なし分類のうちISODATA法とよばれる手法で、解析作業の分類項目(結果)は「藻場」と「非藻場」になります。画像分類には教師なし分類のほか、教師データ(トレーニングデータ)をとり、対象の統計的な特徴によって分類する教師つき分類があります。藻場調査(2018~2020年度)では、全国の沿岸を対象として、撮影日等の異なる多数の画像を用いる必要があるため、撮影条件の差が分類結果に影響しないよう教師なし分類を採用しています。 |
| シェープファイル | 図形情報と属性情報をもった地図データファイルの集まったデータ形式(フォーマット)です。シェープファイルはこのGISデータフォーマットの一つで、対象物の位置や形状、属性情報をもつベクターデータ(ポイント、ライン、ポリゴン)を格納することができます。それにより、地球上のどの場所に、どのような形でデータが存在し、その属性は何かを示すことができます。 |
| 潮位 | 海面の高さのことを指し、東京湾平均海面(TP:Tokyo Peil)を基準としています。潮位を計るために各地に検潮所があり、最寄りの検潮所の値で補正して統一した値とします。藻場調査(2018~2020年度)での整理においても補正した値を用いました。藻場の生育と関連して、潮位に関しては、高潮線(大潮時に海面が最も高くなる位置)、低潮線(大潮時に海面が最も低くなる位置)、潮下帯(ちょうかたい:低潮線より下の部分)、潮上帯(ちょうじょうたい:高潮線より上の部分で飛沫帯ともいう)などの用語が使われます。 |
| ブルーカーボン | 2009年10月に国連環境計画(UNEP)の報告書において、藻場・浅場等の海洋生態系に取り込まれた(captured)炭素が「ブルーカーボン」と命名され、吸収源対策の新しい選択肢として提示されました。ブルーカーボンを隔離・貯留する海洋生態系として、海草藻場、海藻藻場、湿地・干潟、マングローブ林が挙げられ、これらは「ブルーカーボン生態系」と呼ばれます(国土交通省ウェブサイト)。 |
| ポリゴン | 一般には多角形を指し、GISデータでは図形の面のことを指します。藻場分布素図、藻場分布図の成果はポリゴンになります。藻場調査(2018~2020年度)で作成した藻場分布図のポリゴンには、凡例やデータ作成のもとになる衛星画像の諸元(衛星種類、撮影月日等)等を属性として付与されています。 |
| 洋上風力発電 | 陸上風力発電と対比してオフショア風力発電(Offshore wind power)とも言われます。洋上では陸上よりも大きな風力エネルギーを得ることが期待でき、かつ私権も陸上ほど強くないことからとくにイギリス、オランダ、デンマークなど欧州で2000年以降急速に導入が進んでいます。施設の形式として、一般に水深50m程度までは着床式、それ以深は浮体式とよばれる発電施設が計画されます。この施設の設置による環境影響として、おもに鳥類の渡りへの影響、回遊性の水生生物への影響があげられています。藻場については、発電施設そのものや工事中の濁り、電力線の設置、陸揚げなどが影響要因として考えられます。わが国でも洋上風力発電普及法が施行され、各地で計画が進んでいます。 |
| リモートセンシング | 対象物に接触することなしに離れた(remote)場所から観測する(sensing)ことを意味します。藻場調査(2018~2020年度)では、衛星画像に記録された光(電磁波)の情報が格納された衛星画像を用いて解析しています。衛星画像では電磁波の情報として、近赤外(波長0.7μm~1.3μm)、可視光(0.4μm~0.7μm)のバンドが記録されていますが、近赤外は水中に届かないため、藻場調査(2018~2020年度)では、青、緑、赤の可視光の情報を使って解析しています。GISで用いるデータには、境界の明確な地物、事物で、線(ライン)、点(ポイント)、面(ポリゴン)から構成されるベクターデータと、植生界のように境界が曖昧なラスターデータがあります。藻場調査(2018~2020年度)で作成した藻場分布図はベクターデータ(ポリゴンデータ)で作成しています。 |
| GIS (ジー・アイ・エス) | GISとは地理情報システム(Geographic Information System)の略で、「地上の存在する事物、地上で発生する現象を「地図化し、解析する」ためのツールを表わします(ESRI社)。GISで用いるデータには、境界の明確な地物、事物で、線(ライン)、点(ポイント)、面(ポリゴン)から構成されるベクターデータと、植生界のように境界が曖昧なラスターデータがあります。藻場調査(2018~2020年度)で作成した藻場分布図はベクターデータ(ポリゴンデータ)で作成しています。 |
| Kml (ケー・エム・エル) | kml(Keyhole Markup Language)とは、Google Earth によって広められたXMLファイルの一つです。XMLはファイルにデータを書き込むときの記述形式の一つで、ソフトウェア間でデータを交換する時に用います。kmlにより、位置をもった情報をGoogle Earth だけでなく各種のGISソフトやGoogle Maps、モデリングソフトで展開できるようになります。このkmlファイルをzipで圧縮したものがkmzファイルです。 |
| M7000シリーズ | 藻場分布図の背景情報として使用している、日本水路協会が提供する海域の水深、等水深線データです。M7000シリーズでは、海域により格納されている等深線間隔は異なりますが、世界測地系に準拠したデータ(シェープファイル)が入手できます。 |
参考文献
ESRIジャパンHP, GIS基礎解説 日本で使用される座標系
猪木幹雄・中田勝行・那須充, 図説わかる測量, 株式会社学芸出版社, 2014
井上吉雄編, リモートセンシングGIS・GPS活用ガイド, 森北出版株式会社 2019
神谷充伸監修, ネイチャーウォッチングガイドブック海藻, 株式会社誠文堂, 2017
環境省, 第7回自然環境保全基礎調査 第5章 日本の藻場の現状, 2008
国土交通省HP, ブルーカーボンとは, 2021年8月25日確認
越原康之, 海を育て漁場の宝庫に(海の草原づくり), 和歌山県, 2009
三重県農林水産部水産基盤整備課, 「藻場造成ガイドブック」改訂版, 2013
宮脇昭(代表), 日本の植生 7海ソウ, 学研, 1977
中島広樹、田中敏博、吉満敏、寺田竜太, 鹿児島県笠沙におけるホンダワラ属藻類3 種の季節変化と藻場垂直分布の長期変化, 藻類, 61(2)2013
仲岡雅裕, アマモ場の生物多様性と機能, 日本生態学会(編)エコロジー講座3 なぜ地球の生きものを守るのか(所収), 文一総合出版, 2010
日本藻類学会 編, 海藻の疑問50, 成山堂書店, 2017
ルイ ソチェ・作野裕司, 衛星Terra/ASTERデータを使った吉名干潟における藻場モニタリング, 水工学論文集,第52巻 2008
島袋寛盛 編, (特集)気候変動が藻場生態系に与える影響, 海洋生物236号, 生物研究社, 2018
白山義久、桜井泰憲、古谷研、中原裕幸、松田裕之、加々美康彦, 海洋保全生態学, 株式会社講談社, 2012
水産庁HP, 藻場の働きと現状~藻場の分類, 2020年6月30日確認
田中次郎、中村庸夫, 基本284 日本の海藻, 平凡社, 2004
谷口和也, 磯焼けを海中林へ~岩礁生態系の世界~, 裳華房, 1998
東京大学海洋研究所編, 入門ビジュアルサイエンス海洋のしくみ, 日本実業出版社, 1999
宇野木早苗、久保田雅久, 海洋の波と流れの科学, 東海大学出版会, 2018
山口靖・八木令子・小田島高之編, はじめてのリモートセンシング~地球観測衛星ASTERで見る~, ジオテクノス株式会社, 2004
山本智之, 温暖化と日本の海, グリーンパワー2012.2, 公益財団法人森林文化協会, 2012