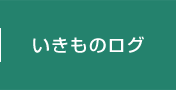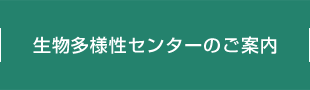| 要約 |
世界自然遺産地域である屋久島は、亜熱帯から冷温帯までの環境に多様な生態系を有し、多くの固有種や北限・南限種が生育・生息する。しかし、近年、屋久島特有の生態系への影響が懸念される事例が報告されている。それらの中から本研究ではヤクシカ(Cervus nippon yakushimae)および島外から持ち込まれた外来種であるタヌキ(Nyctereutes procyonoides)の生息状況、森林生態系への影響を調査、検討することを目的とした。
1.ヤクシカの生息密度と森林生態系に与える影響に関する調査
「群落構造への影響調査」と「絶滅危惧種への影響調査」を実施した。
群落構造への影響調査では、ヤクシカの生息密度が異なる場所において、植生とシカの糞粒密度を調査し、その関係を検討した。その結果、シカの糞粒密度が増えると植生の被度、種数が減少する傾向が見られた。このような植生の変化と環境要因(光、土壌水分、地質、土壌、周辺植生)との間に明らかな関係は見られず、一方で植生の被度、種数の減少とともに食痕が増加する傾向が見られた。このため、植生の変化はシカによる影響が大きいと考えられた。シカの糞粒密度が低い地点では、嗜好性が高い種に食痕が見られるが、植生の被度は保たれている。糞粒が低密度から高密度へと上昇する地点では、嗜好性が中程度の種へも食痕が増加し植生の被度が減少する。糞粒密度が高い地点では、嗜好種は減少して不嗜好種が残り植生の被度は低下する。これは、シカの採食圧が高くなるにつれて餌となる植物が減少するため、シカがその食性を変化させている結果と考えられる。このような現象はシカの生息密度が増加した各地域から報告されている。
絶滅危惧種への影響調査では、防鹿柵を4ケ設置し、その柵内外で絶滅危惧種とされるシダ植物の個体と林床植生を1年間モニタリングした。その結果、ヤクシカの採食が絶滅危惧種のシダ植物の定着と成長を妨げ、林床植生についてもその被度と種数の増加を妨げていると考えられた。
以上の結果から、早急に調査や対策が必要と考えられる課題として、�希少種や絶滅危惧種等を中心とした植生保全の対策、�シカの影響による土壌流出についての調査、必要に応じた対策の検討、�シカ個体群管理のためのデータ収集、合意形成・体制構築、調査・研究と対策事業の同時進行、が挙げられる。さらに、屋久島は世界遺産に登録されており、その価値を保全するための管理を行う必要がある。他地域の事例から、長期にわたってシカの高密度が続くと、植生の構造や組成の変化、多様性の消失へつながる可能性も考えられる。今後、関係機関、住民が話し合いの場を持ち、連携をとりながら、ヤクシカの保護管理を含め、島全体の具体的な管理目標、行動計画等を検討し、順応的管理を進めることが望まれる。
2.タヌキの生息状況と森林生態系に与える影響に関する調査
本研究では、屋久島におけるタヌキの分布調査と外来生物駆除の観点から捕獲技術を検討するための試験捕獲、およびDNAや胃内容分析などの捕獲個体分析を実施した。
本研究により、屋久島に生息しているタヌキは、国内外来生物で、同一母系集団から拡大してきた可能性が高いこと、また、既に標高200m以下の低地では島全周に分布し、標高800m地点でも確認されたことから、山岳地域にも分布している可能性が高いことが確認された。捕獲技術を検討するための試験捕獲では、屋久島においてタヌキを効率的に捕獲するためには、他種の混獲を可能な限り抑えるなどの対応が必要と考えられた。また、捕獲個体の胃内容物分析から、タヌキの捕食は広い範囲の動物種に及び、特に昆虫類の出現率が高いことが確認された。
屋久島におけるタヌキの侵入は競合による在来種の排除、捕食による在来種の減少を引き起こすことが考えられ、その結果、在来生物の相互関係が崩れ、屋久島のような閉鎖された島嶼では生態系全体に影響を及ぼす可能性がある。早急な施策が求められる段階にあると考えられる。 |