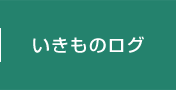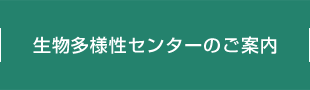| 要約 |
海辺調査は、浅海域の抽出とその概要把握を行うと共に、全国の海辺の利用・法指定等状況及び海岸線の改変状況を調査し、また、併せて海岸域における生物の生息状況及び生息環境を調査することを目的とする。
調査の内容と方法は下記のとおり。
<浅海域分布調査>
浅海域の分布状況等を把握する為、最新の海底地形・底質及び人工構築物等に関する資料を収集し、水深10m迄の等深線、底質、 変化した海岸線等についての情報を把握して浅海域分布図を作成する。
<海辺環境調査>
既存資料等から浅海域環境(地形条件及び生物相)、海辺利用・法指定等状況及び海岸改変状況について把握する。
<海辺生物調査>
年2回、大潮の干潮時に方形枠を用いて潮上帯及び潮間帯の生物のトランセクト調査を実施する。
調査結果は下記のとおり。
<浅海域分布調査>
第5回基礎調査の結果では、干潟は、49,380.3ha確認され、うち有明海が約4割を占めていた。また、第4回調査時以降、1,870haの干潟が消滅したことが判明した。最も多く干潟が消滅したのも有明海で、その面積は322.3haに達していた。
次に、藻場は、全国で142,459ha(10m以浅を対象)把握された。
また、サンゴ礁地形は、鹿児島県のトカラ列島以南に多く存在した。なお、八重山列島には国内最大の面積のサンゴ礁が存在しているが、同海域の造礁サンゴ類の種の多様性は世界でも屈指のものである。
<海辺環境調査>
第5回基礎調査の結果では、海岸線の総延長は、第4回基礎調査海岸調査結果に比べ約800km増加した事が明らかとなった。
また、海岸(汀線)の区分別延長を同じく第4回基礎調査結果と比較すると、自然海岸の延長が約700kmの減であり、一方人工海岸の延長は約880kmの増となっていた。
<海辺生物調査>
潮上帯及び潮間帯に出現した生物種のリストが作成された。
本書はその調査要綱。 |