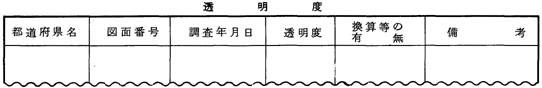
〔16〕 自然環境保全調査実施要領
昭和48年6月
環境庁自然保護局
(大綱)
自然環境保全調査大綱
第1 目 的
自然環境保全法第5条に規定する基礎調査を48年度全国一斉に実施し、わが国における自然環境の現況を把握するとともに、その解析を行ない全国的な自然環境の保全の施策を推進するための基礎資料とする。このため、植生、野生動物、地形地質、海中自然環境等の現況を把握するとともに、その解析により自然度の判定を行ない、また自然が人間の生活のための環境保全に対し、どの程度の寄与をしているかを検討する。さらに自然のもつ貴重な価値に着目し、国土におけるすぐれた自然の確認を行なう。
第2 調査内容
調査内容は次のとおりとする。
1.基礎調査
(1)自然度調査
自然度判定のための基礎資料として自然環境の現況を調査する。
ア 植生自然度 陸域の自然度、特に人間による物理的破壊状況を知るために、群落の種組成により判断する。今までに一般に認められた群集から判断して、約200凡例の区分を行い、現存植生図を作成する。
イ 陸水域自然度 湖沼、河川の生物分布、水質、利用状況等を調査する。
ウ 海域自然度 海域(海岸を含む)の生物分布、水質、利用状況等を調査する。
(2)すぐれた自然の調査
特異性、稀少性、原産性、歴史性等の観点よりすぐれた自然の確認を行なう。
ア 植物 貴重な植物の個体・群落の生育地、各種の群落がまとまっている地域、典型的な垂直分布等を調査する。
イ 野生動物 貴重な野生動物の生息地、繁殖地、渡来地等を調査する。
ウ 地形、地質、自然現象、地形若しくは地質が特異であり、または特異な自然の現象が生じている地域を調査する。
エ 海中自然環境 サンゴ、魚類、海草類等、海中の生態系がすぐれた状態を維持している海域を調査する。
オ 歴史的自然環境 遺跡、歴史的建造物等の歴史的文化財や過去の生活、生産様式と密接に結びついた歴史的風土としての自然環境を調査する。
(3)総合解析調査
上記の基礎資料を整理集計し、自然度等を判定するとともに、電算機による解析を行なう。
2.改変状況調査
都市、公害防止計画策定地域その他人間の活動により自然環境の改変が進みつつある特定の地域を選定し、改変状況を調査するとともに、残された自然が人間の生活環境保全に対してどの程度の寄与をしているか検討する。
ア 植生現存量 群落区分ごとの植生現存量を航空写真、植生図等より測定する。
イ 植生生産量 群落区分ごとの単位生産量を定め、植生現存量より改変地域の植生生産量を推定する。
ウ 鳥類生息分布 改変地域における鳥類の生息分布を調査し、植生現存量・生産量との関連を検討する。
エ その他改変状況資料 土地利用、人口密度、環境汚染等の人間活動による改変の資料を収集整理し、植生生産量との関連を検討する。
第3 調査方法
1.環境庁は調査の企画、立案、取りまとめを行なう。
中央に学識経験者よりなる自然環境保全調査委員会を設け、調査項目、調査方法、集計解析方法などの審議を行なう。
2.調査は国の委託により都道府県が主体となって実施し、市町村、地方の学識経験者及び民間のコンサルタントの協力参加を求める。
都道府県における作業機関は原則として下記の中から選定するものとする。
ア 都道府県の関係部課等および試験研究・調査機関
イ 関係大学および研究機関、国の試験研究・調査機関
3.都道府県の作成した資料の集計整理および解析については民間コンサルタントに委託する。
|
(基礎調査) 1.自然度調査 ア 植生自然度 |
1.調査事項及び調査対象区域
調査対象区域は、当該都道府県全域とし、植物社会学的現存植生図を作成する。
2.植生図凡例
植生図の凡例には、原則として群集及び群集レベルの群落を用いる。
凡例は、別添1の植物社会学的現存植生図凡例を参照のこと。
|
a 寒帯・高山帯自然植生 b 亜寒帯・亜高山帯自然植生 c 亜寒帯・亜高山帯代償植生 d ミズナラ-ブナクラス域自然植生 e ミズナラ-ブナクラス域代償植生 f ヤブツバキクラス域自然植生 g ヤブツバキクラス域代償植生 h 河辺・湿地・塩沼地・砂地(各クラス共通) i 植林地・耕作地(各クラス共通) j その他(各クラス共通) |
3凡例以上 12 〃 4 〃 37 〃 23 〃 48 〃 23 〃 28 〃 33 〃 7 〃 |
3.調査の方法
ア フィールド調査・航空写真解読により、植生図を作成する。
なお、既に作成された既存資料がある場合は、それを活用する。
イ 都道府県においては、5万分の1の地形図にて植生調査を取りまとめることとする。最終的に20万分の1地勢図に整理する。
ウ 付属資料として、当該都道府県の植生概説をおこなうと共に、代表的群落(主として、凡例として利用した群落)については、1ケ所以上の植生調査表を添付し、概説する。
エ 5万分の1の地図上に記載する群落の最小面積は、記載可能な大きさと(2×2mmを一応の目安とする。但し、2mm以下であっても、10mm以上の長さを有するものは、可能な限り記載する。
オ 植生調査票は特に定めないが、調査事項等についてはJCT(P)で作成したものを参考とすること。
なお、調査に際しては、調査区内の全出現種を省略せず、記載すること。
カ 植生調査者、解説者、植生図作成者の氏名、所属を明記する。
キ 提出書類は図面・付属資料各1部とする。
|
イ-(ア)陸水域湖沼自然度 |
1.調査事項
湖沼における自然度を知るために次の事項について調査する。
(1)湖沼概要
(2)受水区域概要
(3)湖岸線の利用・改変状況
(4)水質等の理化学的性状
(5)生物分布
2.調査対象湖沼
環境庁の定める湖沼。その他既存資料の整備された湖沼があれば、各都道府県において資料整理のこと。
3.調査の方法
ア 調査項目
様式1に示した各項目
イ 資料収集
関係機関に出向き、最新の調査資料を収集する。調査は既存資料の収集を主とし、既存の知識、研究報告等の資料を基礎にして行なうものとするが、必要に応じて現地調査を行ない、さらに各種地形図、航空写真の判読等により補完するものとする。
ウ 調書の作成
“イ”により収集した資料から様式1により各湖沼ごとに調書を作成する。
エ 図示
縮尺5万分の1地形図(広大な湖沼については縮尺20万分の1地勢図)に受水区域及び観測年月を記入する。
オ 参考資料の提出
様式2に示した各項目について既存の資料がある場合には、収集、整理の上、調書を提出する。
|
イ-(イ)陸水域河川自然度 |
1.調査事項
河川における自然度を知るため次の事項について調査する。
(1)河川概要
(2)水質等の理化学的性状
(3)生物分布
2.調査対象河川
環境庁の定める河川。調査対象河川の選定に当っては環境庁と協議の上決定すること。
その他既存資料の整備された河川があれば各都道府県において資料整理のこと。
3.調査の方法
ア 調査項目
様式3に示した各項目
イ 資料収集
関係機関に出向き、最新の調査資料を収集する。調査は既存資料の収集を主とし、既存の知識、研究報告等の資料を基礎として行なうものとするが、必要に応じて現地調査を行ない、さらに各種地形図、航空写真の判読等により補完するものとする。
ウ 調書の作成
“イ”により収集した資料から様式3により各河川ごとに調書を作成する。
エ 図示
縮尺20万分の1地勢図に観測地点、観測年月を記入する。
オ 参考資料の提出
様式4に示した各項目について既存の資料がある場合には、収集整理の上調書を提出する。
|
ウ 海域自然度 |
1.調査事項
海域における自然度を知るために次の事項について調査する。
(1)水質(透明度及びCOD)
(2)海岸線の利用・改変状況
(3)生物分布(貝類・海草類などの地区別分布及び漁獲量)
2.調査対象区域
各都道府県の沿岸地先海域全域
3.調査の方法
(1)水質
ア 調査項目
透明度及びCOD
イ 資料収集
関係機関に出向き、昭和47年度(47年度のものがなければ最新の資料)に実施された水質関係の調査資料を収集する。調査は既存資料の収集を主とし、既存の知識、研究報告等の資料を基礎にして行なうものとするが、必要に応じて現地調査を行なう。
ウ 調書の作成
“イ”により収集した資料から透明度及びCODに関する項目を選び出し、分析方法別に整理し、透明度及びアルカリ法によるCODの値に換算し、月別に分けて図示しうるようにする。透明度は様式5により、CODは様式6により調書を作成する。
エ 図示
“ウ”により整理した資料にもとづき、透明度及びCOD別に各月ごとに縮尺5万分の1地形図に記入し、等値線を引く。
様式-5
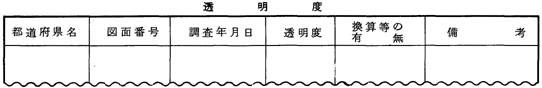 |
様式-6
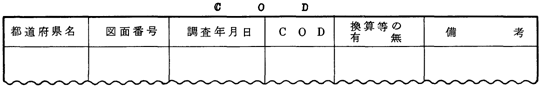 |
(2)海岸線の利用・改変状況
ア 調査項目
次の項目について海岸線を分類し、延長を測定し、図示する。
(ア)海岸汀線及びそれに接する海域の状況
ⅰ 純自然海岸
海岸汀線及びそれに接する海域が人工によって改変されていないで、自然の状態を保持している海岸
ⅱ 半自然海岸
道路や護岸等で海岸汀線に人工が加えられているが、なお汀線に接する海域が自然の状態を保持している海岸
ⅲ 人工海岸
海湾、埋立、浚渫、テトラポット等の土木工事により海岸汀線及びそれに接する海域が著しく人工的に改変された海岸
(イ)海岸陸域の土地利用状況
ⅰ 自然地
樹林地、砂浜、断崖等の自然が人工によって著しく改変されていないで自然の状態を保持している土地
ⅱ 農業地
畑、牧野、水田等の農業的な利用が行なわれている土地
ⅲ 市街地、工業地
市街地、集落地、工業地等の人工的な利用が行なわれている土地
イ 資料収集
各種地形図及び航空写真の判読、ならびに関係機関、関係市町村の聞き取調査等により資料を収集する。
ウ 図示
“イ”により収集した資料から各調査項目を様式7により、縮尺5万分の1地形図に記入する。記入する海岸線の延長はおおむね100m単位とする。
エ 調書の作成
各都道府県ごとに調査項目別の海岸線延長を集計し、海岸汀線及びそれに接する海域の状況については様式8により、海岸陸域の土地利用状況については様式9により調書を作成する。
様式-7
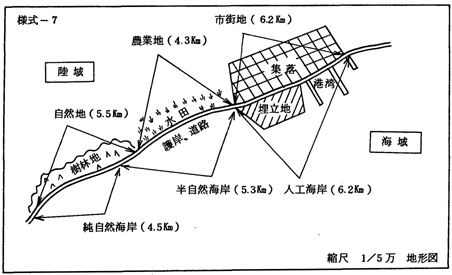 |
様式-8
|
海岸汀線、海域状況 (都道府県名) |
|
|
純自然海岸 |
半自然海岸 |
人工海岸 |
海岸線総延長 |
|
延長 |
・ km |
・ km |
・ km |
・ km |
|
比率 |
( %) |
( %) |
( %) |
( 100%) |
(備考)延長は小数点以下1位まで(100m単位)記入のこと。
様式-9
|
海岸陸域土地利用状況 (都道府県名) |
|
|
自然地 |
農業地 |
市街地・工業地 |
海岸線総延長 |
|
延長 |
・ km |
・ km |
・ km |
・ km |
|
比率 |
( %) |
( %) |
( %) |
( 100%) |
(備考)延長は小数点以下1位まで(100m単位)記入のこと。
(3)生物分布
ア 調査項目
貝類、海草類などの地区別分布及び漁獲量
イ 資料収集
(ア)主として各地域の漁業協同組合に出向き、昭和47年度(47年度のものがなければ最新の資料)の貝類、海草類などの種類別漁獲統計資料を収集する。貝類、海草類などの種類については様式10を参照のこと。ただし垂下式などの養殖している種類は除く。
(イ)関係機関に出向き、藻場の分布状況を調べる。
ウ 調書の作成
(ア)“イ-(ア)”により収集した資料から様式10により調書を作成する。漁獲量のわかっているものについては、これを集計し漁獲率(%)を算出する。漁獲量の明らかでないものについては、漁獲量にかえて、多い(L)、普通(M)、少ない(S)の記号で示す。
(イ)調書は各漁業協同組合ごと(漁業協同組合が細分化され、その数が多い場合は海区-水域の特性によって分けられた区域-の漁協)の資料をまとめたもの、及び都道府全体を集計したものを作成する。
エ 図示
縮尺5万分の1地形図に調書を作成した各漁業協同組合(海区でまとめた場合は、まとめたいくつかの漁協)の地先範囲及び“イ-(イ)”により収集した藻場の分布図を記入する。
なお、藻場については、できれば藻の種類及びその面積を図面に付記する。
オ 参考資料の提出
ベントス(底生生物)について既存の研究報告がある場合には、その資料を提出する。
|
〔2〕すぐれた自然の調査 ア 植物 |
1.調査対象区域及び調査事項
ア 調査対象地区は当該都道府県全域とし、貴重な植物の個体・群落の生育地、各種の群落がまとまっている地域、典型的な垂直分布等を調査する。
イ 調査は、(ⅰ)貴重な個体植物調査、(ⅱ)貴重な群落調査に分けて行なう。
2.調査事項
調査の方法は、既存の知識、研究報告等の資料を基礎にして行なうものとするが、基礎調査で行なう植物社会学的現存植生図作成と、適宜平行して行なう。
3.貴重な個体植物調査
(ⅰ)調査基準
貴重な個体植物調査については(ア)~(エ)のうち1以上に係るものを記述対象とする。
(ア)日本特産であること、または、地方特産であること。
(イ)稀産種であること。
(ウ)世界又は日本における南限又は北限であること。
(エ)その他、重要な種等であること。
(ⅱ)調査方法
貴重な個体植物調査については、別添2の貴重植物生育地調査表を主体として調査をすすめるものとするが、現地調査者の判断に基づき適宜追加する。
(ⅲ)記載方法
記載の方法は以下によるものとする。
(ア)5万分の1地形図を使用し、各種毎にその自生地を黒点で示し、貴重植物生育地調査表にあげた種の番号を付すこと。
(イ)同一の場所に、2種以上の種が生じ判別が困難な場合には別々の地形図に示すこと。
(ウ)絶滅したことが判明する場合には、その種が生えていた地点を図示し、絶滅した年月を付記すること。5万分の1地形図上に絶滅地を赤点で示し、種の番号を付すこと。
(エ)いずれの場合も、各種の自生地の海抜高を付記すること。
(オ)調査者が追加しようとする種は、貴重植物生育地調査表に挙げられた種の追加番号とすること。
4.貴重な群落調査
(ⅰ)調査基準
貴重な群落調査については、特に下記のものに重点を置き調査する。
(ア)各種の群落がまとまっている地域、典型的な垂直分布をなし、貴重と認められるもの。
(イ)群落が特に自然性の高いもの、当該地域では特に稀少性の高いもの。
(ウ)その他、重要な群落と認められるもの。
(ⅱ)記載方法
記載の方法は、以下によるものとする。
(ア)図面
5万分の1地形図を使用し、対象群落を黒線で囲む。この場合、各地形図ごとの対象区域に番号を付す。
(イ)説明書
様式11により説明書を作成する。この場合内容欄には、(a)典型的群落、(b)稀出現群落、(c)各種の群落のまとまっている地域、(d)垂直分布、(e)立地的特殊群落、(f)その他について記載する。
なお、説明に当っては、適宜、植生調査表を添付する。
(ウ)評価
説明書中、評価欄には、調査委員による各対象地域の評価を次によりA、B、Cで記入する。
A~全国レベル保護対象、B~地方レベル、C~都道府県レベル
様式-11
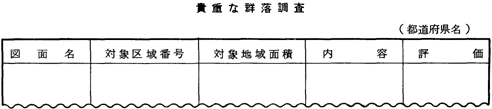 |
|
イ 野生動物 |
1.調査対象区域及び調査事項
ア 調査対象区域は当該都道府県全域とし、生息地(繁殖地を含む)、渡来地(鳥類)について調査する。
イ 調査対象動物は、獣類、鳥類、爬虫類、両■類、魚類(淡水産)、昆虫類とし、調査基準により選択記述するものとする。
2.調査基準
ウ 調査基準は以下によるものとし、(ア)~(エ)のうち、1以上に係るものを記述対象とする。ただし、対象種は別表2を基準として選定するものとする。
(ア)日本特産であること。
(イ)稀産種であること。
(ウ)世界又は日本における南限又は北限の種であること。
(エ)その他、重要な個体群等であること。
3.調査の方法
エ 調査の方法は、既存の知識研究報告等の資料を基礎にして行なうものとするが、必要に応じて現地調査を行なうものとする。
4.記載方法
オ 提出書類は、図面、説明書各1部とするが、内容及び記載方法は以下によるものとする。
(ア)図面
5万分の1地形図を使用し、対象動物の生息地、渡来地を黒線で囲むものとする。この場合、各地形図毎に対象区域に番号を付すものとする。
(イ)説明書
様式-12により説明書を作成する。この場合内容欄には、(a)営巣場所の所在地、(b)環境状況(地形、植生等)、(c)生息状況について、記載するものとする。
(ウ)評価
説明書中、評価欄には、調査委員による各対象地域の評価を次によりA、B、Cで記入するものとする。
A~全国レベル保護対象、B~地方レベル、C~都道府県レベル
様式-12
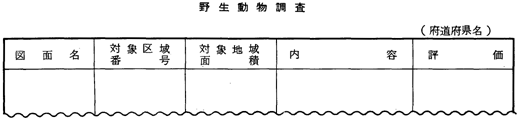 |
|
ウ 地形、地質、自然現象 |
1.調査対象区域及び調査事項
ア 調査対象区域は当該都道府県全域とし、すぐれたまたは特異な地形、地質、自然現象について調査する。
2.調査基準
イ 調査基準は以下によるものとし、調査単位はおおむね別表3によるものとする。
(ア)点又は線的分布をするものについては、模式的又は記念物的意味をもつ岩石、鉱物、化石などの露頭、典型的な地形種類(小地形)、火山現象、水文、気象、海象現象で、限られた分布をするものであること。
(イ)面的分布をするものについては、(ア)のうち大規模なもの、および地形、地質、自然現象などのさまざまな要素の組合せにより、地球科学的意味を持った景観を構成するものであること。
3.調査の方法
ウ 調査の方法は、既存の知識、研究報告等の資料を基礎にして行なうものとするが、必要に応じて現地調査を行なうものとする。
4.記載方法
エ 提出書類は、図面、説明書各1部とするが、内容及び記載方法は以下によるものとする。
(ア)図面
5万分の1地形図を使用し、イ-(ア)については、直径2mmの黒点および、巾1mmの黒線で表現する。イ-(イ)については、分布地域を黒線で囲むものとする。この場合、各地形図毎に、対象の番号を付すものとする。
(イ)説明書
様式-13により説明書を作成する。この場合イ-(ア)及びイ-(イ)のうちイ-(ア)の大規模なものについては、(a)種類、(b)環境状況、イ-(イ)のうち、景観については、(a)要素、(b)環境状況についてそれぞれ記載するものとする。
(ウ)評価
説明書中、評価欄には、調査委員による各対象の評価を次により、A、B、Cで記入するものとする。
A~全国レベル保護対象、B~地方レベル、C~都道府県レベル
様式-13
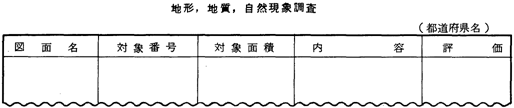 |
|
エ 海中自然環境 |
1.調査対象区域
ア 調査対象区域は当該都道府県地先海域のうち、主として水深20メートル以下の浅海、潮間帯を対象とし、海中動植物の生息地や海中地形からなる海中自然環境について調査する。
2.調査基準
イ 熱帯魚、さんご、海草、その他これらに類する動植物及び海中地形等の自然環境がすぐれた状態を維持している海域であって、次の調査基準に合致するものを選択する。
(ア)海域の水質が汚染されていないこと。
(イ)黒潮、対馬海流、千島海流等の各海流によって形成されるさんご、熱帯魚、海草、特殊生物等からなる代表的な海中の生態系であって、海中地形に変化があり、海中動植物が豊富で、かつその種類が多いこと。
3.調査の方法
ウ 調査の方法は、既存の知識、研究報告等の資料を基礎にして行なうものとするが、必要に応じて現地調査を行なうものとする。
4.記載方法
エ 提出書類は図面説明書各1部とするが、内容及び記載方法は以下によるものとする。
(ア)図面
5万分の1地形図を使用し、“2”の区域を黒線で囲むものとする。この場合、各地形図ごとに当該区域に番号を付すものとする。
(イ)説明書
様式-14により説明書を作成する。この場合、内容欄には(a)海中動物、(b)海中植物、(c)海中地形、(d)透明度、(e)その他、等自然環境の概要について記載するものとする。
(ウ)評価
説明書中、評価欄には、調査委員による当該区域の自然環境について評価を行ない、次によりA、B、Cで記入するものとする。
A~全国レベル保護対象
B~地方レベル 〃
C~都道府県レベル〃
様式-14
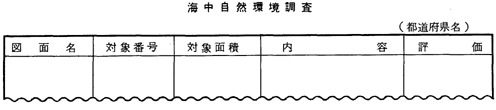 |
|
オ 歴史的自然環境 |
1.調査対象区域
ア 調査対象区域は当該都道府県全域とし、歴史的自然環境について調査する。
2.調査基準
イ 調査基準は以下によるものとする。
(ア)遺跡、歴史的建造物等の歴史的文化財や、過去の生活、生産様式と密接に結びつき、これらと一体をなす歴史的風土としての自然環境を形成しているものであること。たとえば歴史的文化財と一体となった自然林等のすぐれた自然環境
3.調査の方法
ウ 調査の方法は、既存の知識、研究報告等の資料を基礎にして行なうものとするが、必要に応じて現地調査を行なうものとする。
4.記載方法
エ 提出書類は、図面、説明書各1部とするが、内容及び記載方法は以下によるものとする。
(ア)図面
5万分の1地形図を使用し、“2”の区域を黒線で囲むものとする。この場合、各地形図ごとに当該区域に番号を付すものとする。
(イ)説明書
様式-15により説明書を作成する。この場合「文化財の内容」については、(a)名称、(b)指定の種類、(c)その他を記載し、「自然環境」については、(a)地形、(b)植生、(c)動物、(d)その他等、自然環境の概要について記載するものとする。
(ウ)評価
説明書中、評価欄には、調査委員による当該区域の自然環境について評価を行ない、次によりA、B、Cで記入するものとする。
A~全国レベル保護対象
B~地方レベル 〃
C~都道府県レベル〃
様式-15
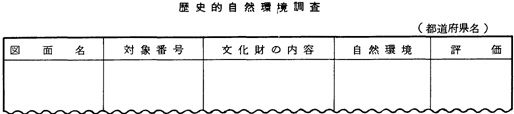 |
(自然環境改変状況調査)
1.調査の目的
自然破壊の進行に対処し、都市、公害防止計画策定地域その他人間の活動により自然環境の改変が進みつつある特定の地域を選定し、植生の現存量、生産量、鳥類生息分布等自然環境の改変状況を調査するとともに、残された自然が人間の生活環境保全に対して、どの程度の寄与をしているか検討する。
2.調査対象地域
東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県に属する関東地方一帯(ただし島嶼部を除く)
3.調査事項
(1)植生現存量調査
(2)植生生産量調査
(3)鳥類生息分布調査
(4)改変状況資料収集
4.植生現存量調査
(1)(調査対象地域における植生区分図の作成)
関東地域について現存植生図及び既存資料を基礎として、現存量算出のための植生区分を行ない、植生区分図を作成するとともに、植生区分別面積を測定する。
(2)(植生現存量モデル調査地帯の抽出)
土地利用、地域環境等が典型的な特色を示す地域をモデル的に選定し、サンプル調査のためのモデル調査地帯とする。この地帯は、関東地方106枚の5万分の1地形図図葉のうち別図に示す26枚の地域とする。
(3)(精密植生区分別現存量推定地域の抽出)
モデル調査地帯の中から5万分の1地形図ごとに20地域を選定し、精密植生区分別現存量推定地域とする。
(4)(空中写真による植生型区分)
現存量算出単位として次のような植生型に区分する。空中写真を判読するとともに、さらに林相図、土地利用図、土地条件図等既存資料を活用する。
|
1.森林(林地、森林、農用林、防風林、風致林等) ア 樹種区分 ○天然林、人工林 ○常緑樹、落葉樹 ○針葉樹、広葉樹、マツ、スギ、混こう樹等主要樹種別 イ 樹高階区分(新植、他4~5階) ウ 樹冠層構成区分(6~9型) エ 疎密度階区分(4~5階) オ 立木本数階区分(3階) 2.特用樹林 桑、茶、果樹、竹林 3.農用地 水田、畑 4.草地 牧野、自然草地、人工草地 5.都市緑地 樹林地(樹林被覆率)草生地(草生被覆率) 6.その他 |
(5)(植生区分型別ヘクタール当り単位現存量の推定)
空中写真の判読により、さらに森林調査簿、統計資料現地照合等により、植生区分型別にヘクタール当り単位現存量を推定する。
(6)(植生現存量モデル調査地帯5万分の1図葉単位別現存量の推定)
5万分の1地形図26枚のモデル調査地帯について(3)により推定された単位現存量をもとに、森林調査簿、統計資料、現地照合等により、植生区分型単位別現存量を推定する。
(7)(植生区分図のヘクタール当り平均単位現存量の推定)
関東地方全域植生区分図について植生区分別にヘクタール当り平均単位現存量を推定する。
(8)(植生区分図による全域現存量の推定)
関東地方全域について、植生区分図により、植生現存量を推定する。
(9)(植生現存量図の作成)
推定した植生現存量を5万分の1地形図106枚に図化する。
5.植生生産量調査
(1)(植生区分ごとの生産量算定指数の確定)
既存の知識、研究報告、統計報告等の資料を基礎として、植生区分ごとの生産量算定指数を確定する。
(2)(全域植生生産量の算定)
植生現存量図をメッシュ化し、メッシュ単位別現存量を算出するとともに、(1)の結果をあわせて、メッシュ別生産量を算出する。
(3)(植生現存量及び植生生産量の磁気テープヘの収録)
関東全域について、メッシュ別植生現存量及び植生生産量を磁気テープに収録する。
6.鳥類生息分布調査
(1)(調査区の決定)
5.5km×4kmのメッシュ(5万分の1地形図を縦横各4等分した16箇のメッシュ)を1個の調査区とし全県を通じて1連番号を付す。
これによって調査区は、茨城県242、栃木県255、群馬県252、埼玉県146、千葉県206、東京都85、神奈川県94の合計1,280個となる。ただし、島しょは除く。
(2)(調査員)
調査員は鳥類に関して相当程度の知識を有する者を3調査地ごとに1人の割合で選定して、調査を委嘱する。調査員のうち高度の知識を有する者を1都県あたり2人を選び専門委員とする。
(3)(調査の方法)
調査は年2回、調査区内の観察、聴きとりおよび既存の資料を活用して、調査区に生息する鳥類の種名を記録する。
調査記録の整理は様式1によって行なう。
(4)(調査の取まとめ)
(ア)鳥類生息分布調査票の作成
調査結果にもとづき、メッシュ番号ごとの鳥類の種名一覧表を作成する。
(イ)鳥類分布地図
(ア)の鳥類の種名一覧表から20万分の1地勢図に次の区分により鳥類の生息分布を示す図面を作成する。
A 70種以上
B 50~69種
C 30~49種
D 10~29種
E 10種未満
(5)(調査報告)
調査実施者は、別紙様式-2の鳥類生息分布調査報告書および様式-1の鳥類生息分布調査記録簿に20万分の1地勢図および5万分の1地形図を添付して昭和49年2月28日までに環境庁自然保護局長に報告するものとする。
7.改変状況資料の収集
土地利用図、土地条件図、林相図、人口密度、環境汚染等の人間活動による改変状況の既存資料を収集整理する。
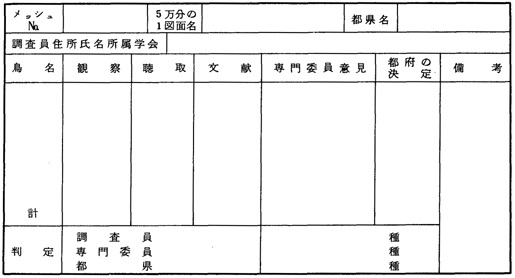 |
|
(注) |
1.鳥名欄には、都県内に生息する鳥類名を印刷しておくこと。 2.観察、聴取、文献欄には、該当する場合は○印を付し、備考欄には発言者の氏名、文献名等を記入すること。 3.観察した範囲を5万分の1地形図に記入し添付すること。 |
8.調査の実施主体
(1)植生現存量調査及び植生生産量調査は民間コンサルタントが実施に当る。
(2)鳥類生息分布調査及び改変状況資料の収集は、関東地方7都県が実施に当る。
|
鳥類生息分布調査報告書 1.鳥類生息一覧表 (都県名) |
|
鳥 名 |
メッシュNo(各都県1から始まる通し番号) |
計 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)メッシユごとの鳥類生息分布調査記録を添付すること。
2.鳥類生息分布地図 20万分の1の地勢図にメッシュごとの区域を記入し、鳥類生息分布をA、B、C、D、Eの記号で記入した図面とする。 |