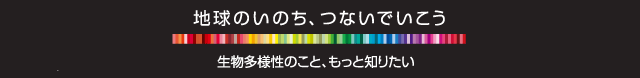生物多様性地域連携促進セミナー in 長野
| 日時 | 平成25年1月19日(土)10:30~16:00 |
|---|---|
| 会場 | 塩尻総合文化センター 講堂(長野県塩尻市大門七番町3番3号) |
| 主催等 | 主催:環境省 共催:長野県、国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)、生物多様性自治体ネットワーク |
| 参加者数 | 約140名 |
| 当日の 発表資料 |
開催挨拶
主催側から環境省が、共催者を代表して長野県から開会の挨拶がありました。
森 一弘(環境省 松本自然環境事務所長)
市村 敏文氏(長野県 環境部 自然保護課長)
 | 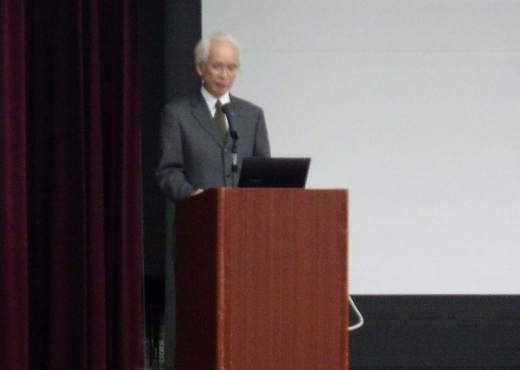 |
| 森 一弘(環境省 松本自然環境事務所長) | 市村 敏文氏(長野県 環境部 自然保護課長) |
生物多様性キャラクター応援団 共同宣言式
UNDB-Jキャラクター「タヨちゃん、サトくん」と長野県キャラクター「めぐるん」が、今後協力して生物多様性に関する普及啓発に取り組むため「生物多様性キャラクター応援団共同宣言」を行いました。

講演・説明・事例発表(i) 特別講演「トキはなぜ禿げたか ―生物多様性と地域連携―」
山岸 哲 氏(公益財団法人山階鳥類研究所名誉所長/兵庫県立コウノトリの郷公園園長)

トキの主な食物はドジョウ、カエル、ミミズです。ドジョウはトキのために日本各地から導入された経緯があり、遺伝的には日本各地だけでなく大陸系統のものまでが混ざり合ってしまっています。佐渡には新種記載されたばかりのサドガエルという希少な種がいますが、トキはこのカエルも良く食べています。また、シャープゲンゴロウモドキという現在は希少種になっている種を食べていたという記録も山階鳥類研究所にあります。ミミズについては人為的な環境である田んぼの稲が成長し餌が採りにくくなる時期に利用するという習性があるようです。
 この他に、アメリカザリガニもよく食べますが、これはよく知られているように外来種です。一方、トキの天敵となるキツネやテンも、佐渡島に人為的に持ち込まれたほ乳類です。つまり、生物多様性の視点からみれば、トキが本来生息した環境とは随分違う状態で野生復帰させています。それは、単に一度絶滅してしまった種を野生に戻すということよりも、トキを含めた生きもののつながりを取り戻すことに大いに意義があります。佐渡島だけでなく長野をはじめ、日本全国の地域にある生物の多様性のつながりを守り、作っていく地域の人の協力が必要です。
この他に、アメリカザリガニもよく食べますが、これはよく知られているように外来種です。一方、トキの天敵となるキツネやテンも、佐渡島に人為的に持ち込まれたほ乳類です。つまり、生物多様性の視点からみれば、トキが本来生息した環境とは随分違う状態で野生復帰させています。それは、単に一度絶滅してしまった種を野生に戻すということよりも、トキを含めた生きもののつながりを取り戻すことに大いに意義があります。佐渡島だけでなく長野をはじめ、日本全国の地域にある生物の多様性のつながりを守り、作っていく地域の人の協力が必要です。
(ii) 「多様な主体の連携による生物多様性保全活動の意義」
竹田 純一 氏
(農山村支援センター事務局長/里地ネットワーク事務局長/内閣官房地域活性化伝道師/東京農業大学学術研究員)

生物多様性の地域連携保全活動とは何か。分かりやすい例としては、市民団体等と企業と学校教育機関の三つが連携して保全活動を行うことです。現在は、これらが別々に活動を行っているために、活動に広がりがなく一部の興味のある人たちしか参加していません。生物多様性にあまり興味が無い人々を、保全活動に組み込んでいくためには工夫が必要です。
例えば、企業や学校の中の「心の悩み」に着目してみました。里山で新入社員研修を1ヶ月間行うと、仲間意識が出来て辞めにくくなるそうです。里山で新入社員研修をすることで、企業にも里山の維持管理にも役に立つ。このように社会の要求と地域の生物多様性の保全を結びつけていく工夫が求められているのです。(この後、北海道や福井県、三重県、鹿児島県などで行われている先行事例を通して、市民団体等と企業と学校教育機関が連携して生物多様性の保全活動の進め方について説明がありました。)
生物多様性に関わる地域計画を策定する際には、地域に対する愛着と連帯感が生まれるように工夫することが大切です。企業の方には、「生き物にぎわい企業活動コンテスト」を参考にして欲しいと思います。また、地域でコーディネーターをする人は、明確なビジョンを持ち分かりやすく説明すること、目標レベルを徐々に上げ飽きないようにすることが大切です。
 (iii) 「生物多様性地域連携促進法のあらましと生物多様性をめぐる最近の話題」
(iii) 「生物多様性地域連携促進法のあらましと生物多様性をめぐる最近の話題」環境省 生物多様性施策推進室 常冨 豊 室長補佐
(発表要旨)
「生物多様性国家戦略2012-2020」の策定やUNDB-Jの活動状況などについて紹介したほか、生物多様性地域連携促進法の目的や制度のあらましについて説明しました。
 (iv) 「希少なチョウの舞う里山『いいやま』」
(iv) 「希少なチョウの舞う里山『いいやま』」月岡 伸太郎 氏(飯山市教育委員会学習支援課 係長)
飯山市内では、地域住民が中心となって行っているヒメギフチョウの保全活動、自然保護団体が中心となって活動するオオルリシジミの保全活動がある。これらの蝶に関わる既存の保全活動を、地域連携の枠組みを使って継続的に大きくしていくために、教育委員会が中心となって活動をしていることを説明していただきました。
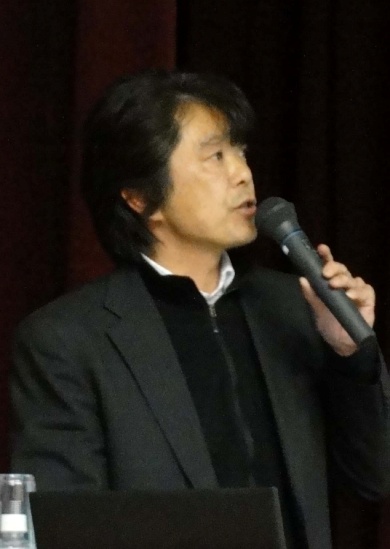 (v) 「浅間山麓における地域連携による生物多様性の保全活動」
(v) 「浅間山麓における地域連携による生物多様性の保全活動」橋詰 元良 氏(NPO法人浅間山麓国際自然学校 代表理事)
NPOが中心となり、上信越高原国立公園において、風景地保護協定を環境省と結び、動植物の保護、景観保全、人材育成などの環境保全活動を実施している。自然環境の保全と観光振興の両立など、克服すべき課題も多いとのご説明をして頂きました。
 (vi) 「信州・信濃町癒しの森事業と生物多様性との関わり」
(vi) 「信州・信濃町癒しの森事業と生物多様性との関わり」小池 克英 氏(信濃町産業観光課 主事)
地元の森林自然資源を活用し、官民共同で「癒やしの森事業」を実施している。これは森林セラピー事業で、エコツーリズムとヘルスツーリズムの中間のようなもの。現在140名のガイドのガイド収入、町内宿泊費など、事業の導入など経済的にも持続的な活動になりつつあること、また今後は生物多様性の視点を取り込んで、森林整備に回す資金を確保したいとのご説明をして頂きました。
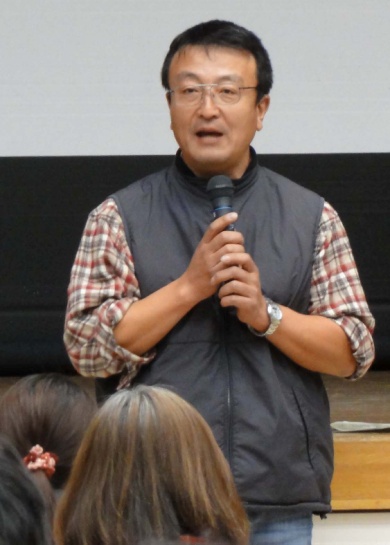 (vii) 「生き物に関心を示さない農家のために」
(vii) 「生き物に関心を示さない農家のために」小川 文昭 氏(ひとむしたんぼの会)
田んぼの生物多様性を守る主体は農家であり、生物多様性保全に関して農家の役割が大きい。現在、志を同じくする農家と、減農薬・無農薬の農業の実践を広げている。除草剤を使わないと収量が減る。でもその代わり何万匹ものトンボを生み出すことが出来る。こういうことを誇りに思えるかどういかがこういう農業を続けられるかの根幹にあると思う。農家が自身の田んぼや地域の文化を大切にする気持ちが強くなれば、心にゆとりがうまれ、田んぼの生きものに興味が湧き、生物多様性を守ることにつながる、上記のような主旨のご説明をいただきました。
ワークショップ・パネルディスカッション
事例発表ごとの4つのグループに分かれて、多様な主体の連携による生物多様性保全活動を進めるために、「それぞれの立場で何ができるか」、「既存の取り組みをさらに展開するためにどうすれば良いか」というテーマで、発表者・参加者を交えて意見交換を行いました。
パネリストからは、ワークショップでの意見として、連携活動のさらなる展開には自治体間や自治体内での横断的な情報共有、職員の現地活動への参加、ICT技術の活用、消費者による生産物の買い支えなどが重要との報告がありました。
山岸氏からは、この種の地域活動に参加したいと考える研究者は多く、是非、皆さんから声をかけて頂きたい、また、トキの保護活動の経験から定期的に計画を見直して進むべき方向を修正していくことが重要とのコメントがありました。また、竹田氏からは、本日の事例発表が各地での活動に大変参考になると述べた上で、活動内容が修正しやすい活動計画としておくと良いとのコメントがありました。


ワークショップとパネルディスカッションの様子
ブース展示
セミナーの会場では、NPO/NGOや民間企業、農業団体、行政など10の活動団体が、それぞれの取組を紹介するパネルを展示しました。各パネルの前では取組の課題等についての意見交換が行わました。
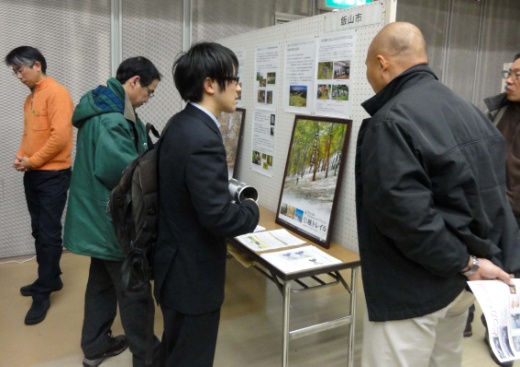

ブース展示の様子