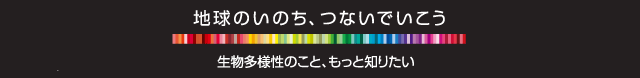生物多様性地域連携促進セミナー in 兵庫
| 日時 | 平成25年2月9日(土) 13:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 兵庫県立人と自然の博物館(兵庫県三田市弥生が丘6丁目) |
| 主催等 | 主催:環境省 共催:兵庫県、国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)、生物多様性自治体ネットワーク 協力 : 兵庫県立人と自然の博物館 |
| 参加者数 | 約100名(サイドイベントには約70名) |
| 当日の 発表資料 |
開催挨拶
主催側から環境省が、共催者を代表して兵庫県から開会の挨拶がありました。
佐山 浩(環境省 近畿地方環境事務所長)
栃尾 隆 氏(兵庫県 農政環境部 環境創造局長)
 |  |
| 佐山 浩(環境省 近畿地方環境事務所長) | 栃尾 隆 氏(兵庫県 農政環境部 環境創造局長) |
生物多様性キャラクター応援団 共同宣言式
UNDB-Jキャラクター「タヨちゃん、サトくん」、兵庫県キャラクター「はばタン」、兵庫県立人と自然の博物館キャラクター「ひとはく博士」が、今後協力して生物多様性に関する普及啓発に取り組むため「生物多様性キャラクター応援団共同宣言」を行いました。

講演・説明・事例発表(i) 「多様な主体の連携による生物多様性保全活動の意義」
竹田 純一 氏
(農山村支援センター事務局長/里地ネットワーク事務局長/内閣官房地域活性化伝道師/東京農業大学学術研究員)

里地里山は、我々の先祖が長い歴史の中で作り上げてきたもので、わずか150年程前までは、ほとんどの日本人が里地里山で生活し、生物が食物などを通じてつながっていました。日本人の暮らし方の変化に伴い、多くの生物が絶滅の危機に瀕しています。こうした地域の生物多様性の損失を防ぐためには、都市域の住民が里地里山に関わりながら生物多様性を保全する活動に積極的に関われる仕組みづくりが重要です。
生物多様性の地域連携保全活動とは何か。分かりやすい例としては、市民団体等と企業と学校教育機関の三つが連携して保全活動を行うことです。現在は、これらが別々に活動を行っているために、活動に広がりがなく一部の興味のある人たちしか参加していません。生物多様性にあまり興味が無い人々を、保全活動に組み込んでいくためには工夫が必要なのです。例えば、企業や学校の中の「心の悩み」の問題があります。里山で新入社員研修を1ヶ月間行うと、仲間意識が出来て辞めにくくなるそうです。労働力不足に悩む里山の生物多様性保全と企業の要求をマッチングさせる。このように社会の要求と地域の生物多様性の保全を結びつけていく工夫が求められています。(この後、北海道や福井県、三重県、鹿児島県などで行われている先行事例を通して、市民団体等と企業と学校教育機関が連携して生物多様性の保全活動の進め方について説明がありました。)
生物多様性に関わる地域計画を策定する際には、地域に対する愛着と連帯感が生まれるように工夫することが大切です。企業の方には、「生き物にぎわい企業活動コンテスト」を参考にして欲しいと思います。また、地域でコーディネーターをする人は、明確なビジョンを持ち分かりやすく説明すること、目標レベルを徐々に上げ飽きないようにすることが大切です。
 (ii) 「生物多様性地域連携促進法のあらましと生物多様性をめぐる最近の話題」
(ii) 「生物多様性地域連携促進法のあらましと生物多様性をめぐる最近の話題」環境省 生物多様性施策推進室 山内 洋志 室長補佐
「生物多様性国家戦略2012-2020」の策定やUNDB-Jの活動状況などについて紹介したほか、生物多様性地域連携促進法の目的や制度のあらましについて説明しました。
 (iii) 「地域連携保全活動による持続可能な都市型里山を目指して」
(iii) 「地域連携保全活動による持続可能な都市型里山を目指して」上野 真理子氏(西宮市環境局環境緑化部環境学習都市推進課 副主査)
西宮市では、現在、甲山グリーンエリアにおいて、環境学習を軸とした持続可能な里地・里山づくりを進めるため、地域連携保全活動計画を策定しています。甲山(かぶとやま)グリーンエリアで実施中の活動事例のほか、地域連携保全活動計画の策定に向けた体制や「持続可能な都市型里山を目指す」という今後の検討の方向性についてご説明をいただきました。
 (iv) 「東お多福山草原保全における多様な主体による地域連携」
(iv) 「東お多福山草原保全における多様な主体による地域連携」橋本 佳延氏(東お多福山草原保全・再生研究会 事務局)
東お多福山のススキ草原では戦後の管理放棄に伴い、遷移等による縮小とササ優占による質の変化が起こり、生物多様性が低下しています。東お多福山草原保全・再生研究会は、「ススキ草原の再生」「草原の生物の保全」「ワイズユース」をめざす複数団体により構成される団体で、当地域での生物多様性の保全活動を行っています。
草原の保全・再生には「大面積管理の必要性」「複雑な規制・所有形態に伴う許認可・調整の煩雑性」「多様な主体が共有できる公的な目標の提示」などの課題があり、これらの解決には促進法の適用が有効と考え、神戸市・芦屋市に地域連携保全活動計画の作成に関する提案を行った事などを紹介いただきました。
 (v) 「淡路水交会による漁業者の森づくり活動」
(v) 「淡路水交会による漁業者の森づくり活動」西野 恵介氏(南淡漁業協同組合 組合員)
淡路水交会では、豊かな海の再生を目指した活動として、柴漬けによるアオリイカ産卵床の造成や漁業者の森作り(植樹活動)の活動を実施しています。
この活動は、淡路水交会だけではなく、協賛企業や漁業関連系統団体、行政、造園業者、地元小学校等の協力のもと実施しているもので、現在、島内に大きく広がってきていますが、今後はこの活動をどのように継続していくかが課題であるとのお話をいただきました。
(vi) 「尼崎の森中央緑地における百年の森の創造を目指した市民・企業・行政の連携」

塚原 淳 氏
(兵庫県 阪神南県民局 尼崎港管理事務所 尼崎21世紀プロジェクト推進室長)
兵庫県では、尼崎21世紀の森づくりを進めています。この先導拠点である尼崎中央緑地では、生物多様性の森創造をテーマに、“地域の森を手本とする”こと、“タネから森を育てる”こと、“みんなの力で育てる”ことをルールとして定め、市民グループや博物館等が協力しているほか、企業や学校も「協定」や「苗木の里親」などの形で関わっています。
兵庫県阪神南県民局の塚原氏からは行政の立場から、尼崎21世紀の森づくりの全体像や、森づくりから森づかいへこれから目指すことについてお話をいただきました。
越柴 豊 氏(尼崎信用金庫 営業統括部 次長)
尼崎信用金庫の越柴氏は、「尼崎21世紀の森づくりの推進に関する協定」を締結した企業として、苗木の育成、苗木の里親案内人の育成、苗木の里親コーナーの設置、定額積立定期預金「どんぐりの木」の発売、植樹活動など、これまで実施されている活動やプロジェクトの内容についてご紹介をいただきました。
ワークショップ
事例発表ごとの4つのグループに分かれて、多様な主体の連携による生物多様性保全活動を進めるために、「それぞれの立場で何ができるか」、「既存の取り組みをさらに展開するためにどうすれば良いか」というテーマで、発表者・参加者を交えて意見交換を行った。



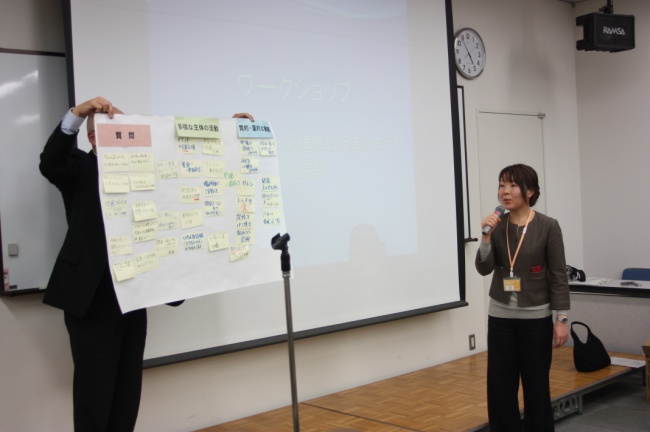
ワークショップの様子
ブース展示
人と自然の博物館、中セミナー室で開催したブース展示では、兵庫県内を中心に14団体が出展し、活動内容の紹介などを行いました。
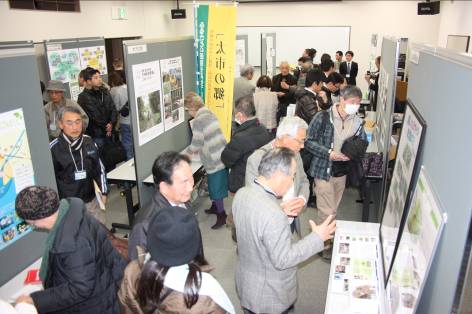
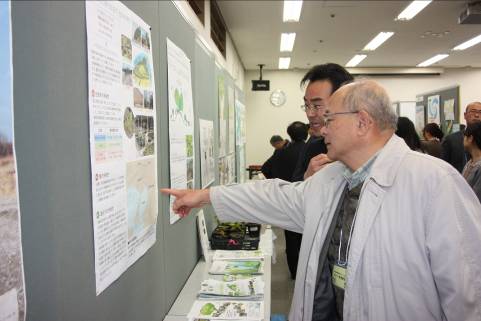
ブース展示の様子
サイドイベント(子供向けイベント)
人と自然の博物館、実習室で開催したサイドイベント(子供向けイベント)では、別会場で子どもたちを対象としたサイドイベントを開催しました。このサイドイベントでは、参加者が「生物多様性キャラクター応援団共同宣言式」、「生物多様性おにごっこ」、「MY行動宣言」、キャラクターたちとの写真撮影会に参加し、生きものと環境について学習しました。
*「生物多様性おにごっこ」とは、生きものの種類によって脅威(外来生物やウイルスなど)に対する感受性が異なること学ぶことができるクイズです。


サイドイベント(子供向けイベント)会場の様子