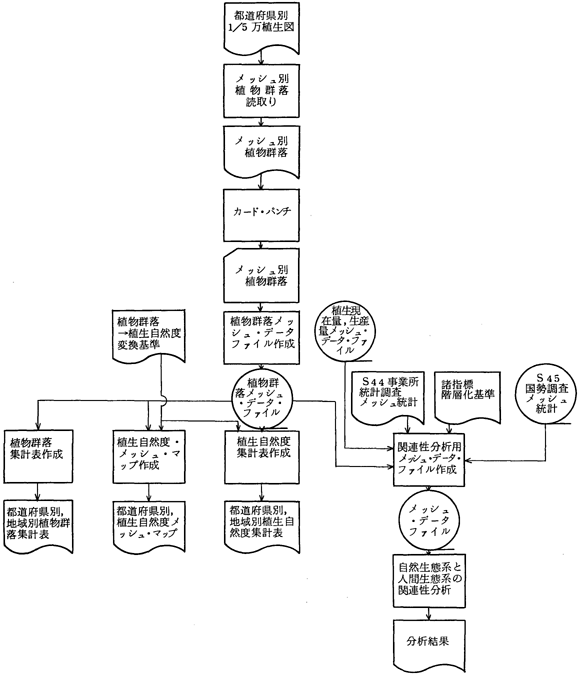
2.植生自然度調査
今日、環境診断や自然環境調査の基礎図として最も一般的に利用されている植生図は、現存植生図と現在の潜在自然植生図である。前者は、現実に野外に生育している植物群落を対象に、各種の植生単位で図化したもの。後者は、植生に加えられている現在の一切の人為的干渉が停止されたとしたら、その立地がどのような自然植生を支え得るかというポテンシャルな能力を考えた理論的な植生を図化したものである。今回の第一回調査では前者の現存植生図が全国にわたって作成された。この現存植生図は相観によるものと、植物社会学的調査に基づいたものが、よく利用される。相観による植生図とは、見た目に映ずる外観をとらえたもの、すなわち植物群落の優占種や生活形を主とした外見をとらえたもので、文化庁が昭和42年から47年までの6年間に行った天然記念物緊急調査で作成したものがこれに近い。一方、植物社会学的現存植生図とは、植物群落の種組成に重点をおいて、群落を構成する種の組み合わせをとらえたものである。すなわち植生野外調査に基ずく群落組成表比較作業を行って、国際的基準での全出現群落についての群落単位の決定を行う。国土を十段階の植生自然度にクラス分けするには、どうしてもこの植物社会学的な種組成により区分される現存植生図を必要としたわけである。今回1年あまりの短期間で20万分の1のスケールの全国の現存植生図ができたのは前記文化庁の相観による植生図に負う所が多い。しかし、植物社会学の大系化が十分でなく、1年間という時間的制約から、植生図の精度には或程度の限界を認めざるを得ない。しかし、今回の調査により従来のものより一歩前進した精度の高い植生図が全国的にカバーされたことは間違いない。
植生図の凡例づくりは前記懇談会を中心にして行われ、原則として群集及び群集レベルの群落を用い次のような分類に従って全国で362の凡例が作られ、さらに各調査者が随意必要とする凡例を追加するシステムがとられている。
1 寒帯・高山帯自然植生
2 亜寒帯・亜高山帯自然植生
3 亜寒帯・亜高山帯代償植生
4 ミズナラ−ブナクラス域自然植生
5 ミズナラ−ブナクラス域代償植生
6 ヤブツバキクラス域自然植生
7 ヤブツバキクラス域代償植生
8 河辺、湿地、塩沼地、砂丘植生(各クラス共通)
9 植林地、耕作地植生(各クラス共通)
10 その他(各クラス共通)
実際の植生図作成は各都道府県の植生専門家によってフィールド調査と航空写真解読を併せて行われ、縮尺5万分の1地形図に原図が作られ、付属資料として、各県の植生概説を行うと共に、代表的群落については、1ケ所以上の植生調査表を添付した。最終的には縮尺20万分の1にとりまとめられ植生図が印刷された。
群集:特定の種組成。生育条件及び相観をもつ植物社会学的群落分類における基本単位。
自然植生:人間の影響をまったく受けず、自然のままに生育する植生。
代償植生:人間の影響によって、立地本来の自然植生が様々に置き代った植生。
植物群落を全国及び地方別に集計したものが表−2である。実際の作業は全国土面積約37万平方キロを縦横ほぼ1キロの区画(縮尺5万分の1の地形図各1枚を縦横に20等分した区画)−行政管理庁の地域メッシュ−すなわち1キロメッシュに区切り、都道府県で作成した現存植生図から各メッシュごとに優先する群落種別を確定した。なお、各メッシュごとに優先する群落を確定する方法として、1キロメッシュの中心に直径5ミリの円を描き、その円の中に優先する植物群落で代表させた。各メッシュごとに判定した植物群落を全国、地方別、都道府県別に電算機で集計した。
各植生区分が全国で示める比率を表3、図1でみると、例えば寒帯・高山帯自然植生0.4%・亜寒帯・亜高山帯自然植生7.3%、ミズナラ−ブナクラス域自然植生12.7%、ヤブツバキクラス域自然植生1.6%であった。
かって日本の暖帯地方全域−九州・四国及び本州の関東以西と、東北地方までの海岸沿の地域はヤブツバキクラス域に属する常緑広葉樹で占められていたが、人間の定住と開発が進むことによって、今日では国土の1.6%しか常緑広葉樹の自然植生が残されていないことがわかる。またわが国で、ミズナラ−ブナクラス域に属する領域は、月平均気温10℃以上の月が4〜6カ月つづく所とされており、北海道南西部、東北地方一帯、中部地方の山地(高山・亜高山地帯を除く)その他近畿から九州にかけての標高の高い山岳部がこの領域に当る。今日、ミズナラ−ブナクラス域の自然植生についても全国の12.7%が残っているにすぎない。
表4は、植生区分地方別分布比率表である。これを事例的に、チシマザサ−ブナ群団、スズタケ−ブナ群団、ブナ−ミズナラ群落、クリ−ミズナラ群落、スダジイ群落についてそれぞれの地方別分布をみたものが図2である。例えば、日本のブナ林の主要部を構成し、北海道渡島(おしま)半島から日本海ぞいに中国山地まで発達するチシマザサ−ブナ群団は全国で17,266メッシュ存在するほか、これを地方別にみると東北56.5%、北海道20.3%、北陸10.9%である。また、関東平野のまわりの山地部から丹沢・伊豆半島さらに近畿から九州にかけてみられるスズタケ−ブナ群団は、全国で1.638メッシュ存在するが、これら地方別にみると、関東44.7%、四国15.5%、近畿14.4%、東海8.5%である。さらに、ヤブツバキクラス域の自然植生の事例として、スダジイ群落をみると、全国で1,442メッシュ存在するが、これを地方別にみると、九州51.1%、沖縄35.6%、関東4.9%、近畿3.3%である。
“自然度”とは、「自然は人間の手のつけ具合、人工の影響の加わる度合によって、きわめて自然性の高いものから、自然性の低いものまで、いろいろな階層にわかれて存在する」という意味で使った言葉である。陸域については、植物群落の種の組合せによって土地に対する人間の手のつけ具合が判定できることが、植物社会学の研究により明らかになってきた。すでに西ドイツの著名な植物生態学者エーレンベルグ教授は、人間の干渉の度合に応じた植物景観を8つの階層に分類している。
今回の調査では、まず、植生図作成に際して定めた約360の植物群落を、小委員会の意見をききながら、10のグループに区分し、これを植生自然度とした(表5参照)。ここでは、自然草原、高層湿原、高山植物、極相林などの自然植生を自然度10及び9の一番上におき、緑のほとんどない住宅地、工場などの造成地を一番低い自然度1とし、その中間に二次林、植林地、二次草原、農耕地等の順にランクさせている。10と9は自然性の高さにおいて同じランクで、10は草原のような単層の植物社会、9は森林を形成する多層の植物社会である。また、一般的にみて10は人為に対して弱い植生(復元しにくい植生)、9は人為に対して比較的強い植生(復元しやすい植生)ということもできる。しかし、これはあくまでも10と9両者間の比較であって、原生林のような9の森林が人為に対して強いというわけではない。8と7も類似したランクで、8は特に9の自然林に近い植物群落であり、7は例えば武蔵野のクヌギ−コナラ林のように常に人為の影響下にあるもの。5と4及び3と2もそれぞれほぼ同じランクに属する。従って10段階の植生自然度を一般にわかりやすくし土地利用的に括約すると表5のとおりⅥ〜Ⅰまでのランクになる。また植生自然度10〜6の大部分が一般に“樹林地 と呼ばれる土地である。自然度2のうち緑の多い住宅地は「緑被率60%以上のもの」と定義した。
このように、“植生自然度”とは植物社会学的な観点からみて土地の自然性がどの程度残されているかを示す一つの指標であり、それは半面人間による自然破壊の程度を示す指標でもある。これまで感覚的にしかつかんでいなかったわが国の自然破壊の実情が改めて植生自然度という物差によって確認されることになる。今回の“緑の国勢調査”では、この植生自然度の調査に最大の重点がおかれた。なお詳細な群落ごとの自然度区分は資料編を参照されたい。
実際の作業は、現存植生図から各メッシュごとに優先する群落種別を確定し、表5の区分表に従ってこの群落種別を植生自然度に転換したものであり、全国、地方別、都道府県別に集計した。植生図よりメッシュ別に植物群落を読み取り、植生自然度の判定・集計を行い、最後に各種の要因分析を行う手順は次のフローチャートのとおりである。
植生自然度の全国集計(表6参照)をみると、まず自然草原や自然林など植生自然度が109と高く、人為のほとんど加わっていない地域は国土の22.8%、一方市街地・造成地など緑のほとんどない植生自然度は3.1%となっている。これによって国土の約8割は何等かの意味で人間の手が加わっていることが明らかになった。6〜10までの植生自然度をプラスすると森林面積になるが、その比率が全体で69.1%で、既に発表されている林野統計の比率と結果的に一致した。また、農耕地(2+3)、植林地(6)、二次林(7+8)、自然植生(9+10)がそれぞれほぼ20%台を占めて等分されていることも興味深い。
地方別に植生自然度を比較すると自然度9及び10の比率の高い地方は、北海道の61.7%を最高に、沖縄35.8%、北陸19.7%、東北18.2%となっている。また自然度1の比率の高い地方は、関東8.4%、沖縄7.7%、東海7.3%、近畿6.1%等である(図3参照)。なお、北海道では択伐方式の天然林施業が主体であり、このため今回作成された現存植生図からは人為のほとんど加わらない自然林と或程度人為の加わった天然林との区別が困難であった。したがって9に属する自然植生を多く残している。沖縄の910及び1の両方とも高いのは、西表など一部の島嶼部に照葉樹の天然林が残されていることと、沖縄本島などが相当開発されていることが原因である。地方別にみると自然度109に属する自然性の高い地域は、北海道、東北、北陸、南九州等北と南の一部にかたよって残っていることがわかる。
都道府県別に植生自然度をみると、自然度109の比率の高い県は、北海道(61.7%)を最高に、沖縄(35.8%)、富山(30.9%)、比率が20%を超える青森、山形、石川、新潟等(図4参照)。緑のほとんどない自然度1の比率の高いのは東京(39.7%)、大阪(34.2%)、神奈川(28.0%)で、愛知、千葉、埼玉も1の比率が10%を超え大都市圏の緑破壊が目立つ。(表7参照)。
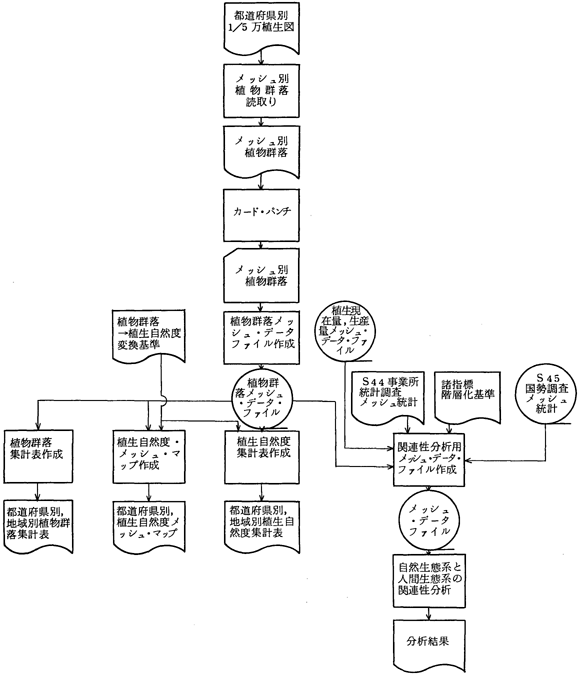 |
都道府県の植生自然度の事例として、東京都の植生自然度をみよう。図5は東京都植生自然度のメッシュ・マップ(島嶼部省略)で各区画のメッシュごとに植生自然度が数字で表示されており、自然度1〜9に対しては同じ数字が、自然度10に対しては数字0がうちだされている。さらにメッシュ・マップをわかりやすく図化したしたものが図6である。
以上の図から次のことがわかる。まず、東京都全域のうち約40%が緑のほとんどない市街地、工場地等で占められており、都心から約30キロ離れた立川附近までほとんど緑のない地区で覆われ、さらに中央線等の鉄道の沿線に沿って自然度1がスプロール状に周辺地域までのび自然破壊が進んでいく。都内23区内は緑のない裸地がほとんどで、かって武蔵野の雑木林として知られた近郊地も、多摩ニュータウンをはじめとする大規模な宅地造成のためにみるかげもなく、自然度2の田畑や小規模な林がわずかばかり残されている。緑のない自然度1の地区が進んでいくことは半面自然の後退を意味する。緑の後退現象は、ホタル・トンボ・バッタなど私たちの身近にすむ生き物類の後退曲線とも相関がある。ただ23区内では、明治神宮の森などが自然度9になっている。(明治神宮の森は人工的に植栽されたものだが、数十年たった今日では、潜在自然植生の構成種が生き残り、シラカシ群集を形成している。)またメッシュ図には表現されていないが、皇居の森や白金(しろがね)の自然教育園にはスダジイ林等の自然植生が残されている。
立川をすぎ八王子から青梅あたりになると自然度が次第に高まり2〜7とバラエティに富んでくる。青梅から西の奥多摩地域はほとんど自然度6の植林地になり緑の多い地区に出合うようになる。北西部の秩父多摩国立公園に属する山岳部ではブナ、シラビソなどの9の原生林に近い植生が残されている。
多摩川南部から町田北部の丘陵地には、武蔵野の2次林であるクヌギ−コナラ群集が見いだされる。これは自然度7に判定されている。また、近郊地帯で特色のある自然植生として高尾山のモミ・ブナの天然林があげられる。この地域は明治の森高尾国定公園の核心部に当る自然度9で、貴重な都市近郊林となっている。
都内23区内にもわずかながら自然度10がみられる。これは多摩川等の河川敷にオギやヨシなどの冠水河辺草原が“自然草原状態”で生えているため10に判定されたのが理由である。
オギやヨシの植物群落は、その土地には本来生育している自然植生であるため、自然度10に判定される。しかし、これらの群落は一度人手により破壊されても、非常に回復が早く、その種組成的判定からは自然に生育する群落と区別がつかない。それ故、多摩川の河川敷の条件のよい所には、オギやヨシの群落が出現し自然度10がみられるのである。多摩川の河原はある程度人手が付いており、総合的にみて自然性は低くなっているが、普通の平坦地、山地の樹林に比較してみれば、まだ自然はよく残っている。例えば、河辺にはカワラノギクのように多摩川等の固有種とされているものが生育しており、このような観点からみれば、これが自然度10に判定されたことも理解できる。今後の植物社会学の発展につれて、このように現在では自然の群落と判断せざるを得ない植物群落も、人為との関わり具合によって下位の群落に分かれるかも知れない。植生自然度区分上の今後の検討課題と考えられよう。
地域の植生自然度をみるために(ア)自然的なタイプとして富士山、(イ)都市的なタイプとして伊勢湾沿岸地域、(ウ)歴史的なタイプとして奈良盆地の三つの地域を事例として取り上げ、比較してみよう。(表8参照)
山梨、静岡の両県にまたがり、自然の比較的残っている富士山を中心とする20キロ圏地域をみると、自然度の高い9+10は14.8%、自然度の低い1は4.3%、5の2次草原が15%あるのも特徴的。これを国立公園区域の内と外で比較すると9+10は公園区域内が27.1%に対し、公園区域外は3.5%。1についても内が1.3%に対し外は7.O%であった。全般的に9+10が意外に少なく、視覚で感ずる風致度と生態的にみた植生自然度がかならずしも一致しないことがわかる。
日本の象徴とされている富士山においても、自然植生と呼ばれるものは15%弱に過ぎない。
(イ)伊勢湾沿岸地域(図8参照)
都市開発や臨海工業地帯の造成が進んでいる伊勢湾沿岸地域(愛知県知多郡から名古屋市を経て、三重県四日市市に至る沿岸10キロの帯状地域)をみると、自然度1が43.4%で地域の半分近く都市化、工業地化が進んでいる。2の農耕地が残り半分近く、41.5%を占め、6〜10の樹林地はわずか10.7%。ここでも自然度10が長良川の河口部や一部の海岸に点在してる。これは多摩川の場合と同様ヨシ、オギなどの水辺植生が自然度10と判定されているからである。しかし実際の環境は相当都市化が進み、水質も汚濁が著しく、自然度10といった感覚からは程遠い。これは先にも述べたように、ヨシ、オギが環境の悪化に対する抵抗性が強く回復も早いため、植生自然度10になっているためである。
歴史的風土にめぐまれた奈良盆地(奈良県)をみると、自然度1は14.0%と比較的多い面積を占める。一方、自然度9+10の自然は0.2%しかないが、植生自然度6〜10の樹林地が44%も残っている。このことから、歴史的風土を構成する主要な自然は9の自然林ではなく、2の農耕地と6の植林地及び7の二次林であることがわかる。
植生自然度を都市別に比較すると大都市や工業都市などの緑の後退の現象が明らかになると共に、都市の性格やタイプに応じた自然度の分布がみられる。都市の植生自然度の事例として、仙台、水戸、東京23区、川崎、大阪、奈良、尼崎の7都市を取り上げて比較した(表9参照)。
まず、“森の都”と言われる仙台では、森林である自然度6〜10の地区が28.1%も残されており、その名のとおりである。水戸でも20.7%で、仙台と同じような傾向にある。歴史的自然環境の豊かな奈良市では6〜10が最も多く市域の54.4%も占めている。これに対し過密都市東京23区は1.3%、大阪市ではほとんど6〜10はみられない。工場の多い尼崎も大阪市と同様であるが、川崎では市街地の後背地になる多摩川丘陵に自然度7の二次林が13.7%も残されている。しかしこの二次林も早急に近郊緑地として保全対策を進めないと宅地化の波に消されてしまうだろう。
逆に緑のほとんどない自然度1をみると、大阪市は90.8%にものぼり、東京23区が87.2%となっててるが、大阪市にくらべ4〜10が4.9%ほどみられ、自然の断片がわずかながらうかがえる。奈良市では1が16.4%、仙台25%、水戸5%であった。
国立公園の植生自然度の事例として、知床、箱根、伊勢志摩、大山、阿蘇、西表の6国立公園の地区を比較する(表10、図10参照)
まず、わが国で最も原始的な国立公園のタイプである北海道の知床国立公園は全公園区域の99%が自然度910で占められ、その大部分がエゾマツ、トドマツ等の原生林からなっている。比較的観光開発の進んでいる箱根団地でもまだ自然度9+10が30.9%も残されている。これは神山や二子山などのブナの天然林・自然草原である。しかし、緑のほとんどない自然度1が箱根団地の4.5%を占めており、次の伊勢志摩国立公園の3.9%と共に6公園の中で1の比率は最も高い。伊勢志摩の自然度910.2%は神宮林などのシイ天然林である。ここでは、6の植林地が51.9%を占めているのが特徴的である。
大山隠岐国立公園の大山団地では6の植林地と7の二次林が団地の大半を占めている。ここの自然度918.5%はブナの天然林である。阿蘇国立公園では自然度5ススキの二次草原が全公園区域の43.6%をカバーしているのが特徴的。阿蘇の自然風景を構成するのは二次草原の牧野景観で、定期的な採草や火入れ等の人為によって維持されている風景である。ここの自然度9、10は九重山や阿蘇山に残された自然林や自然草原、自然裸地。
沖縄の最南端にある西表国立公園については、イリオモテヤマネコで有名な西表島の公園区域だけをみると、北海道の知床国立公園と同じ程度の原始性を示し、9の照葉樹やマングローブの原生林で覆われている。これだけ大規模にスダジイ、オキナワウラジロガシ、タブノキ等の照葉樹林が残されている地域は日本ではこの島以外にない。しかし、西表国立公園全域の植生自然度をみると、竹富(たけとみ)島や黒島などの人文景観にめぐまれた島も公園区域に含まれているため、全体として植生自然度は低くなり9+10は82.5%となっている。
ア 植生自然度10、9:自然草原、自然林
植生自然度{10+9}の地域は、全国の約23%を占めているが、北海道、沖縄を除いた本土では11%しか残っていない。しかも国土の北と南、山岳地や離島にその大部分が偏在している。10、9それ自体で学術的価値を持つ植生が多いと共に、開発の進んだ今日では稀少な存在として相対的な価値を帯びつつある。従って、自然環境保全の面から先取り的に確保されねばならない地域である。
植生自然度10の大部分は人為に対して最も弱い植生・復元困難なあるいは不可能な植生であるから、道路等の開発や各種の土地利用により生態系の維持が困難となる場合が多い。9のうち大面積の原生林が残された地域は、わが国の自然の原型として、植生だけでなく野生動物や地形・地質も含めた純度の高い生態系を保存するため十分な安全率を見込み、広大な面積が厳正に確保されねばならない。(アメリカの原始地域法では、生態系を厳正に保全し、徒歩による孤独なレクリエーションだけが認められる地域の最低面積として2,000ヘクタールが定められている。また、わが国の自然環境保全法では、原則としてすべての人為を排する原生自然環境保全地域の最低面積として1,000ヘクタールが定められている。)なお、10、9の相当部分は、自然公園の特別保護地区や第1種特別地域、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域の特別地区等の要件を具えるものである。例えば、国の指定する原生自然環境保全地域や自然環境保全地域の指定要件として自然度を応用すると表−11のごとくなる。
また国立公園の事例をみても、原始性の高い知床国立公園では公園区域の99%、西表国立公園では83%が10と9で占められている。特に、植生自然度という指標は、自然公園の計画や、管理の問題を検討する際の有益な基礎資料となる。従来の計画手法は、視覚に映ずる風致景観という観点から公園計画が決定され、それによって管理が行われる場合が多かった。従って公園の特別保護地区が、亜高山帯以上の低木林やお花畑、または特殊な地形地質からなるランドマーク等の風景を対象として設定されることが多かった。森林帯に残された自然度9の生態的に重要な天然林が自然公園の第2種や第3種の特別地域として、森林伐採の対象になっている場合もある。今後は、視覚的な風致景観という観点とともに、生態的な自然度という観点からも公園計画を再検討し、管理の強化を図る必要がある。さらに、都市地域、農村地域に点在する10、9は次のような特性を持つものであり、地域計画に当ってその保全に留意しなければならない。
ア 郷土の森など生態的なシンボルとなるランドマーク。あるいは、社寺有林などのサンクチュアリー。
イ 昆虫、野鳥の生息地など地域の自然の多様性を保持する地区。
ウ 傾斜地のシラカシ林や水辺地のハンノキ、ヨシ群落などきびしい自然条件に耐え残存する10、9は災害等に対する生活環境保全上の指標植生。
イ 植生自然度8、7:二次林
{8+7}の二次林地域が全国の26%を占めている。特に、中国地方では58%、近畿39%、四国で38%も二次林地域が占めている。一般に二次林はかっての薪炭林等が現在自然放置され粗放な土地利用形態が多く、二次林の比率の高い地方や地域の土地利用の可能性とその保全を今後どのように考えるかが問題となる。
8、7の二次林地域は、比較的人為に対して強く、人間の干渉と調和を保って成り立つ植生であるが、例えば次のような留意事項が考えられる。
まず、武蔵野のクヌギ、コナラ林のように地域に対して風土的特性を与えているものがある。また、歴史的自然環境を構成する重要な樹林地でもある(例えば、奈良盆地の24%)。次に自然公園の中にある8、7は、自然公園の景観上、風致上重要な特別地域を構成するものもある(例えば、大山隠岐国立公園大山団地では35%)。自然公園や自然環境保全地域の緩衝地域としての役割もはたしている。さらに都市地域に残存する二次林は、都市住民にとってレクリエーション的価値のある都市林を形成し、さらに自然度の低い都市に自然の多様性を与えている。また、植生自然度10、9の残されている比率の低い関東から以西の西南日本にかけて、それらの地方に残されている植生自然度8はより自然性の高い9への遷移途上の植生として、学術的価値を有するものがある。
ウ 植生自然度6〜2:植林地、二次草原・農耕地
全国の49%を占めている。6は造林地や植栽された樹林地(全国の21%)、5、4は二次草原(4%)、3、2は一般に集約的な農耕地(24%)である。これらの地域においては自然と人工との調和を保ちつつ、良好な自然環境の育成と、生産緑地としての生産力の維持を図ることを保全上留意する。したがって、計画に当って、土壌の地力維持及び地下水や土地そのものの保全等を図り、自然の基礎の損傷を避ける必要がある。なお二次草原の5、4は草地生態系として学術的に重要なものもあり、また自然公園の中にある5の二次草原は原野景観(例えば阿蘇国立公園の44%)として公園の主要な自然風景を構成するものもある。
エ 植生自然度1:緑のない都市、工業地
全国の3%を占めている。しかし、東京都では40%(都内23区では87%)、大阪府34%(大阪市では91%)、神奈川県28%に達し、大都市圏の都市砂漠化が認められる。この地域は生活環境の保全上緑の創造と復元が最も急を要する場所である。特に過密都市や工業都市では、自然度1の地域が市域の大部分を占めているため、残された緑を保護することよりも、緑化により積極的に緑を回復・整備する対策が考えられなければならない。一方、まだ緑の比較的残されている都市では、都市緑地、生産緑地として保全を図る。いずれにしても、市民の生活に必要な緑を確保する目標基準として“緑の環境基準”の設定が考えられなければならない。
以上のように植生自然度の10から1までを組み合わせることによって、計画対象地域の生態的特性と保全上の問題点をある程度把握できるであろう。上記の組み合わせの他に例えば、1を除いた10〜2は広い意味での緑地、10〜4は集約的な人為の加わらない良好な自然環境を維持した自然緑地、3〜2は農業的な生産緑地、8〜6は林業地帯等の分析の方法がある。また、環境影響評価(環境アセスメント)に当って、自然度は自然環境の現況把握のための一つの目やすともなろう。