位
置
図
5
万
分
の
1
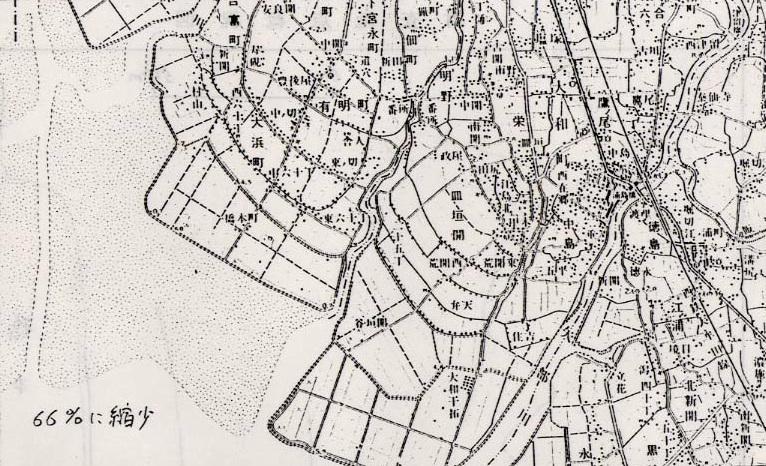
概
況
写
真

地 図 |
調査区 |
市 町 村 名 |
地 名 |
|
調査年度 |
1989 |
23 |
27 |
柳川市 |
橋本開地先 |
都道府県名 |
福岡県 |
|
環 |
1.地形 |
|||||
底 |
1.底生動物 |
|||||
鳥 |
春・秋のシギ・チドリ類の渡来は、種数、個体数ともに日本でトップクラスである。オオソリハシシギ・オグロシギ・ダイシャクシギ・ホウロクシギはいずれも300〜500羽、アオアシシギ・チュウシャクシギはいずれも1000〜2000羽、オバシギ・コオバシギは数百羽が渡来する。他に、ツルシギ・アカアシシギ・コアオアシシギなども渡来する。 |
|||||
そ |
近年、陥没により、干潟の面積が減少しつつあり、また、干潟の分布状況も変化しつつある。 |
|||||
位 |
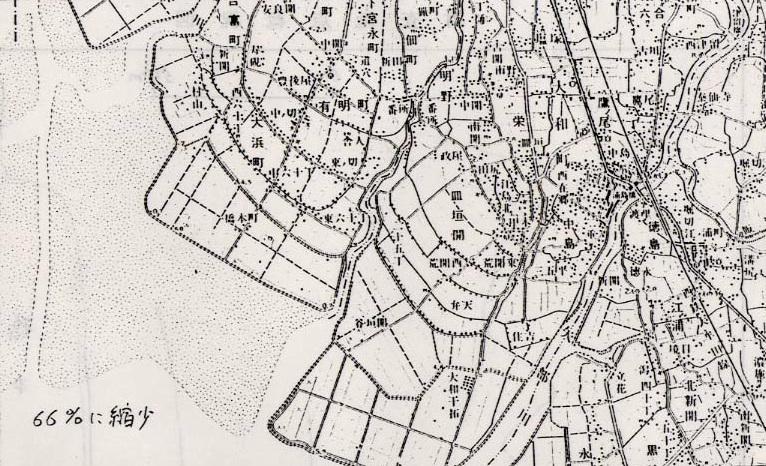 |
概 |
 |
調 |
所属 福岡県自然環境研究会 |
調査 |
○1 現地調査 1989年10月15日 |
資 |
福岡県有明水産試験場「福岡県有明海域の干潟分布調査」1981 |
||
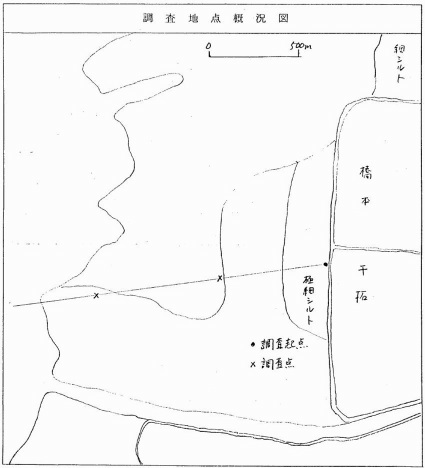 |
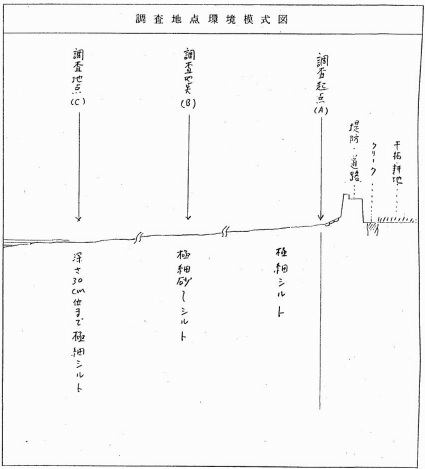 |
目次へ