位
置
図
5
万
分
の
1
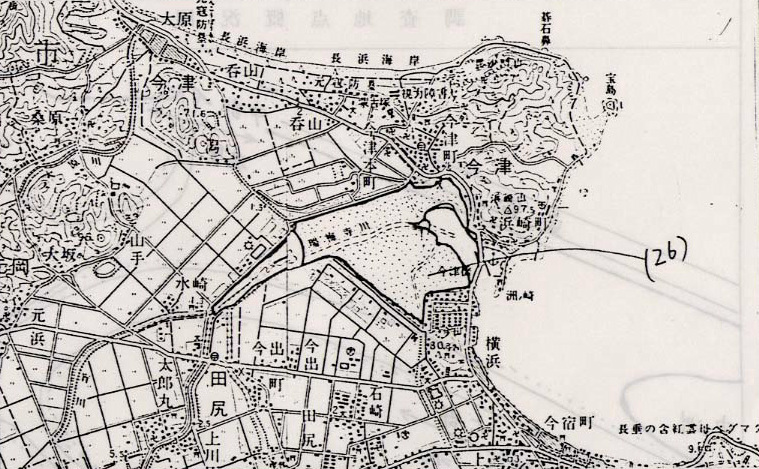
概
況
写
真

地 図 |
調査区 |
市 町 村 名 |
地 名 |
|
調査年度 |
1989 |
20 |
26 |
福岡市 |
今津 |
都道府県名 |
福岡県 |
|
環 |
1.地形・底質 |
|||||
底 |
1.底生動物 |
|||||
鳥 |
博多湾では、和白干潟と並んでシギ・チドリの渡来数が多い干潟である。オグロシギ・オオソリハシシギ・ダイシャクシギ・ホウロクシギなど大型シギ類は、それぞれ10〜50羽が渡来する。チュウシャクシギ・ソリハシシギ・ハマシギなどは、数百羽単位で渡来する。シロチドリ・コチドリの渡来数は、近年減少しており、千羽単位で渡来することは少なくなっている。冬にはカモ類が数万羽渡来するが、多いのはマガモ・カルガモ・ヒドリガモ・ホシハジロ・オナガガモなどである。他にサギ類・カイツブリ類・カモメ類なども干潟を利用している。時には、ヘラサギ・クロツラヘラサギ・ヒシクイ・マガン・サカツラガン・ハシボソカモメなども渡来する珍島のメッカでもある。 |
|||||
そ |
<その他の特記事項> |
|||||
位 |
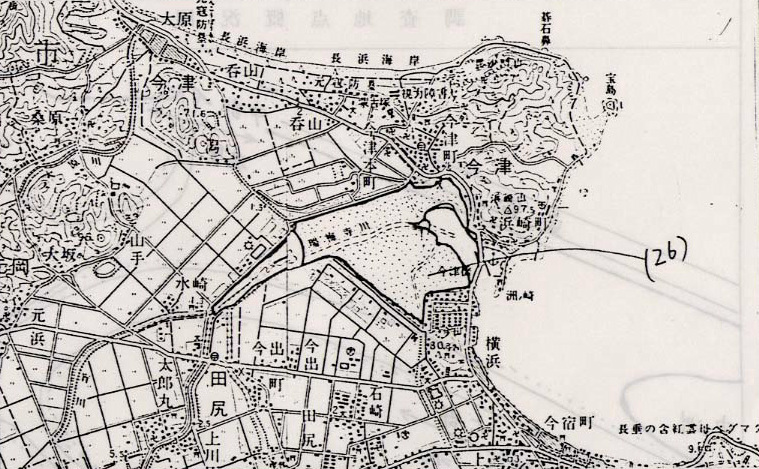 |
概 |
 |
調 |
所属 福岡県自然環境研究会 |
調査 |
○1 現地調査 1989年11月12日 |
資 |
|
||
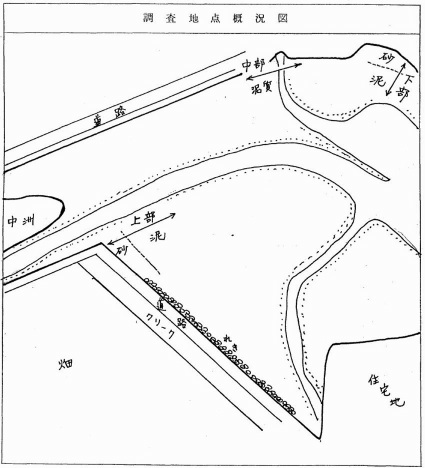 |
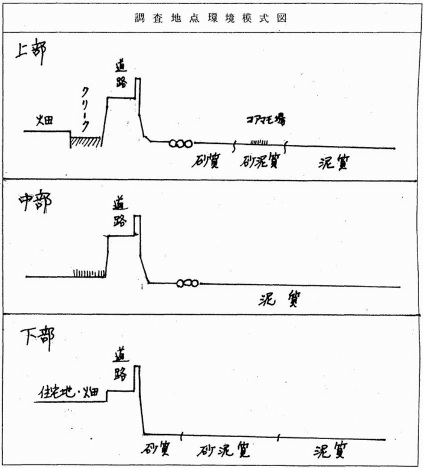 |
目次へ