位
置
図
5
万
分
の
1
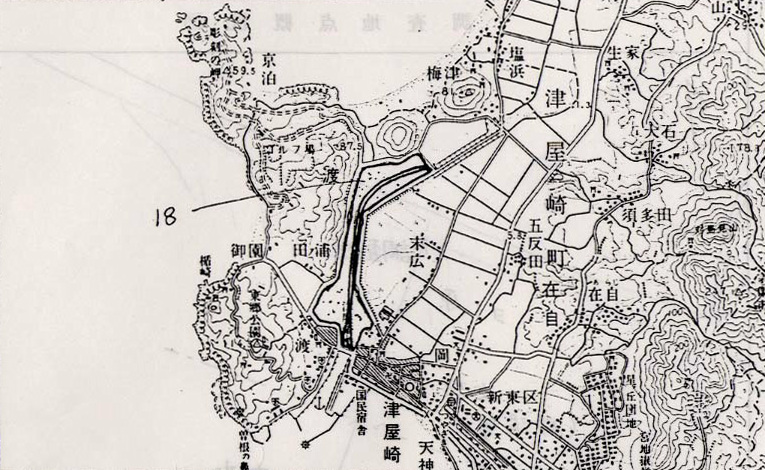
概
況
写
真

地 図 |
調査区 |
市 町 村 名 |
地 名 |
|
調査年度 |
1989 |
19 |
18 |
津屋崎町 |
渡 |
都道府県名 |
福岡県 |
|
環 |
1.地形 |
|||||
底 |
1.底生動物 |
|||||
鳥 |
シギ・チドリ類の利用は少なく、シロチドリ・コチドリ・キアシシギ・ソリハシシギ・アオアシシギなどが、少数渡来する程度である。一方、カモ類・カモメ類の利用もあまり多くないが、サギ類の利用はコサギをはじめとしてよく見られる。 |
|||||
そ |
(記入例) |
|||||
位 |
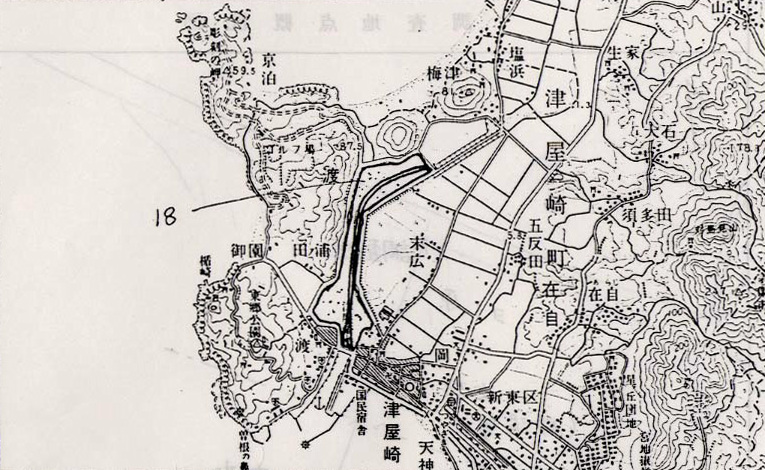 |
概 |
 |
調 |
所属 福岡県自然環境研究会 |
調査 |
○1 現地調査 1989年11月11・12日 |
資 |
|
||
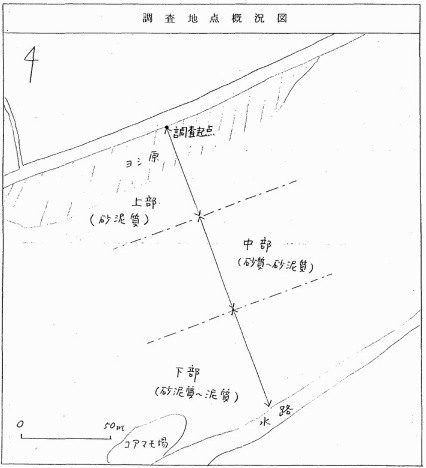 |
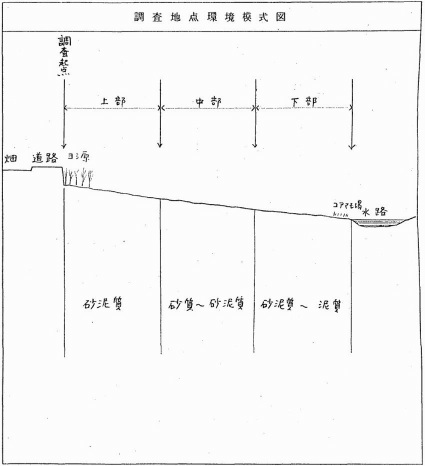 |
目次へ