位
置
図
5
万
分
の
1

概
況
写
真

地 図 |
調査区 |
市 町 村 名 |
地 名 |
|
調査年度 |
1989 |
19 |
20 |
倉敷市 |
高州 |
都道府県名 |
岡山県 |
|
環 |
1.倉敷市児島唐琴沖の祖父祖母島の東方に、大潮時、広く干出する砂洲の干潟。東西約1.1km、広さ約13haの「へ」の字形で、潮間帯下部に相当する。東西方向に微高地が連なり、南側へはなだらかに深くなっている。最高地点を起点とし、南方番ノ洲方向に測線を設けた。測線上に東から潮下帯が割り込んだ状況で、起点から約20m地点に低潮線があり、これより以遠は潮下帯のアマモ場が続き、起点から約130m地点の低潮線以遠は再び微高地の潮間帯下部である。沖出しの150m地点を経て、起点から約300m地点で再び潮下帯となる。砂底で、水は清澄、きれいである。 |
|||||
底 |
1.潮下帯のアマモ場内の調査地点を含めて、確認種数は65種と多い。なかでも節足、軟体、環形動物が多く、大半を占めている。干潟上部の微高地部では、潮流による砂の移動、潮干狩による踏圧や海底の撹乱の頻回のため、動物は少ない。干潟下部の低潮線近くでは軟体動物のアサリが卓越して数多く、イトゴカイ科、ケヤリ科、スピオ科(以上環形)、ホシムシ類(星口)、アラムシロガイ、ホトトギスガイ(軟体)、ヤドカリ類、アナジャコ(以上節足)が数多く、ハスノハカシパン、クモヒトデ類(以上棘皮)、が得られた。そして、踏圧が頻回の起点近くでは、アサリ、キサゴ(以上軟体)、スピオ科の他は数少なく、種数も少ない。また、潮下帯のアマモ場内では軟体動物の腹足類の種数は少ないが、上記低潮線上部の動物相に匹敵する動物相が得られた。 |
|||||
鳥 |
満潮時小群で群れるカモメ類を見るが、満潮時の鳥類の利用はほとんどない。大潮干潮時に出現する干潟で、シギ・チドリ類の利用はあるものと考えるが、海岸より距離を隔てた地であり、適切な資料も見当らない。 |
|||||
そ |
・著名なアサリの潮干狩地として親しまれている。 |
|||||
位 |
 |
概 |
 |
調 |
所属 川崎医大 |
調査 |
1 現地調査 1989年7月20日 |
資 |
|
||
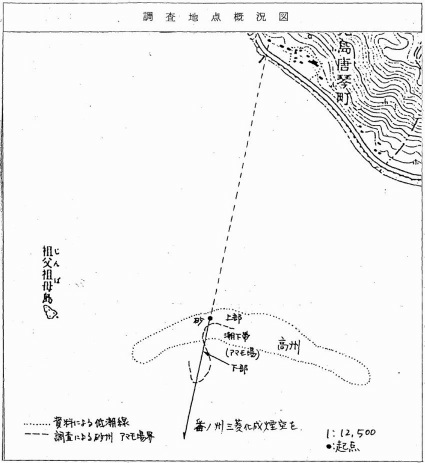 |
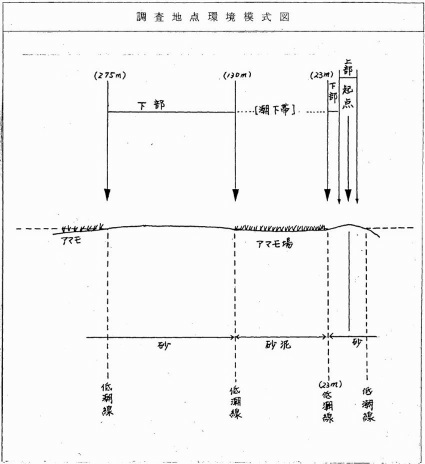 |
目次へ