位
置
図
5
万
分
の
1

概
況
写
真

地 図 |
調査区 |
市 町 村 名 |
地 名 |
|
調査年度 |
1991 |
8 |
5 |
白子町 |
浜宿海岸 |
都道府県名 |
千葉県 |
|
環 |
九十九里浜の南部、北部が砂浜部の波による侵食が進んでいるのに対して、南白亀川北部から真亀川周辺の砂浜部は侵食の傾向は顕著でなく、勾配が緩やかで、干潮時には100mを越える砂地が干出する。典型的な砂地の干潟は本邦でも珍しい。砂浜上部はコウボウムギ、ハマヒルガオなどの植生が発達し、後背地はクロマツ林と九十九里浜の自然がよく残されている。海水は清澄で、波による攪拌の影響による濁り以外の有機汚染の傾向はまったく認められない。現在の0ころ海浜部に対する開発計画も存在しない。 |
|||||
底 |
砂浜は一般に底生生物相は貧弱であるのが普通であるが、浜宿海岸周辺は二枚貝、甲殻類など豊富である。高潮線の有機性の漂着物の多いところには、ヒメハマトビムシが多く、季節によってはスナガニが分布し、中部にはヒメスナホリムシが卓越し、下部には小型二枚貝のフジノハナガイが多量生息するとともに、異尾類のハマスナホリガニ、多毛類のチロリ、アミ類のシキシマフクロアミなどが多い。また、大潮低潮線付近にはキンセンガニ、ツメタガイ、ヒラコブシガニ、チョウセンハマグリ、ダンベイキサゴなども観察される。漂着有機物としてホンダワラ、アラメ、多くの紅藻類、魚類、クラゲやコケムシなど豊富である。 |
|||||
鳥 |
年間を通してのシギ・チドリ調査は過去実施されていない。今回の調査で周年観察したが、予想以上にシギ・チドリが渡来数が多いことが確認された。外洋砂浜性のミツユビシギは6−7月を除いて周年観察され、渡り期にはハマシギが多数飛来した。両種とも越冬することが確認された。ミユビシギはこの海岸では満潮時にも干潮時にも採食し、その主要な食物はヒメスナホリムシであった。更に、補足的な食物として多毛類のチロリやシキシマフクロアミを利用している。ハマシギは砂浜では前種ほど適応した採食者ではなく、南白亀川河口の小干潟や内陸部の水田、湿地などで採食する。 |
|||||
そ |
当該海岸では開発計画はない。砂浜では潮干狩、釣りが行なわれているが、その九十九里浜の原型とも考えられる優れた自然景観をもつにもかかわらず、一般にはあまり知られず、かつ、シギ・チドリの観察も行なわれていない。大潮低潮線付近には内湾干潟ではほとんど見られなくなったツメタガイも生息する。 |
|||||
位 |
 |
概 |
 |
調 |
所属 東邦大学 |
調査 |
○1 現地調査 1991年8月24日 |
資 |
|
||
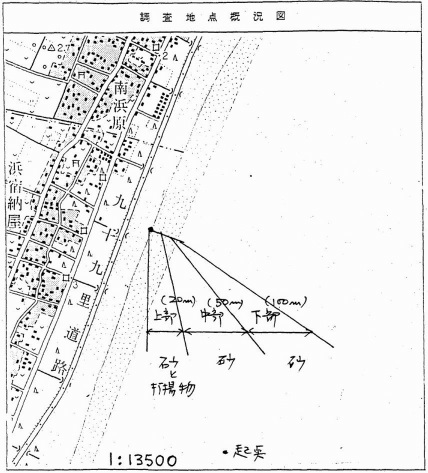 |
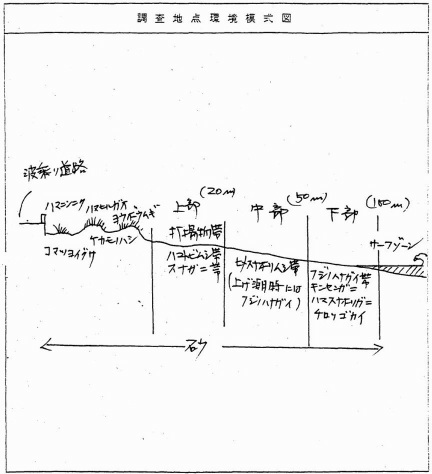 |
目次へ