位
置
図
5
万
分
の
1
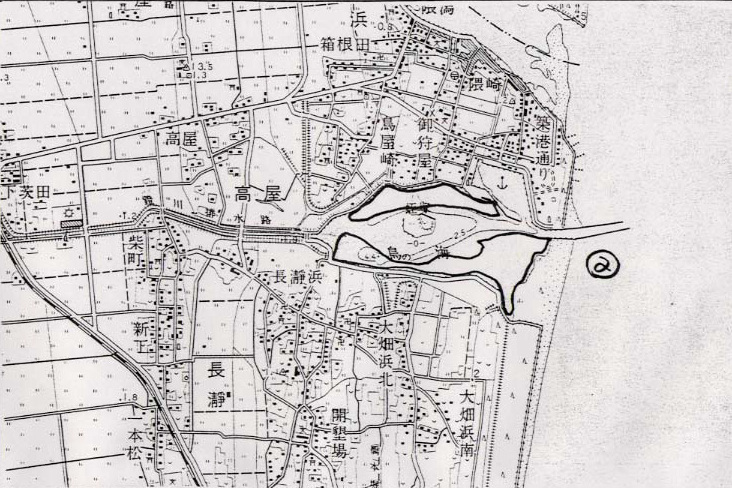
概
況
写
真
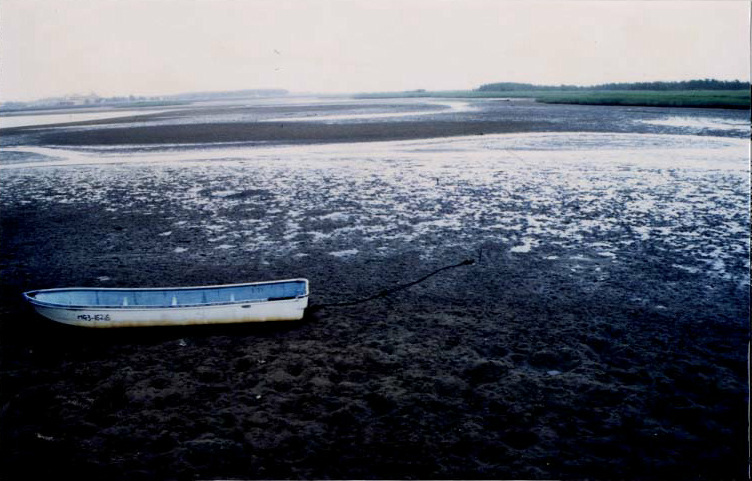
地 図 |
調査区 |
市 町 村 名 |
地 名 |
|
調査年度 |
1991 |
20 |
2 |
亘理町 |
鳥の海 |
都道府県名 |
宮城県 |
|
環 |
1.地形・底質 |
|||||
底 |
1.底生動物 |
|||||
鳥 |
県内では蒲生干潟、井土浦等と並ぶ数少ない干潟であり、シギ・チドリ類の渡りの中継地として重要な干潟となっており、26種が記録されている。 |
|||||
そ |
|
|||||
位 |
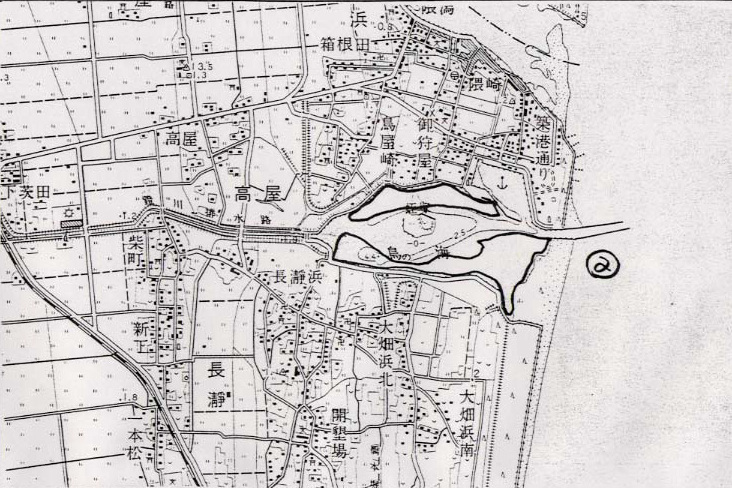 |
概 |
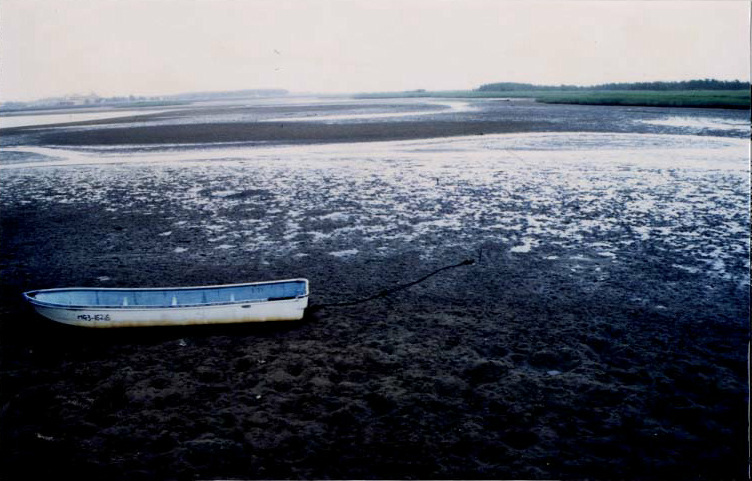 |
調 |
所属 東北大学 |
調査 |
○1 現地調査 4年7月14日 |
資 |
|
||
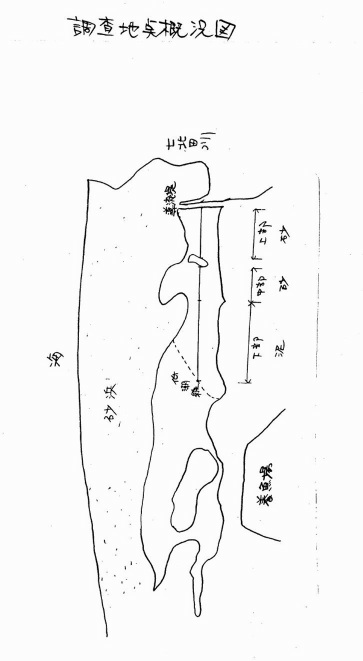 |
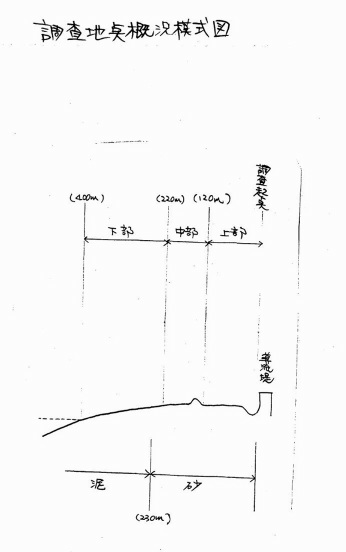 |
目次へ