位
置
図
5
万
分
の
1
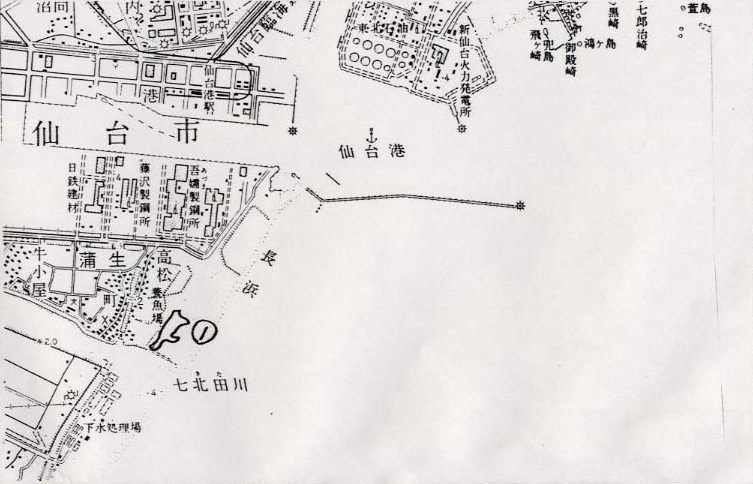
概
況
写
真

地 図 |
調査区 |
市 町 村 名 |
地 名 |
|
調査年度 |
1991 |
14 |
1 |
仙台市 |
蒲生 |
都道府県名 |
宮城県 |
|
環 |
1.地形・底質 |
|||||
底 |
1.底生動物 |
|||||
鳥 |
当干潟は県内の他の干潟に比べ、鳥の種類が極めて多様であり、かつ干潟面積の割には個体数も非常に多く、特にシギ・チドリ類の飛来地として知られている。現在までに確認されているシギ・チドリ類は47種に及び、日本産シギ・チドリ類の75%に達している。 |
|||||
そ |
|
|||||
位 |
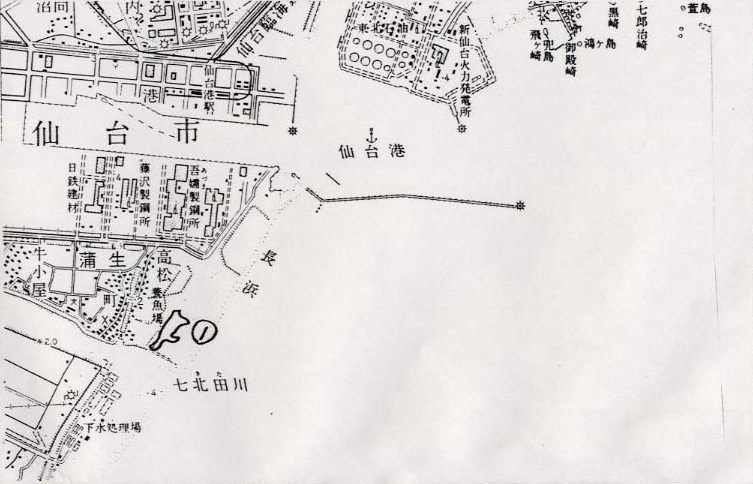 |
概 |
 |
調 |
所属 東北大学 |
調査 |
○1 現地調査 4年7月15日 |
資 |
蒲生干潟環境保全対策基礎調査報告書 |
||
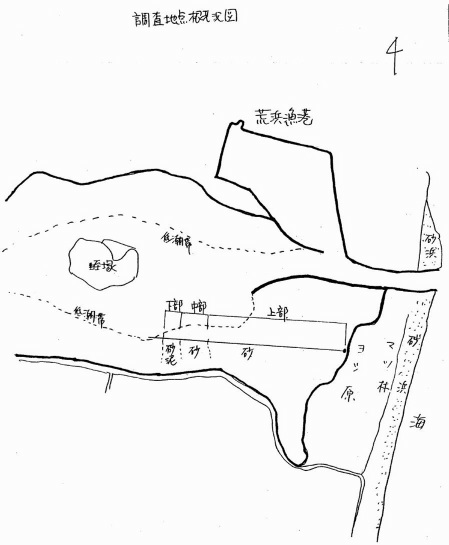 |
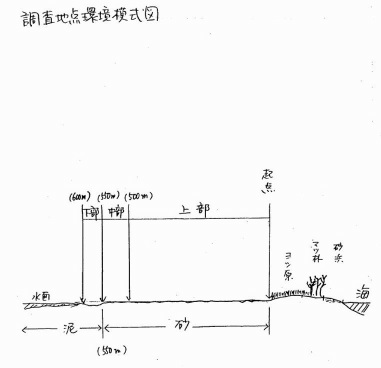 |
目次へ