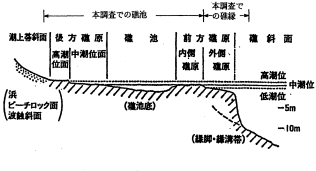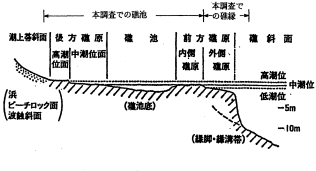�@
�Q�D�T���S�ʊC�撲�����ʂ̉��
�����@�G��1
�@
�i�P�j�͂��߂�
�@
�u�T���S�ʒ����v�͎��������f���h���Γ��Ȗk�̔�T���S�ʊC��Ə��ȓ�̃T���S�ʊC��ɕ����Ď��{���ꂽ�B���̂����T���S�ʊC�撲���͕����Q�i1990�j�N�x�`�����S�i1992�j�N�x�A���������Ɖ��ꌧ���e�X���{�����B�����N�x�ƒ����C��͕\�V�̒ʂ�ł���B
�@
�@
�\�V�@�N�x�ʒ����n��ꗗ�i�T���S�ʊC��j
| �N�x |
�������� |
���ꌧ |
|
|
| �����哇���k�� |
| �����哇�암�A�^�_���A�f���h�� |
| ���V���A�^�_���A�f���h�� |
|
| ����{�� |
| ���d�R���� |
| �{�ÌQ���y�щ���{�����ӗ��� |
|
�@
�@
�������@�͒�߂�ꂽ���{�v�j�i�����f�ځj�ɂ���čs��ꂽ���A�T���͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�T���S�ʂ̒n�`�͐}�S�̂悤�ɋ敪�����B����̒����ł͑O���ʌ������ɏʒr�i�{�����ł͓����ʌ����܂ށB�܂����d�R�����̐ΐ��ʌ��܂ށj�Əʉ��i�O���ʌ��y�яʎΖʁj�ɋ敪���A�ʒr�ɂ��Ă̓J���[�ʐ^�i���y�n���@�y�щ��ꌧ�Ǝ����������B�e�������́j�̔��ǁi�ʒr�̖ʐρA�C��̐���A���ň�̒����j�ƌ��n�W�{���o�����i�T���S���ʁA����^�ʔ�x�������j�ɂ��T���S�ʂ̌�����ʓI�ɔc�����A�ʉ��ɂ��Ă͒������g�q�@�i������}���^�@�j�ɂ�铥���i�T���S����^�ʔ�x�y�уT���S��Q�����j�ɂ��T���S�ʂ̌�������I�ɔc�������B
�Ȃ��A�����s�ɑ����鏬�}���Q���C��ƉΎR�C��ɂ��ẮA�ܓx�I�ɂ����ۂ̃T���S�̏o���I�ɂ��T���S�ʊC��Ɋ܂܂����̂ł���B�������A���̒n��̓T���S�ʂ̔��B���s�\���ŁA�ʐ^�ɂ�锻�ǂɓK���Ȃ����߁A����̒����ł͏��}���Q���C��ɂ��Ă̂݁i�ΎR�C��ł͒��������{���Ă��Ȃ��j�����Ƃ�y�ъ����������������Ƃɂ��āA�}���^�@�ƌ��n�����撲�������{����A���̌��ʂ������s�������Ă���B
�{�_�͏�L�̉��ꌧ�A���������ɂ��̃f�[�^����ɑ��ʃT���S�̕��z����͂������̂ł���B�Ȃ��A���}���Q���C��ɂ��ẮA�O�q�̂悤�ɓ��ʂȎ戵���������G���A�ł��邽�߁A�{�_���Ɍʂɍ���݂��āA���̒��ňꊇ���ĉ�͂��s�Ȃ����B
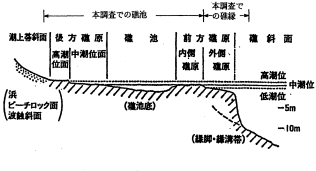
�}�S�@���ʒn�`�̊T�O�}�i�����A1980�j
�@
�i�Q�j�ʒr�̖ʐϋy�яʒr���̃T���S�Q�W�ʐ�
�@
���������{�����T���S�ʁi�ʒr�j�̑��ʐς͖�96,000ha�ł���B���d�R�������ő�Ŗ�39,000ha���߁A�����ʼn���C��̖�27,800ha�������i�\�W�j�B��Q���̃T���S��ʐς͓f���}�̔����Ȗʐς������Ɩ�83,000ha�ŁA�����̌��ʂƖ�13,000ha�̍��ق�������i���m�q��1980�j�B����͉��������Ɣ��d�R�����̒����C��̑���ɂ��Ƃ��낪�傫���B�A���A����y�ы{�×C��ł͋t�Ɍ������Ă��邪�A����͑�Q�����ʐ^��Ŕ��ʂł���͈͂܂łƂ��āi�ʎΖʂ��܂܂�Ă���j���肵���̂ɑ��A����͒����Ώۂ��ʒr�Ƃ��A�ʎΖʂ̓}���^�@�ɂ�钲���ΏۂƂ��A�ʒr�̒����ΏۂƂ��ď��������߂ɐ��������̂Ǝv����B
�@
�\�W�@�C�ꐫ��ʖʐ�*�i�T���S�ʊC��j
| ���� |
�C�於 |
�C�@�@��@�@���@�@�� |
���v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ������ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*1/10,000��Ɛ}��ő���
�@
�Ȃ��A��Q��̒����n�ŁA���������{���Ȃ�������Ȓ����n�͈ɍ]���ƈ������ŁA���̃T���S�ʖʐς͑�Q��̒������ʂɂ���974ha�ł���B
�����Ŕ��������ʒr���̃T���S�Q�W�̖ʐς͖�34,190ha�ŁA�T���S�ʒ�̐���i�{�����ł̓J���[�ʐ^���ǂ݂Ƃ����j���ő�̖ʐϔ䗦�i35.6%�j���߂Ă���B�C��ʂł͔��d�R�����C�悪�ő�Ŗ�19,230ha�A�����ʼn���C��̖�7,050ha�ł���B���������C��͒n�`�I�ɃT���S�Q�W�̐���ɕs�K�Ȓ�������̖ʐς�54.7%�ƃT���S�ʂ̔����ȏ���߁A�T���S�Q�W�̖ʐς͑��ΓI�ɏ������B�t�ɔ��d�R�����C��͊��o����ʐς͏������T���S���z�ʐς���49.2%���߁A���ΓI�ɑ傫���B
�@
�i�R�j�ʒr���ŃT���S��
�@
��Q���i1978�N�j��A��ɖ��ߗ��ē��ɂ��1506.7ha�̃T���S�ʂ����ł����i�\�X�j�B����C�悪�ő�ŁA1224.0ha�ɒB���A���C��̃T���S�ʂ�4.4%���߂�B
�Ȃ��A�����ő�Q���i1978�j�ȑO�ɏ��ł����T���S�ʂ��V����327.7ha���ꂽ�B�܂��A���ŔN��s���̂��̂�474.5ha���ꂽ�B�e�C��Ƃ���ȏ��Ō����͍`�p��s�s�p�n�����̂��߂̖����ł���B���̑��q�H�┑�n�̂��߂̟��ւɂ����ł��A�݂��Ă���B����ɂ����ł͊m�F����Ȃ������i�\10�j�B
��ȏ��Ŏ���Ƃ��ẮA�����哇�}�����̐V������`�ɂ����̂≫��{�������s�̓s�s�p�n�ɂ����́A��u��s�̍`�p�ɂ����̂Ȃǂ���������i�\11�j�B
�@
�\�X�@�T���S�ʏ��ŔN��ʖʐρi�T���S�ʊC��j
| ���� |
�C�於 |
���@�Ł@���@�� |
1979�`92���v |
���v |
| �`1978* |
1979�`80 |
1981�`83 |
1984�`86 |
1987�`89 |
1990�`92 |
�s�� |
| ������ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
���v |
327.7 |
36.2 |
595.9 |
189.2 |
528.8 |
156.6 |
474.5 |
1506.7 |
2308.9 |
| *�����ŐV���ɖ��炩�ɂȂ����i��Q���ł͌v�コ��Ă��Ȃ��j���ŖʐρA����āA1978�N�ȑO�̏��Ŗʐς̂��ׂĂ�\���������̂ł͂Ȃ��B |
�@
�\10�@�T���S�ʏ��Ō����ʖʐρi�T���S�ʊC��j
| ���� |
�C�於 |
���� |
���� |
���� |
���̑��E�s�� |
���v |
| ������ |
|
|
|
|
|
|
| ���� |
|
|
|
|
|
|
| �@ |
���v |
2165.8 |
0.0 |
123.9 |
19.3 |
2308.9 |
| �����̏ꍇ�͂P.�����A�Q.����A�R.���ցA�S.���̑��E�s���̏��ɗ��R���\�����ďW�v�B�i��:�P,�R,�S�̏ꍇ�A�P.�����ŏW�v�j |
�@
�\11�@��ȏ��Ŏ���i�T���S�ʊC��j
| ���@�� |
�C�@��@�� |
���@�Ł@���@�� |
| ������ |
�������� |
| �}���� |
�V������` |
100.5ha�i1985�N�j |
|
| ���� |
|
| �����s |
�s�s�J�� |
532ha�i1982�N�j |
| ����s�A��u��s |
�`�p |
242ha�i1988�N���_*�j |
| ���ǎs |
�`�p |
�@41ha�i1991�N���_*�j |
| �Ί_�s |
�Ί_�` |
97ha�i1991�N���_*�j |
|
|
�N�͍H�������N�B*�ɂ��Ă͍H���p�����B |
�@
�i�S�j�ʒr�ɂ�����T���S�Q�W�̕��z��
�@
�T���S�Q�W�̕��z���34,190ha�̓����\12�Ɏ����B�C��ʂɂ͋{�×�1,957.1ha�Ə��Ȃ��A����������5,951.1ha�A�����7,046.4ha�A���d�R������19,231.5ha�ƍő�̖ʐς��߂�B��x�ʂł͔�x�{�i�T%�����j���ł�����61.3%���߂�A�����Ŕ�xI�y��II��30.6%�ŁA��xIII�AIV�̍���x���8.2%�ɂ������A�킪���̃T���S�ʂł͒��x�̃T���S�Q�W���L����ʐς����|�I�ɑ������Ƃ��킩��B�C��ʂł͉���Œ��x�C�悪�����A71.8%��5%�����̔�x�̃T���S�Q�W���z��ƂȂ��Ă���B�{�×�64.9%�A���d�R������64.5%��5%�����̕��z��͂قړ����x�ł��邪�A�t�ɔ�xIII�AIV�̍���x�̖ʐς͉�������9.2%�A�{�×�11.6%�A���d�R����8.5%�ł���B����������5%�����̔�x���z�悪37.0%�Ə��Ȃ��A���ΓI�ɔ�x�̍����T���S�Q�W�̑����C��ł���B�ȉ��Ɋe�n��ʂɃT���S�̕��z���L���B
�@
�\12�@��x�ʃT���S�Q�W�ʐρi�T���S�ʊC��j
| ���@�� |
�C �� �� |
��@�@�@�@�x |
���@�v |
| �{ |
I |
II |
III |
IV |
| ������ |
�g�J���� |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���@�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ��x |
�{:5%���� |
|
I:5�`25% |
|
II:25�`50% |
|
III:50�`75% |
|
IV:75�`100% |
�@�@
�P�g�J����
�g�J���C��͏��ȓ�ŃT���S�ʂ����m�ɂȂ�A���S���Ɋ��o�ʌ����m�F�ł���悤�ɂȂ�B�������A�ʒr�͖����B�ł���A�ʒr���̃T���S�Q�W�͂܂������m�F�ł��Ȃ��B
�@
�Q�����哇�y�ъ�E���i�}�T�j
��E���͑S���قڔ�xI�ł��邪�A�n�`�I�Ɋ��o�ʌ����啔�����߁A�T���S�Q�W�̍L����͏������B�����哇�ł͊}���p���͔�x�{���L����B����x�C��̍L����n�_�͖k���ł͊}�����p���Ŏ}��~�h���C�VAcropora�A�R�����T���SMontipora�𒆐S�Ƃ����xIII�̌Q�W��46.9ha����B���ɗ������̊}���p���Ƀ~�h���C�VAcropora�A�R���T���SMontipora�𒆐S�Ƃ��A�A�i�T���S���h�LMillepora�A�n�i���T�C�T���SPocillopora�A�g�Q�T���Sseriatopora�A�V���E�K�T���SStylopora������̃T���S��xIII�AIV�Q�W��43.3ha���z����B
���V�i�C���ł͖����s���q��Ɏ}��̃~�h���C�VAcropora�A�t��R�����T���SMontipora�������x�ɕ��z����C�悪����B�A�i�T���S���h�LMillepora�A�p���I�N�T�r���C�VHeliofungia
�A�N�T�r���C�VFungia�����܂߁A��xIII�AIV�̌Q�W��75.7ha���z����B��a����I�A�u�ˊ��Ɏ}��~�h���C�VAcropora�A�핢��R�����T���SMontipora�̔�xIII�̌Q�W��34.2ha����B
�암�ł͐ߎq�ɑ��A�}��~�h���C�VAcropora�𒆐S�ɔ�xIII�̌Q�W��39.8ha����B���˓����݂ɂ͏��ʐςł��邪�A�_�X�Ǝ}��~�h���C�VAcropora�̍���x�T���S�Q�W�����z����B
�@
�R���V���i�}�U�j
���̐��݂͒f�R��n�`��悵�A�ʂ̔��B�����ɕn��ł���B�T���S�ʂ͓��݂𒆐S�Ɍ����A���o�ʌ����L���A�T���S�Q�W�̕��z�͂��܂�L���Ȃ����A�����̔�x��I�AII����ŁA�}��~�h���C�VAcropora�A�R�����T���SMontipora�𒆐S�ɑ��~�h���C�VAcropora��������B��xIII�AIV�͎R�̕t�߂ɂ킸���Ɍ����邾���ł���B��x�{������قǑ����Ȃ��B
�@
�S���i�Ǖ����i�}�U�j
���V���Ɠ��l�T���S�ʂ̔��B�͕n��ł��邪�A�S�����Ƃ�܂��Ă���B���o�ʌ��̖ʐς��傫���A�T���S�Q�W�̖ʐς͑傫���Ȃ��B��xIII�AIV�̌Q�W�݂͂�ꂸ�A��x�{�������Ȃ��B�قƂ�ǔ�xI�AII�ŁA�}��~�h���C�VAcropora�A�R�����T���SMontipora�Ƒ��~�h���C�VAcropora�̌Q�W�ł���B�A���A���~�h���C�VAcropora���z��͏ʉ��ł���B
�@
�T�^�_���i�}�V�j
�����Q���ł͍ő�̏ʒr��L����B���Ă͎}��~�h���C�VAcropora�̌Q�W���L�����Ă����Ǝv���邪�A�������_�ł͖����ɉ͕s�ǂł���B�k�݂̎���ɔ�xIV�̎}��~�h���C�VAcropora�@35.2ha�̕��z�������邪�A�S���P�l�𒆐S�Ƃ��Ĕ�x�{�̏ꏊ��776.8ha����A����͗^�_���̃T���S�Q�W1,121.4ha��69.2%���߂�B�S���P�l�͉��̃n�}�T���SPorites���_�݂���B
�@
�U����{���y�ѕt�����i�}�V�A�W�j
����{�����݂ł͔�xIII�AIV�̑傫�ȃT���S�Q�W�͂قƂ�nj���ꂸ�A�唼�͔�x�{�y��I�̌Q�W�ł���B����{�����݂Ɍ����Ă����Β��������T���S�Q�W�ʐ�6229.0ha�̂����A��xIII�AIV�̌Q�W�̖ʐς�1.8%�ɉ߂����A��x�{�̃T���S�Q�W�ʐς�76.3%���߂�B��xI�̖ʐς�19.8%�Ŗ{�������A���[�C�݂Ȃǂɕ��z����B�킸���ɖk���̍�������@�É��ɑ��~�h���C�VAcropora(���a�Pm�O��j�𒆐S�Ɏ}��~�h���C�VAcropora�A�n�i���T�C�T���SPocillopora�̔�xIII�̌Q�W��71ha���݂���B���̌Q�W�̓��]�[�g�̊ό������Ƃ����p����Ă���B
�@
�V����{�����ӗ����i�}�V�A�X�j
����{���ɔ�ׁA���ӗ����̃T���S�ʂɂ�����T���S�Q�W�̏͂��Ȃ�ǂ��B�ɕ������ł̓T���S�Q�W�ʐ�272.5ha�̂����A��xIII�AIV�̖ʐς�68.3%��߁A��x�{�̖ʐς�14.2%�ɂ����Ȃ��B���̎��͂͂قڑS��ɂ킽��A����x�̎}��~�h���C�VAcropora��R�����T���SMontipora�����z���A�����̋�u�쓇�ɒ��x�̌Q�W���܂Ƃ܂��Ă݂��邾���ł���B�c�NJԗ̓T���S�ʒn�`���ʒr���`������ꏊ�����Ȃ��A���o�ʌ��������B�ʒr�̃T���S�Q�W��66.4ha�ɂ����Ȃ����A�ʉ����ɂ݂͂��Ƃȑ��~�h���C�VAcropora�̍���x�Q�W�����z���Ă���B
�n���쓇�ł���x�{�̃T���S�Q�W��͕��z�����A�T���S�Q�W�̖ʐ�105ha�̂����A��xI�AII��71.4%�AIII�AIV��28.6%���߁A�ʒr���Ɏ}��n�R�T���Sporites�A�R�����T���SMontipora����Ƃ���Q�W�����z����B
�v�ē��͊��o�ʌ����������z���A�ʒr�n�`�͂��܂�݂��Ȃ��B�������t�߂Ɏ}��R�����T���SMontipora�̔�xIII�AIV�̌Q�W41ha���݂��邪�A�傫�Ȗʐς��߂�̂͌�_���ɉ��т�ʂŁA256ha�̃T���S�Q�W�����݂���B����������x�̌Q�W�͂Ȃ��A78%�͔�x�{�̎}��~�h���C�VAcropora�ŁA22%����xI�AII�̎}��R�����T���SMontipora�A�~�h���C�VAcropora�ł���B
�@
�W�{�×y�є��d�����i�}10�j
�����ł́A�r�ԓ��k���̔��d�����������͈͂Ɋ܂߂��Ă���i���d�����͒n�`�}��ɕ\������Ă��Ȃ����ߕX��A�r�ԓ��̋敪�ɉ������Ă���j�B�����ł̃T���S�ʈ�ʐς�976.8ha�����肳��Ă��邪�A84.7%�͊��o����ŁA�T���S�Q�W�ʐς�5.9%�ɂ����Ȃ��B�T���S�Q�W�ʐς̔�x�ʓ����59.3%����x�{�ŁA��xIII�AIV��11.3%�i�}��~�h���C�VAcropora)�ł���B
�{�Ó����ӂŔ�xIII�AIV�̃T���S�Q�W�̍L���肪�݂���̂́A�����������̓����C��Ŏ}��̃~�h���C�VAcropora�ƃR�����T���SMontipora�Q�W����40ha���z����B���͂قƂ�ǔ�x�{�̌Q�W��ł���B
�ɗǕ������ӂ���x�͒Ⴍ�A96.3%����x+�̎}��~�h���C�VAcropora�Q�W��ł���B����A�����̑��NJԓ��A���[���ł͏͗ǍD�ŁA�T���S�Q�W�ʐ�227ha�̂���61.2%����xIII�AIV�̎}��~�h���C�VAcropora�A�R�����T���SMontipora����Ƃ���Q�W�ŁA��x�{�̖ʐς�13.7%�ɂ����Ȃ��B
�@
�X���d�R�i�Ί_���A���\���j�i�}11�j
�Ί_���y�ѐ��\���ł͔�x�{�̖ʐς����|�I�ɑ����B�}��̃T���S���I���͐ς��������A�~�W�O�T�ނ�n�C�I�I�M���̏��^�C�����D�肷��C���Q���ƂȂ��Ă���C�悪�قƂ�ǂł���B��r�I�L���ʐςŔ�xIII�AIV�̃T���S�Q�W��������͔̂��ۂł���B���ۊC��ł͖�100ha�̎}��R�����T���SMontipora����Ƃ���T���S�Q�W�����z���鑼�A�A�I�T���SHeliopora
coeralea�̑�Q�����݂���B�약�ɂ�53ha�̔�xIII�AIV�̎}��R�����T���SMontipora�A�n�}�T���SPorites����Ƃ���Q�W�����z����B
�@
�P�O�ΐ��ʌi�}11�j
�ΐ��ʌi�n�`�}�敪�ł͔��d�R�C�撆�̒|�x���A���l���A�����Ɋ܂܂��j�̃T���S�Q�W�ʐς͖�13,OOOha�ł���B�����A��x�{�̖ʐϔ䗦��53.7%�A��xI�AII�̖ʐϔ䗦��36.4%�A��xIII�AIV�̖ʐϔ䗦��9.9%�ł���B
����x�iIII�AIV�j�̃T���S�Q�W�͏��l���̖k�����瓌���ɂ����Ă݂���}��~�h���C�V�Q�W�Ŗʐ�962ha�ł���B���̌Q�W�́A1978�N���唭�������I�j�q�g�f�̐H�Q���܂ʂ��ꂽ���̂ŁA�ߔN����ɕ��z����g�債����B�ΐ��ʌł̓T���S�Q�W�͉̓r��ɂ���B
�@
�}�T�@�T���S��x���z�}�i�����哇�j
�}�U�@�T���S��x���z�}�i���V���E���i�Ǖ����j
�}�V�@�T���S��x���z�}�i�^�_���E����k���j
�}�W�@�T���S��x���z�}�i����암�j
�}�X�@�T���S��x���z�}�i����{�����ӗ����j
�}10�@�T���S��x���z�}�i�{�×j
�}11�@�T���S��x���z�}�i���d�R�j
�@
�i�T�j�ʉ����ɂ�����T���S�Q�W�̕��z��
�@
������}���^�@�Œ��������g�q���A�ʉ����̃T���S�Q�W�̔�x�Ɛ���^�y�є�Q���ώ@�������ʂł���B�ʉ����̒n�`�͏ꏊ�ɂ��X���ω����邽�߁A�ώ@�͈͂̕����ω����A�܂��������̊C�ۂɂ��q�����[�g���ω�����̂ŁA�ώ@���ʂ͏ʉ������̏ꏊ�Ƃ��Ē�߂�����̂���ʉ�����\�������̂ł���B
�C��ʂɏW�v�������ʁi�\13�j�ɂ��A�S���������͖�1,300km�ɒB����B��x�ʂł�I�AII��52.0%�ƍł������A�ʒr����x�{�����|�I�ɑ����̂ƌ��ʂ��قɂ���B��x�{��36.0%�AIII�AIV��12.0%�ł���B�C��ʂł͉���ȊO�̊C��͔�xI�AII���ő�̔䗦���߂邪�A����݂̂���x�{��46.2%�ƍő�̔䗦�������B����C��ł͏ʒr�݂̂Ȃ炸�A�ʉ�����x�̒Ⴂ���Ƃ��킩��B����͉���{���C�݈�̏ʉ��̃T���S��x���Ⴂ���Ƃ��������̂ŁA����C��̎��ӗ����ł͗l�q�͈قȂ�B�C��̒��Ŕ�xIII�AIV�̊����������Ȃ�͔̂��d�R��15.9%���߂Ă���B�e�n��ʂ̏��ȉ��ɋL���B
�\13�@�ʉ��T���S��x�ʕ��z�W�v�\*�i�T���S�ʊC��j
| ���� |
�C�於 |
�� �@�@�x |
�v |
| �{ |
I,II |
III,IV |
| ������ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���@�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@
�P�g�J����
���y�ѕ̑S��������19km�̂����A83.2%����xI�AII�ł���B�S�ʓI�ɏʂ̔��B�͕s�\���ł���B���ΓI�ɂ͐��ݑ��Ŕ�x�����������B
�@
�Q�����哇�y�ъ�E��
��E���S��������36.9km��87.3%�͔�xI�AII�ł���B�哇�{���ł͑S����146.5km�̂���49.8%����xI�AII�ŁA45.1%����x�{�A��xIII�AIV��5.1%�ł���B���݂Ɛ��݂��ׂĂ݂�Ɠ��݂̕�����x�{�����Ȃ��i38.9%�ɑ�����49.1%�j�A��xIII�AIV�������i8.4%�ɑ�����2.9%�j�B���v�C�������̗����ł͑哇�{������xIII�AIV�̔䗦������20.5%�ŁA��x�{���Ⴍ28.4%�������Ă���B
�@
�R���V��
�S��������75.2km�̂����A��xI�AII��59.2%�ōő���߁A�����Ŕ�x�{��35.6%�ŁA��xIII�AIV��5.2%�ł���B���݂Ɛ��݂��ׂĂ݂�ƁA�����哇�Ɠ��l�ɐ��݂������݂ɔ�x�̍����X�����݂���B���Ȃ킿�A���݂ł͔�x�{��25.3%�ɑ��A���݂ł�52.2%�A��xIII�AIV�����݂ł�7.3%�ɑ����݂ł�1.7%�ł���B
�@
�S���i�Ǖ���
�S��������50.6km�ŁA��xIII�AIV�݂͂�ꂸ�A��x�{��I�AII���قڔ�����B
�@
�T�^�_��
�ʉ��͖̉����[���ł͂Ȃ��A��xIII�AIV��0.5%�ɂ����߂����A��xI�AII��73.1%���߂�B
�@
�U����{���y�ѕt�����i����A���[���j
�S��������292.6km�̂����A��x�{��66.7%���߂�B��xIII�AIV��5.8%�ł���B���̓��݂Ɛ��݂��ׂ�ƁA��x�{�͓���64.2%�A����68.4%�A��xI�AII�͓���28.1%�A����27.0%�A��xIII�AIV�͓���7.7%�A����4.5%�Ƒ卷�Ȃ��B
��r�I��x�̍������z���݂���̂́A�ӓy�������A�{�������k���A�쉮���������ł���B���̂����ӓy�������A�{�������k���̊C��̓I�j�q�g�f�̊ώ@�n�_�������B���ɖ{�������k���ł̓I�j�q�g�f�̖��x�������A�[���ɉ������T���S�Q�W�ɂ͂�����Ƃ����H�Q�̂��߂ɂł��������̑O�����ł��Ă���A�������Đi�s���ł������B���̑��ÉF�������ӁA����암�A���[���A���[�C�݁A�ߔe��`���A�����s�����n���ŃI�j�q�g�f�̊ώ@�n�_�����������B
�@
�V����{�����ӗ���
�ɕ������͏ʒr�݂̂Ȃ炸�A�ʉ����T���S�̕��z�͗ǍD�őS��������39.2km�̂����A��xIII�AIV��45.7%���߁A�t�ɔ�x�{��5.9%�ɂ����������A����{���Ɨl�q���S���قȂ�B�ɕ������암�ŃI�j�q�g�f�̊ώ@�n�_�������݂�ꂽ�B�c�NJԏ������ǍD�ŁA�S����73.5km�̂����A31.7%����xIII�AIV�Ŕ�x�{��10.3%�ł���B���ɍ��Ԗ����k�݂Ŕ��B�������~�h���C�VAcropora�Q�W���݂邱�Ƃ��ł���B�������A�I�j�q�g�f�̍����x�ȕ��z�����C��Ɠn�Õ~���k���݂Ŋώ@���ꂽ�B�n���쓇��81.0%����xI�AII�ł���B�v�ē���87.9%����xI�AII�ł���B�A���A�v�ē��k�݂͑S����������Ă��Ȃ��B
�@
�W�{�×y�є��d����
�{�Ó��k���̃T���S�ʑє��d�����i�n�`�}�敪�ł͒r�ԓ��Ɋ܂߂��j�͔�xI�AII��64.4%�ő唼���߁A��xIII�AIV��16.1%�ł���B�{�Ó��i�ɗǕ������܂ށj�ł́A��xI�AII��74.7%���߁A�c����x�{�Ɣ�xI�AII�Ŕ����ĕ����Ă���B
�{�Ó������̑��NJԓ��y�ѐ��[���ł͏ʒr�̃T���S��x����r�I�ǍD�Ȃ̂ɑ��A�ʉ��͂���قǂł��Ȃ��A�{�Ó�������x�{�̔䗦�͍����i27.9%�j�A�ő�͔�xI�AII��58.8%�ł���B
�@
�X���d�R��
�Ί_���ł͑S��������92.4km�̂����A�ő�䗦���߂�͔̂�xI�AII��57.8%�ŁA�����Ŕ�x�{��25.9%�ł���B��xIII�AIV��16.3%�ł���B
���̓����ł݂Ă݂�ƁA�Ί_���ł����݂̕����ǍD�ł���B���Ȃ킿�A��xIII�AIV�̔䗦�͐���8.5%�ɑ��A����28.2%�A��x�{�̔䗦������40.7%�ɑ��A����3.5%�ƑΏ̓I�ł���B���l���k�݂ɍ���x�̑��~�h���C�VAcropora�Q�W�����z����B���\���i���ԓ����܂ށj�́A�Ί_���Ƃقړ����x�Ŕ�xI�AII��59.6%�A��x�{��26.0%�A��xIII�AIV��14.4%�ł���B�^�ߍ����A�g�Ɗԓ��͔�xIII�AIV�͊e�X7.9%�A13.7%�ł���B��x�{��I�AII�����͂���B
�@
�P�O�ΐ��ʌ�
�ΐ��ʌi�n�`�}�敪�ł͔��d�R�C�撆�̒|�x���A���l�����i���������A�����Ɋ܂܂��j�̓�y�іk�݂ł͔�xIII�AIV�̔䗦�͔�r�I����25.8%���߂�B��x�{��16.4%�ł���B
�@
�@
(�U)���}���Q���̃T���S�Q�W
�@
���}���Q���ɂ��T���S�ʂ͕��z����B�������A���̌`�Ԃ̓G�v�����ʂƌĂ�鏬�K�͂Ȃ��̂ł���A�ʒr�������B
���̂��߁A�ʒr���J���[�ʐ^��͂ɂ�蒲������Ƃ������@���Ƃ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ŃT���S�ʈ�ł���Ȃ���A�X�I�ɔ�T���S�ʊC��̒�����@�ł���A�������Ɗ������������ɂ��ƂÂ��}���^�@�y�ђ����撲�������݂��킹�����n�����̕��@��K�p�����B�������A�����̌��ʂ̓T���S�ʊC��Ɋ܂܂��ׂ����̂ł���̂ŁA�ʂɍ��𗧂ĂċL�����ƂƂ���B����͉ΎR�C��ɂ��Ă͒������s�Ȃ��Ȃ������B
�������s�����̂��ۓ��A�����y�ѕ�ŁA�\14�Ɏ����ʂ�456ha�̃T���S�Q�W���L�^���ꂽ�B
�@
�\14�@��x�ʃT���S�Q�W�ʐρi���}���Q���C��j
| ��@�x |
I |
II |
III |
IV |
�v |
| �ʁ@�� |
170 |
151 |
120 |
15 |
456 |
| % |
37.3 |
33.1 |
26.3 |
3.3 |
100 |
| �Q�W�� |
34 |
16 |
5 |
1 |
56 |
| ���ϖʐ� |
5.0 |
9.4 |
24 |
15 |
�@ |
�@
�ʐϔ�ł͖�70%����xI�AII�ł���B�������A����x�̌Q�W�͈�Q�W�̖ʐς��傫���B
�����s�̕ɂ��A�Q�W�͂قƂ�ǂ̂��̂������̐���^�̃T���S����\������Ă���B�e����^�̖ʐς͎�����Ă��Ȃ�������핢��̐���^�����������Ă���B�����Ɏ����ŁA���A�}��Ȃǂ̐���^���n�߁A���̐���^���݂��Ă���A���l�Ȑ���^�����݂����C���i�ς��`������Ă���B�������A�C�ݐ��̑傫���p�����������̓p���ɂ́A��r�I�K�͂̑傫�Ȏ}��~�h���C�V�̌Q���������Ă���A���}���Q���ł͓��قȊC���i�ς��`�����Ă���B
���}���Q���͑�m���ɓ_�݂��鏬�����Q�ŁA�C�݂����ڊO�m�ɖʂ��鏊�������܂����݊��ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��������Ȃ����߁A�T���S�̐������͋ɂ߂ėǍD�ł���B�܂��A�T���S�ʋ��ɑ��鋙�l�����Ⴂ���߁A���ނ͖L�x�ł���킪���ł͑��ɗ�����Ȃ��ǍD�ȊC���i�ς�悷��C��ƂȂ��Ă���B
���ŃT���S�Q�W�͕\15�Ɏ������Q�P���A���v�Tha������Ă��邪�A��������l�דI�v���ɋN��������̂ł���B
�@
�\15�@���ŃT���S�ʖʐρi���}���Q���C��j
| �s������ |
���Ŗʐ� |
���Ŏ��� |
���ŗ��R |
|
|
|
|
|
�@
�܂��A�����s�̒������ʂł́A�H�Q�����ɂ���Q�͑S������Ă��炸�A�e�T���S�Q�W�͐l�דI�ȉe������n��������Ό��S�ȏ�Ԃɕۂ���Ă���悤�ł���B
�@
���p����
�����B�Y�@1980�@�T���S�ʂ̔��n�`�\��.�n��25�i�W�j:34-42.
���m�q�Ɗ�����Ё@1980�@��Q�R���ۑS��b����.�C�撲����.�C�ݒ���
; �����E����E�T���S�ʕ��z�����A�C��������A�S����319pp.
�ڎ���
�@
1�C�������Z���^�[
�@
�@
�@