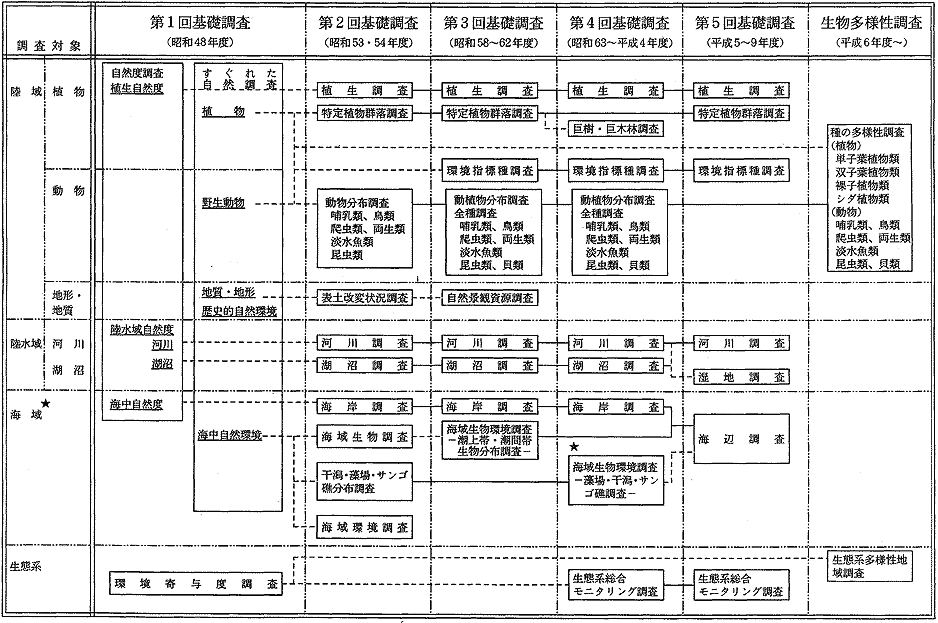
I. 序
1.自然環境保全基礎調査の概要
(1)自然環境保全基礎調査とは
|
自然環境保全基礎調査は、全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備するために、環境庁が昭和48年度より自然環境保全法第4条の規定に基づき概ね5年毎に実施している調査である。 |
■自然環境保全法第4条
|
国はおおむね5年ごとに地形、地質、植生及び野性動物に関する調査、その他自然環境保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。 |
|
一般に、「緑の国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域等の各々の領域について調査項目を分類し国土全体の状況を調査している。 調査結果は報告書及び地図等にとりまとめられたうえ公表されており、これらの報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計画をはじめとする自然保護行政の他、環境アセスメント等の各方面において活用されている。 |
(2)自然環境保全基礎調査の歩み
| 第1回〜第5回の調査骨子は図1のとおりである。 第1回基礎調査は昭和48年度に実施され、その結果は49・50年度の2ケ年にわたり公表された。 それまで、基礎的な自然保護のための調査は全国レベルでは実施されていなかったなかで、第1回の基礎調査を実施するにあたりまず考えられた目的は、科学的な視点に立った調査を実施することによって国土にある自然の現況をできるだけ正確に総合的に把握し、守るべき自然、復元・育成・整備すべき自然は何かということを明らかにし、全国的な観点に立った自然保護行政を推進するための基礎資料を整備することであった。 第1回基礎調査は全国的なレベルの自然環境保全のための基礎的な調査としてははじめてのものであり、さらに急激な国土の改変がすすむなかで、保護施策を講ずるべき貴重な自然がどこにあるのかを早急に明らかにする必要に迫られていたことから、対象を限定した調査が中心となった。 これに対し、第2回基礎調査では基礎的な情報の収集を5年おきに繰り返し実施するというこの調査の性格をより明確にし、自然環境に関する網羅的、かつ客観的な基礎的情報の収集に主眼をおいて調査を計画、実施した。ただし、短期間に全国土とその周辺海域にわたって多様な生物環境や地形・地質的環境のすべてを調査・記録し、それらを集計・解析して、わが国の自然環境の実態を把握することは困難である。このため、行政上の必要性と調査の実行可能性とを考慮して以下の5点に目標を絞り、合計14項目の調査を昭和53・54年度の2ケ年で実施した。その後、55〜57年度にデータの点検及び集計解析を行い公表した。 |
| 1 | 自然保護上重要な動植物に関する選定及び評価基準を定め、それに基づいた動植物リストを作成し、リストアップされた動植物の生息地と生息状況について把握する。 |
| 2 | 自然環境の基本情報図として、縮図5万分の1の植生図(全国の約2分の1の地域について)を整備する。 |
| 3 | 広域に生息する大型野性動物の分布状況を把握する。 |
| 4 | 海岸、河川、湖沼の自然環境がどの程度人為的に改変されているかについて把握し、これらのうち、人為的に改変されていない自然状態のままの地域をリストアップする。 |
| 5 | 以上の諸情報を体系的・総合的に整理し、これらのデータを行政機関だけでなく、国民一般が広く利用できるように公開する。 |
|
第3回基礎調査では、第2回基礎調査の内容を基本的には踏襲し、自然環境に関する客観的、網羅的な情報収集を調査対象を拡大して続けるとともに、第2回基礎調査以後の変化の状況を把握することを目的に昭和58〜62年度に実施し、昭和63年度に総合とりまとめを行った。第2回と異なる点は動物の分布調査の対象を主要分類群の全種に拡大したこと(動植物分布調査(全種調査))、一般国民のボランティア参加による調査を導入し居住地周辺部の身近な自然の現状についての調査を行ったこと(動植物分布調査(環境指標種調査))、景観の骨格を成す地形に着目した自然景観についての調査を行ったこと(自然景観資源調査)等である。 続いて昭和63年度より開始した第4回基礎調査においても基本的には第3回基礎調査と同様に客観的、網羅的な情報の収集及び前回調査以後の変化状況の把握を目的として実施している。第4回基礎調査でこれまでと内容を異にしているのは巨樹・巨木林の分布等の調査を実施したこと(巨樹・巨木林調査)、河川調査の対象河川を変更したこと、生態系の系全体の動態をモニタリングし自然現象あるいは人的影響を捉えるための調査(生態系総合モニタリング調査)を開始したことなどである。第4回基礎調査は平成4年度までに調査を終了、5・6年度にとりまとめを行う予定となっている。 なお、第5回基礎調査は、平成5年度より開始し、植物分布調査、湿地調査、海辺調査を追加して実施する。さらに平成6年度より生物多様性調査を新たに開始する予定である。 |
図1 自然環境保全基礎調査骨子一覧
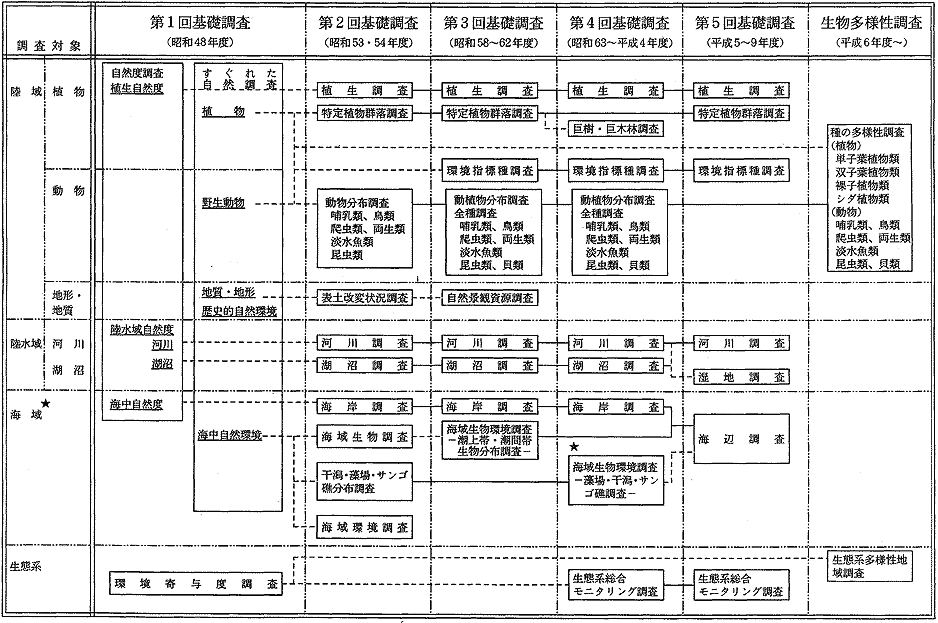
2.干潟・藻場・サンゴ礁調査について
(1)はじめに
| 海域に関する調査は図1に示した通り第1回から実施されているが、干潟・藻場・サンゴ礁調査は第2回と今回(第4回)実施された。今回は海域生物環境調査(干潟・藻場・サンゴ礁の分布に関する調査)と題して平成元年度から4ケ年で行われた(表1)。 干潟・藻場・サンゴ礁は、沿岸の浅海域に広く分布する重要な生物の生息地である。干潟とは一般に干潮時に干出する平坦な砂泥質堆積域をいうが、魚貝類等の小動物からシギやチドリ類など渡り烏の生息地として重要である。また、水質の浄化作用も忘れることのできない機能である。 藻場は固い岩礁底に分布するホンダワラ類やアラメ、カジメ等の群落と砂泥底に分布する顕花植物群落に大別されるが、いずれも一次生産の場として重要であるばかりでなく、多くの動物のすみかとしても機能している。 サンゴ礁は本調査では主に造礁サンゴ群集の分布把握を意図している。造礁サンゴ類の分布は北は太平洋岸では千葉県、日本海岸では新潟県までが知られているが、サンゴ礁が形成されているのは吐■喇列島までとされている。サンゴ群集は藻場と同様に他の小動物のすみかとなっている。また、サンゴ礁は極めて多様な生物群集がみられることで知られており、重要な生息地である。 本調査はこのような貴重な存在である干潟、藻場、サンゴ礁について、分布状況や消滅状況を把握する目的で実施された。 なお、調査手法は自然環境保全基礎調査検討会の海域生物環境分科会で検討された。 |
海域生物環境分科会
稲葉 明彦 比治山女子短期大学副学長
内田 紘臣 串本海中公園センター取締役学術部長
菊池 泰二 九州大学理学部附属天草臨海実験所教授
有馬 郷司 水産庁南西海区水産研究所藻類増殖研究室長
中尾 繁 北海道大学水産学部教授
風呂田利夫 東邦大学理学部海洋生物学研究室講師
山口 正士 琉球大学理学部海洋学科教授
(2)調査の内容
a.干潟
|
日本沿岸全域の干潟の存在する海域(39都道府県)を対象とし、平成元年度から3ケ年にわたり実施された。 現存する干潟については、分布域の位置、範囲、面積、タイプ及び底質についての調査をした(干潟分布調査)。また、第2回調査地区と今回調査地区との比較対照を行い、消滅干潟については消滅域の位置、範囲、面積及び消滅時期についても記録を取った(干潟改変状況調査)。さらに各県の現存干潟から代表的な干潟を選定し、底生生物を中心とした現地調査を行い、その特徴を把握した(干潟生物調査)。 調査は各都道府県に委託し、既存の調査報告書、その他最新の資料による資料調査及びヒアリング調査を実施し、必要に応じて現地確認調査を行い、資料情報の重複を整理するとともに精度を高めた。 |
なお、調査対象干潟は次の通りである。
|
* |
干潟分布調査(現存干潟) |
|
1 |
高潮線と低潮線に挟まれた干出域の最大幅が100m以上であること。 |
|
2 |
大潮時の連続した干出域の面積が1ha以上であること。 |
|
3 |
移動しやすい底質(砂、礫、砂泥、泥)であること。 |
|
* |
干潟改変状況調査(消滅干潟) 昭和53年以降、埋立、浚渫その他の改変により消滅した干潟で、次の全ての要件に合致するもの。 |
|
1 |
昭和53年において存在した干潟であること。なお、前回調査に記載されている干潟であっても、上記の定義に該当しないものは存在したものとはみなさない。 |
|
2 |
消滅面積が1ha以上であること。埋立等の事業区域が1ha以上あっても、干潟そのものの改変が1haに満たないものは消滅域には含めない。 |
b.藻場
| 日本沿岸全域の藻場の存在する海域(39都道府県)を対象とし、平成元年度から3ケ年にわたり実施された。 現存する藻場については分布域の位置及び範囲、面積、タイプを、また、消滅藻場については消滅域の位置及び範囲、面積について調査をした。 調査は各都道府県に委託し、既存の調査報告書その他最新の資料による資料調査及びヒアリング調査を実施し、また必要に応じて現地確認調査を行い、資料情報の重複を整理するとともに精度を高めた。 なお、今回の調査では資料情報の充実による新たな分布の把握、面積測定精度の向上等の影響が大きいことが予測されたため、前回調査結果と増加面積の比較については当初から調査項目に含めていない。 なお、調査対象藻場は次の通りである。 |
| * | 藻場分布調査(現存藻場) |
| 1 | 面積が1ha以上であること。 |
| 2 | 水深が20m以浅に分布すること。 |
|
* |
藻場消滅状況調査(消滅藻場) 昭和53年度以降消滅したと判断される藻場で、次の全ての要件に合致するもの。 なお、埋立、浚渫などの人工改変だけでなく、海況変化その他の要因による消滅域も含むものとするが、季節変動による一時的な消滅域は除くこと。 |
| 1 | 昭和53年時点で存在していた藻場であること。 |
| 2 | 消滅面積が1ha以上であること。 |
c.サンゴ礁
| 造礁サンゴの分布する沖縄、鹿児島、宮崎、熊本、大分、長崎、高知、愛媛、徳島、島根、和歌山、三重、静岡、神奈川、東京、千葉の16都県を対象に実施された。 調査はサンゴ礁海域(吐■喇列島小宝島以南)と非サンゴ礁海域(吐■喇列島悪石島以北)に分けて行われ、サンゴ礁海域では礁池はカラー空中写真の判読、礁縁は曳航観察(マンタ法)により、非サンゴ礁海域ではマンタ法及び調査区を設定し、造礁サンゴ群集の属レベルの生育型別被度、位置、面積を調査した。なお、東京都の小笠原諸島はサンゴ礁海域に属するが調査手法の便宜上本調査では非サンゴ礁海域として取り扱った。 また、非サンゴ礁海域では被度5%以上で面積0.1ha以上の群集を調査対象とした。 |
(3)調査の成果物
報告書は都道府県別に次の通り作成されている。
・干潟、藻場調査報告書(干潟分布調査及び干潟改変状況調査)
・干潟、藻場調査報告書(干潟生物調査)
・干潟、藻場調査報告書(藻場分布調査及び藻場消滅状況調査)
・干潟、藻場分布図帳
・サンゴ礁調査報告書
・サンゴ礁分布図、サンゴ礁現地調査記録図帳
都道府県別の作成状況は表2の通りである。
なお、第2回調査では次の通り作成されている。
・干潟、藻場、サンゴ礁分布調査報告書(都道府県別・39冊) 昭和54年発行
・海域調査報告書(全国版)
(海岸調査、海域環境調査、干潟・藻場・サンゴ礁分布調査)
昭和56年発行
表1 調査実施年度
| (数字は平成の年度) |
| コード | 都道府 県 名 |
干 潟 |
藻 場 |
サ ン ゴ 礁 |
| 1 | 北 海 道 | 3 | 3 | |
| 2 | 青 森 | 3 | 3 | |
| 3 | 岩 手 | 3 | 3 | |
| 4 | 宮 城 | 3 | 3 | |
| 5 | 秋 田 | 3 | ||
| 6 | 山 形 | 3 | ||
| 7 | 福 島 | 3 | 3 | |
| 8 | 茨 城 | 3 | 3 | |
| 9 | 栃 木 | |||
| 10 | 群 馬 | |||
| 11 | 埼 玉 | |||
| 12 | 千 葉 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 東 京 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 神 奈 川 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | 新 潟 | 3 | ||
| 16 | 富 山 | 2 | ||
| 17 | 石 川 | 2 | 2 | |
| 18 | 福 井 | 2 | ||
| 19 | 山 梨 | |||
| 20 | 長 野 | |||
| 21 | 岐 阜 | |||
| 22 | 静 岡 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | 愛 知 | 1 | 1 | |
| 24 | 三 重 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | 滋 賀 |
| コード | 都道府 県 名 |
干 潟 |
藻 場 |
サ ン ゴ 礁 |
| 26 | 京 都 | 2 | ||
| 27 | 大 阪 | 2 | 2 | |
| 28 | 兵 庫 | 2 | 2 | |
| 29 | 奈 良 | |||
| 30 | 和 歌 山 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | 鳥 取 | 2 | 2 | |
| 32 | 島 根 | 2 | 3 | |
| 33 | 岡 山 | 1 | 1 | |
| 34 | 広 島 | 2 | 2 | |
| 35 | 山 口 | 2 | 2 | |
| 36 | 徳 島 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 香 川 | 1 | 1 | |
| 38 | 愛 媛 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 高 知 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 福 岡 | 1 | 1 | |
| 41 | 佐 賀 | 1 | 1 | |
| 42 | 長 崎 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | 熊 本 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | 大 分 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | 宮 崎 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | 鹿 児 島 | 1 | 1 | 2.3.4 |
| 47 | 沖 縄 | 1 | 1 | 2.3.4 |
表2 調査の成果物
| 成果物 | 千 潟 報 告 書 |
干 潟 生 物 報 告 書 |
千 潟 ・ 藻 場 図 帳 |
藻 場 報 告 書 |
サ ン ゴ 礁 報 告 書 |
サ ン ゴ 礁 図 帳 |
|
| コード | 都道 府県 |
||||||
| 1 | 北 海 道 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 青 森 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 岩 手 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 宮 城 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | 秋 田 | 1 | 2 | ||||
| 6 | 山 形 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 福 島 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 茨 城 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 栃 木 | ||||||
| 10 | 群 馬 | ||||||
| 11 | 埼 玉 | ||||||
| 12 | 千 葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 東 京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 神 奈 川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 新 潟 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 富 山 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 石 川 | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | 福 井 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 山 梨 | ||||||
| 20 | 長 野 | ||||||
| 21 | 岐 阜 | ||||||
| 22 | 静 岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 愛 知 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | 三 重 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 滋 賀 | ||||||
| 成果物 | 千 潟 報 告 書 |
干 潟 生 物 報 告 書 |
千 潟 ・ 藻 場 図 帳 |
藻 場 報 告 書 |
サ ン ゴ 礁 報 告 書 |
サ ン ゴ 礁 図 帳 |
|
| コード | 都道 府県 |
||||||
| 26 | 京 都 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 大 阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | 兵 庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 奈 良 | ||||||
| 30 | 和 歌 山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 鳥 取 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | 島 根 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | 岡 山 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 34 | 広 島 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 35 | 山 口 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 36 | 徳 島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | 香 川 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | 愛 媛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | 高 知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 福 岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | 佐 賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 42 | 長 崎 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 43 | 熊 本 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 大 分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 宮 崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 鹿 児 島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 47 | 沖 縄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |