|
(参考図1−1 調査区の設定−現存干潟)
|
|
(参考図1−2 調査区の設定−消滅干潟)
|
付2. 第4回自然環境保全基礎調査
海域生物環境調査
干潟、藻場調査要項・実施要領
(抜 粋)
干潟・藻場調査要項
1 調査の目的
沿岸浅海域における重要な生物の生息環境である干潟・藻場の最新の分布状況及び前回調査以降(前回調査とは、昭和53年度に行なわれた第2回自然環境保全基礎調査干潟・藻場・サンゴ礁調査のことを言う。以下同)の消滅状況等を把握する。 また代表的な干潟について、底生生物相の概要、特徴を把握する。
2 調査実施者
国が都道府県に委託して実施する。
3 調査対象地域
日本沿岸全域とする。ただし干潟については分布県のみとする。
4 調査実施期間
平成元年度を初年度とする3ケ年計画で実施する。
5 調査内容
調査する事項は次の通りとする。
(1)干潟調査
1 干潟分布調査
現存する干潟について、以下の事項を調査する。
・分布域の位置・範囲
・面積
・干潟のタイプ
・底質
・その他
2 干潟改変状況調査
前回調査以降人工的改変によって消滅した干潟について、以下の事項を調査する。
・消滅域の位置及び範囲
・面積
・消滅時期
・その他
3 干潟生物調査
現存する干潟のうち代表的なものについて、以下の事項を調査する。
・環境の概況
・底生生物の生息状況
・鳥類の渡来状況
(2)藻場調査
1 藻場分布調査
現存する藻場について、以下の事項を調査する。
・分布域の位置及び範囲
・面積
・藻場のタイプ
・その他
2 藻場消滅状況調査
前回調査以降消滅した藻場について、以下の事項を調査する。
・消滅域の位置及び範囲
・面積
・その他
6 調査方法
・干潟分布調査、干潟改変状況調査、藻場調査分布調査及び藻場消滅状況調査については、基本的には前回調査の成果物、最新の空中写真、地形図、海図、既存の調査報告書その他の資料調査およびヒアリング調査により行なう。 また、必要に応じて現地確認調査を行なう。
・干潟生物調査については、原則として現地調査を実施し、また併せて資料調査、ヒアリング調査を行なう。
・各調査の調査方法の詳細は別紙1「干潟・藻場調査実施要領」による。
7 調査結果のとりまとめ
受託者は調査結果を下記の図表にとりまとめる。
(1)干潟分布調査および干潟改変状況調査
ア 干潟分布図
別紙1-1「干潟分布図」(略)にならい、現存干潟、消滅干潟の位置・範囲を1/50,000地形図上に図示する。
イ 現存干潟調査票・消滅干潟調査票
別紙1-2、別紙1-3にならい、現存干潟、消滅干潟の面積、タイプ、その他の項目について、各調査区ごとに「現存干潟調査票」または「消滅干潟調査票」にとりまとめる。
ウ 現存・消滅干潟一覧表
別紙1-4(略)にならい、現存干潟、消滅干潟の分布概要を「現存・消滅千潟一覧表」にとりまとめる。
エ 前回調査区との対照表
別紙1-5にならい、今回調査の現存・消滅干潟と前回調査の現存干潟との対応関係を「前回調査区との対照表」にとりまとめる。
(2)干潟生物調査
ア 標本区環境調査票
別紙1-6にならい、標本区における干潟環境の概況、底生生物相等を「標本区環境調査票」にとりまとめる。
イ 底生生物調査票
別紙1-7にならい、標本区における底生生物調査の結果をとりまとめる。
(3)藻場分布調査および藻場消滅状況調査
ア 藻場分布図
別紙1-8「藻場分布図」(略)にならい、現存藻場、消滅藻場の位置・範囲を1/50,000地形図上に図示する。
イ 現存藻場調査票・消滅藻場調査票
別紙1-9、別紙1-10にならい、現存藻場、消滅藻場の面積、タイプ、その他の項目について、各調査区ごとに「現存藻場調査票」または「消滅藻場調査票」にとりまとめる。
ウ 現存・消滅藻場一覧表
別紙1-11(略)にならい、現存藻場、消滅藻場の分布概要を「現存・消滅藻場一覧表」にとりまとめる。
8 調査結果の報告
受託者は調査結果をとりまとめ、報告書2組と干潟・藻場分布図帳2部をそれぞれ、別紙2「報告書作成要領」(略)および別紙3「干潟・藻場分布図帳作成要領」(略)により作成し、当該年度の3月31日までに環境庁自然保護局長あて提出する。
<別紙1>
干潟・藻場調査実施要領
I. 干 潟 調 査
ア 干潟分布調査及び干潟改変状況調査
1 調査のねらい
(1)干潟分布調査
現存する干潟の最新の分布状況、面積、主な特性を明らかにする。
(2)干潟改変状況調査
前回調査以降の埋立、浚渫等の人工改変による干潟の消滅状況を調査し、開発による干潟改変の動向を把握する。
2 調査対象の定義
(1)干潟分布調査(現存干潟)
現存する干潟で、次の要件の全てに合致するもの。
1 高潮線と低潮線に挟まれた干出域の最大幅が100m以上あること。
2 大潮時の連続した干出域の面積が1ha以上であること。
3 移動しやすい底質(礫、砂、砂泥、泥)であること。
* 干出幅は、基本的には大潮時の平均高潮線・低潮線で判断するものとするが、不明な場合は地形図(国土地理院)や海図上に記載されている干潟の幅(5万分の1地形図上では2mm)をめやすに判断してさしつかえない。
* 河口干潟については、河口から第1橋(埋立地内の橋は含めない)まで対象とする。 また河口干潟については、干出幅が100mに満たなくとも、連続した干出域の面積が1ha以上あれば対象とする。
* 人工的に造成された干潟も対象とする。
(2)干潟改変状況調査(消滅干潟)
前回調査以降、埋立、浚渫その他の人工的改変により消滅した干潟で、次のすべての要件に合致するもの。
1 前回調査時点(昭和53年度末とする。)において存在した千潟であること。
なお、前回調査に記載されている干潟であっても、上のアの定義に該当しないものは存在したものとはみなさない。
2 消滅面積が1ha以上であること。埋立て等の事業区域が1ha以上あっても、干潟そのものの改変が1haに満たないものは消滅域には含めない。
3 調査区
・調査は調査区単位で行なう。
・調査区は前回調査のものとは別に、今回新たに以下の方針に基づき設定する。
・設定された調査区について通し番号を付与する。
* 現存干潟、消滅干潟は区別せず一連の通し番号とする。
・今回設定された調査区と前回調査の調査区との対応関係を、別途調査区対照表として整理する。
(1)現存干潟
・原則として、同タイプの干潟が連続的に分布する範囲(分布域)を1調査区とする。
ただし、分布域が長大な場合は、河口、みお、航路、岬角等の地形で適宜区分することができる。
また、河口等で小面積の分布域が接近している場合は、まとめて1調査区とすることができる。(対象要件を満たしていない小面積の分布域は含めない)
・調査区の区分は、できるだけ前回調査での区分と対応させることとするが、人工改変による消滅や地形の変化等により、前回の調査区区分に従うことが適当でない場合は適宜変更する。
(参考図1-1調査区の設定―現存干潟)
(2)消滅干潟
・埋立て等の同一工区(同時に着工された一体の工事)ごとに区分して1調査区とする。 (参考図1-2調査区の設定−消滅干潟)
4 調査項目
干潟分布調査及び干潟改変状況調査の調査項目は以下のとおりとする。
(1)干潟分布調査
・分布域の位置
・範囲
・面積
・干潟のタイプ
・底質
・遮蔽度
・植生
・藻場
・鳥類の渡来状況
・清澄度
・海岸改変状況
・陸域の土地利用
・保護指定
・干潟の利用
・環境質の変化
・開発計画
(2)干潟改変状況調査
・消滅域の位置及び範囲
・面積
・消滅時期
・消滅原因
・消滅前の干潟のタイプ
5 調査方法
(一般的事項)
既存資料による資料調査を基本とするが、経費の許す限りヒアリング調査や現地確認調査を行なうことが望ましい。
〔参照すべき既存資料の例〕
・第2回自然環境保全基礎調査(干潟・藻場・サンゴ礁調査)の成果物
・最新の空中写真
・国土地理院発行の地形図
・海上保安庁水路部発行の海図
・国土庁または経済企画庁総合開発局作成の土地分類図
・第3回自然環境保全基礎調査(海岸調査、海域生物環境調査等)の成果物
・埋立て計画等に関する各種環境アセスメント図書
・ノリ養殖等の漁場図
・既往の調査報告書
・その他
(各項目別の調査方法)
(1)分布域・消滅域の位置・範囲
前回調査の原因、空中写真の読み取り、地形図等の記載、その他の知見により把握する。 消滅域については、公有水面埋立図書等も参考にする。
(2)分布域・消滅域の面積
面積は原則として五万分の1地形図上に転記した分布域・消滅域を日林協式点格子板を用いて読み取るものとする。なお小面積の調査区にあっては、平均沖出し幅×延長による概算値としてさしつかえない。 ha単位(ha未満は四捨五入)とする。
(3)消滅時期
公有水面埋立図書その他の知見を参考に把握する。なお消滅時期は埋立て工事等の着工時点とする。
(4)消滅原因
公有水面埋立図書その他の知見を参考に、次の区分により把握する。
1 埋立 2 干拓 3 浚渫 4 その他(内容を具体的に記述)
(5)干潟のタイプ
地形・成因からみた干潟のタイプについて、次の区分により把握する。
1 前浜 2 河川 3 潟潮 4 その他(人工干潟などを具体的に記述)
(6)底質
干潟の底質について資料調査及び必要に応じ現地調査等を行ない、次の区分により把握する。 異なる底質が含まれる場合は最も面積の広いものを記載する。
1 礫 2 砂 3 砂泥 4 泥
なお底質のちがいは下記により判断する。
礫 粒径2mm以上
砂 0.1〜2mm 水中で撹絆するとすぐ沈積する。
泥 0.1mm以下 水中で撹拝しても沈積しにくい。
砂泥 砂と泥の混合
(7)遮蔽度
波浪の強さや頻度からみた海岸のタイプについて、次の区分により把握する。
1 開放海岸 2 保護海岸 3 包囲海岸
(8)植生
干潟内の主要な陸上植生の有無および種類について、空中写真、植生図等既存資料を参考に次の区分により把握する。(小面積で局地的に分布するものは無視する。)
0 不明
1 干潟内には植生はない。
2 冠水草原(アシ、オギ等)
3 塩沼地植生(草本:アツケシソウ、シチメンソウ等)
4 塩沼地植生(木本:マングローブ)
5 その他(内容を具体的に記述)
(9)藻場
干潟内の藻場の有無および種類について、空中写真その他既存資料等を参考に次の区分に従い把握する。
1 なし 2 アオサ・アオノリ場 3 アマモ場 4 その他の藻場
(10)鳥類の渡来状況
当該干潟へのシギ・チドリ類の渡来状況について、各県の野鳥関係団体や専門家からのヒアリングを行ない、次の区分により把握する。
0 不明
1 渡来数が特に多い。
2 渡来数が多い。
3 渡来数は少ない。
4 種類が多い。
5 大型のシギ類が含まれる。
(11)清澄度
干潟の海水のきれいさの程度について、次の区分により把握する。
1 きれい。 海の底がよく見え、快適な気分で泳げる程度
透視度30cm以上
2 少し汚れている。 海水に浸かることが気にならない程度
透視度20〜30cm程度
3 かなり汚れている。 海水に浸かる気がしない程度、透視度20cm以下
(12)海岸改変状況
干潟の海岸線の改変状況を下記の区分により把握する。
自然海岸、半自然海岸、人工海岸の定義は、第3回基礎調査海岸調査によることとし、河口及び河川内の場合はその他に区分する。詳細は上記調査実施要領を参考にすること。
上記海岸調査の結果を参照し、その後の変化を確認することにより調査する。
なお同一調査区内に異なる海岸区分が含まれる場合はすべて記載する。
|
1 自然海岸 |
海岸(汀線)が人工によって改変されないで自然の状態を維持している海岸。 |
|
2 半自然海岸 |
道路、護岸、テトラポット等の人工構築物で海岸(汀線)の一部に人工が加えられているが、潮間帯においては自然の状態を保持している海岸。 |
|
3 人工海岸 |
埋立・浚渫・干拓等により人工的につくられた海岸等潮間帯に人工構築物がある海岸。 |
|
4 その他 |
河口部、河川内。 |
(13)陸域の土地利用
干潟に接する陸域の土地利用について、上記海岸調査結果等を参考に次の区分に基づき把握する。
|
1 自然地 |
樹林地、砂浜等人工によって改変されないで自然の状態を保持している土地。 |
|
2 農業地 |
水田、畑、牧野等農業的土地利用が行なわれている土地。 |
|
3 市街地・工業地 |
上記以外の土地。 |
|
その他 |
(14)保護指定
干潟内および背後の陸域の保護指定の状況を、上記海岸調査結果等を参考に次の区分により把握する。
なし:0
国立公園…………[特別保護地区:11 特別地域:12 普通地域:13]
国定公園…………[特別保護地区:21 特別地域:22 普通地区:23]
県立自然公園…………………………[特別地域:32 普通地区:63]
自然環境保全地域……………………[特別地区:52 普通地区:53]
県自然環境保全地域…………………[特別地区:62 普通地区:63]
鳥獣保護区……………………………[特別保護地区:71 その他:73]
(15)干潟の利用
干潟におけるレクリエーション利用の状況を既存資料、ヒアリング等により次の区分にしたがって把握する。
0 不明 1 潮干狩 2 つり 3 海水浴 4 バードウッチング 5 その他(内容を具体的に記述)
(16)環境質の変化
既存資料、ヒアリング等により現時点で認められる環境質の変化や汚染状況について、つぎの区分に従い把握する。
0 不明
1 特になし
2 自然的地形変化(内容を具体的に記述)
* 侵食、河道の変化等人工改変以外の要因による地形変化で顕著に認められるもの。
3 開発にともなう土砂・シルトの流入
4 赤潮、青潮の発生
5 ごみの漂着
6 その他(内容を具体的に記述)
(17)開発計画
埋立て等の大規模な開発が計画されている場合、その名称・内容を具体的に記述する。
|
(参考図1−1 調査区の設定−現存干潟)
|
|
(参考図1−2 調査区の設定−消滅干潟)
|
イ 干潟生物調査
1 調査のねらい
各県の現存干潟から代表的な干潟を選定し、底生生物を中心とした現地調査を行ない、その特徴を把握する。
2 対象調査区(=標本区)の選定
干潟生物調査を実施する調査区(以下標本区という。)は、干潟分布調査の対象調査区の中から、各県において次のような考え方に基づき選定する。
1 各県につき概ね5カ所を選定する。
2 シギ・チドリ類の渡来地として重要な干潟をできるだけ選定する。
3 できるだけタイプ、底質の異なる干潟を選定する。
4 地域的な偏りのないよう選定する。
3 調査項目及び内容
(1)環境の概況
地形、底質、植生、土地利用等干潟環境の概況を把握する。
(2)底生生物の生息状況
干潟の潮間帯を上部(岸寄り)、中部、下部(沖寄り)の3ゾーンに区分し、それぞれのゾーンで主要な底生生物の種類と出現状況を把握する。
(3)鳥類の渡来状況
干潟に渡来するシギ・チドリ類、ガン・カモ類等の渡り鳥の主な種、渡来時期、渡来数、干潟での生態等を把握し、概要を記述する。
3 調査方法
(1)全般的事項
1 環境の概況および2 底生生物の生息状況については、原則として現地調査により把握する。 なお併せて既存資料調査やヒアリング調査も行い、現地調査データを補完する。
(下記の方法による現地調査と同精度の最新のデータが得られる場合には、既存資料による資料調査としてさしつかえない。)
3 鳥類の渡来状況については、主として県内の野鳥関係団体、専門家からのヒアリング及び資料調査により把握する。
(2)現地調査
・標本区内の典型的環境を有する地点を選び、大潮の干潮時に現地調査を実施する。
・観察適期に調査できなかったため、十分なデータが得られなかった生物については必要に応じ既存のデータにより補完する。
・各調査地点では次により調査を行なう。
1調査起点及び調査測線の設定。
・汀線陸側の護岸等を起点とし、沖側に向かって調査測線を設定する。
2調査地点周辺の概観
・調査地点周辺を広く観察し、地形、底質、植生の分布、鳥類の生息状況、海岸線の改変状況、陸域の土地利用等当該地点の環境の概況を把握する。この際調査測線上の低潮線、高潮線、底質、植生分布等について、起点からの概略の距離を測定しておく。 また調査地点周辺の現況写真を撮影する。
3底生生物相の観察
・調査測線上で干潟の潮間帯(大潮時の低潮線と高潮線の間)を上部(陸寄り)、中部、下部(沖寄り)の3ゾーンにおおむね3等分する。(干潟の幅が狭く3ゾーンの区分が難しい場合は、上部、下部の2ゾーンとする。)
・各ゾーンでおおむね10カ所の観察点を設定し、シャベルで底質を堀り取り、目にふれる底生生物の種及び個体数を観察する。
・観察点は互いに10m以上離し、基本的には測線方向に配置することとするが、具体的な位置は、底生生物の生息状況が偏りなく把握できるよう適宜現地で判断する。 なお、上部ゾーンでは高潮線付近(高潮線が護岸等から始まっている場合はその直下)の、また下部ゾーンでは低潮線付近の観察点が、必ず含まれるよう留意する。
・各観察点では、干潟表面及び砂泥中の生物を目視観察する。砂泥中の生物は、シャベルで表層から20cm〜30cmの深さまで堀取り観察する。 観察する範囲は50cm×50cmをめやすとするが、厳密なコードラートを設定する必要はない。
・観察対象とする生物は、現場で目視で容易に識別し得る大きさ以上のものとし、観察事項は種(類)及び個体数の多さの程度(多い、普通、少ない)とする。
*個体数の多さの基準は種によって異なり、一律には示せないので調査者が経験に基づき判断する。
あらかじめ調査票に記載されている代表的な種(類)については、必ずチェックし、それ以外の種については主なものについて同様に観察する。
なお、調査票は本州(房総以西)・四国・九州海域と南西諸島海域の2海域で、それぞれ異なるものを用いる。
各観察点の観察結果は総合し、各ゾーン全体の観察結果として取りまとめ記録する。
・観察結果は次の底生生物の分類群に区分して記載する。
二枚貝類
巻貝類
カニ・エビ・ヤドカリ類
その他の底生動物(ゴカイ類、イソギンチャク類等)
植物(海藻・海草類)
・底生動物の出現状況は、当該種のゾーン全体を通じた出現頻度及び各観察点における個体数の多さに着目し、次により判断する。
|
レベル |
判断基準 |
|
多い |
どこでも見られ、個体数も多い。 |
|
(・多くの観察点で出現し、かつ個体数の多い観察点が多い。) |
|
|
ところにより多い |
ところにより、数多く見られる。 |
|
(・多くの観察点で出現するが、個体数の多い観察点は限られている。又は、 |
|
|
・一部の観察点に限り出現するが、そこでの個体数が多い。) |
|
|
普通に見られる |
どこでも見られるが、個体数は多くない。 |
|
(・多くの観察点で出現するが、どの観察点でも個体数は普通、または少ない。) |
|
|
少ない |
ところにより見られるが、個体数は多くない。 |
|
(・一部の観察点にのみ出現し、個体数は普通、または少ない。) |
|
|
見られない |
見られない。 |
|
(・いずれの観察点にも出現しない。) |
・植物は藻場としてのまとまりをなして出現するものを対象とする。出現状況は、次により当該藻場の疎密度で判断する。
疎密度 判断基準
濃生 海底面がほとんど植生によって覆われている。
蜜生 海底面より植生のほうが多い。
疎生 植生よりも海底面のほうが多い。
II. 藻 場 調 査
藻場分布調査及び藻場消滅状況調査
1 調査のねらい
(1)藻場分布調査
現存する藻場の最新の分布状況、主な特性を明らかにする。 また、前回調査以降の面積、疎密度等の変化の傾向およびその原因を把握する。
(2)藻場消滅状況調査
前回調査以降における藻場の消滅状況(人工改変だけでなく、海況変化による自然消滅等も含む。)及びその原因を把握する。
2 調査対象の定義
(1)藻場分布調査(現存藻場)
現存する藻場で、次の要件のすべてに合致するもの。
1 面積が1ha以上であること。
2 水深20m以浅に分布すること。
(2)藻場消滅状況調査(消滅藻場)
前回調査以降消滅したと判断される藻場で、次のすべての要件に合致するもの。
なお埋立、浚渫などの人工改変だけでなく、海況変化その他の要因による消滅域も含むものとするが、季節変動による一時的な消滅域は除くこと。
1 前回調査時点で存在していた藻場であること。
2 消滅面積が1ha以上であること。
3 調査区
・調査は調査区単位で行なう。
・調査区は前回調査のものとは別に、新たに以下の方針に基づき設定する。
・設定された調査区について、通し番号を付与する。
* 現存干潟、消滅干潟は区別せず一連の通し番号とする。
(1)現存藻場
・原則として、藻場が連続的に分布する範囲(分布域)を1調査区とする。 ただし分布域が長大な場合は、河口、みお、岬角等の自然地形で適宜区分して1調査区とすることができる。
また、小面積の分布域が接近している場合は、まとめた1調査区とすることができる。 (対象要件を満たしていない小面積の分布域は含めない。)
* 異なるタイプの藻場であっても、連続し一体の分布域をなしている場合は、同一の調査区として扱ってさしつかえない。
・調査区の区分はできるだけ前回調査の区分と対応させることとするが、分布域の変動等により困難な場合には、現時点でも最も適切な区分を適宜設定する。
(参考図2-1調査区の設定−現存藻場)
(2)消滅藻場
・連続する消滅域を1調査区とする。
埋立て等の人工的改変による消滅域の場合も、一連の消滅域は一括して1調査区として差し支えない。(消滅干潟の場合とは異なることに注意。)
(参考図2-2調査区の設定−消滅藻場)
4 調査項目
藻場分布調査及び藻場消滅状況調査の調査項目は、以下の通りとする。
(1)藻場分布調査
・分布域の位置及び範囲
・面積
・藻場のタイプ
・優占種
・疎密度
・分布域及び疎密度の経年変化
(2)藻場消滅状況調査
・消滅域の位置及び範囲
・面積
・消滅前の藻場のタイプ
・消滅原因
5 調査方法
(一般的事項)
既存資料による資料調査とするが、経費の許す限りヒアリング調査や現地確認調査を行なうことが望ましい。
[参照すべき既存資料の例]
・第2回自然環境保全基礎調査(干潟・藻場・サンゴ礁調査)の成果物
・最新の空中写真
・埋立て計画等に関する環境アセスメント図書
・水産資源関係の調査報告書
・その他
(各項目別の調査方法)
(1)分布域・消滅域の位置および範囲
前回調査の原図・空中写真の読み取り、公有水面埋立図書、既存の調査資料、ヒアリング結果等を参考にして把握する。
なお分布域は、年間で最も海藻・草類が繁茂する時期のものとする。
(2)分布域・消滅域の面積
分布域・消滅域の面積は、原則として五万分の1地形図上に転記した分布域・消滅域を日林協式点格子板を用いて読み取るものとする。 数値は1ha単位(1ha未満は四捨五入)とする。
(3)消滅理由
次の区分により、公有水面埋立図書、既存の調査資料、その他漁業関係者からのヒアリング等を参考にして把握する。
1 埋立て等の直接改変 2 磯焼け 3 乱獲 4 その他海況変化等 0 不明
(1および4の場合は内容を具体的に記述)
(4)藻場のタイプ
構成種から見た藻場のタイプについて、前回調査その他の既存資料、ヒアリングなどにより、次の区分に従い把握する。
1 アマモ場 2 ガラモ場 3 コンブ場 4 アラメ場 5 ワカメ場 6 テングサ場 7 アオサ・アオノリ場 8 その他
* 各タイプの代表的な構成種(類、科、属名を含む)は、以下のとおり。
|
1 アマモ場 |
: |
アマモ、コアマモ、スガモ、エビアマモ、スゲアマモ、ウミヒルモ |
|
2 ガラモ場 |
: |
○○○モク、ウミトラノオ、ホンダワラ |
|
3 コンブ場 |
: |
○○○コンブ、チガイソ、アナメ |
|
4 アラメ場 |
: |
カジメ、アラメ、スジメ、アジメ、クロメ、ツルアラメ |
|
5 ワカメ場 |
: |
ワカメ、ヒロメ |
|
6 テングサ場 |
: |
テングサ類、マクサ、オオブサ、オバクサ |
|
7 アオサ・アオノリ場 |
: |
アオサ類、アナアオサ、ヒトエグサ、アオノリ類、ヒラアオノリ |
|
8 その他 |
: |
その他の海藻・海草類 |
(5)優占種
前回調査その他の既存資料、ヒアリングなどにより、調査区における海藻・海草類の主な優占種名を把握する。
(6)疎密度
藻場の植生の繁茂密度について、既存資料、ヒアリングなどにより、次の区分に従い把握する。 当該藻場の最も繁茂する時期における状態で判断し、また同一調査区内で異なる疎密度が認められる場合には、優占するものを記入する。
1 疎生 :植生よりも海底面のほうが多い。
2 蜜生 :海底面より植生のほうが多い。
3 濃生 :海底面がほとんど植生で覆われている。
0 不明
(7)経年変化
前回調査時点以降の分布域、疎密度の変化傾向およびその理由を、前回調査結果その他の既存章料およびヒアリング等により把握する。
なおここでの経年変化とは、短期的な周期で繰り返される変動ではなく、長期的に一定の傾向が持続していると認められるものとする。
ア 分布域 : 1 増加傾向 2 減少傾向 3 変化なし 0 不明
イ 粗密度 : 1 増加傾向 2 減少傾向 3 変化なし 0 不明
ウ 原因 : 1 埋立て等の直接改変 2 磯焼け 3 乱獲 4 その他海況変化等 0 不明
(1、4の場合は内容を具体的に記述)
前回調査区との対照表
(記入上の注意)
・様式は前頁に掲げるものとし、用紙はB5判、左側2つ穴あきとする。
・今回調査の現存・消滅干潟かかる調査区と、前回調査(第2回基礎調査干潟・藻場・サンゴ礁調査)の現存干潟にかかる調査区との対応関係を整理し記載する。
・今回調査区の「番号」、「面積」には、調査区番号および各調査区における分布域・消滅域の面積を調査区番号順に記入する。
・前回調査区の「番号」、「面積」には、前回調査の干潟分布図および干潟調査票に記載されている現存干潟の調査区番号および面積を記入する。
・今回調査と前回調査の調査区の対応関係は次により整理する。
1 前回と今回の調査区が1:1に対応する場合
(干潟の形状や面積が変化しても、調査区の区切りには変化がないもの)
対応する今回と前回の調査区の番号、面積をそれぞれ記載し、区分の変更欄には変更なしと記入する。 ただし、前回調査区のすべてがそのまま消滅調査区に移行した場合は、備考欄に全部消滅と注記する。
2前回と今回の調査区が1:1に対応しない場合
(人工改変による消滅等により、前回調査区が分割されたり、あるいは調査方法の変更により統合されたもの)
対応する今回と前回の調査区のグループ毎にまとめて、それぞれの調査区番号、面積を記載する。 区分の変更欄には一部消滅、分割、統合、再編等と移行関係がわかるように記載する。
3前回の現存干潟調査区で、今回の現存調査区、消滅調査区のいずれにも対応しない場合
(定義の変更にともない、実体上の変化の有無に関わらず調査対象から機械的に削除されたもの)
前回調査区についてのみ記載し、区分の変更欄には削除と記載する。
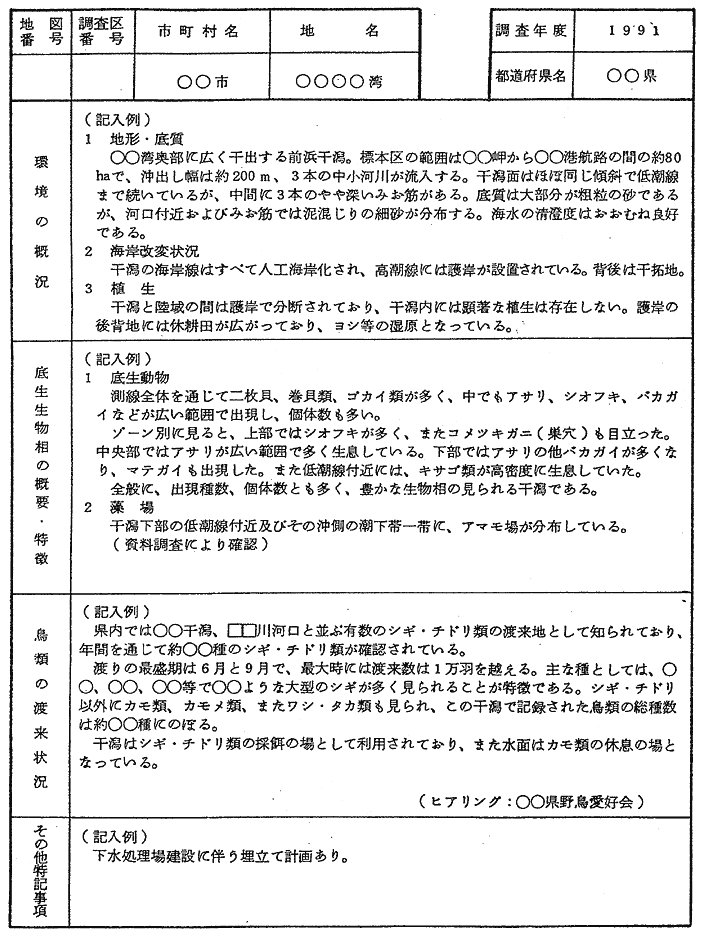 |
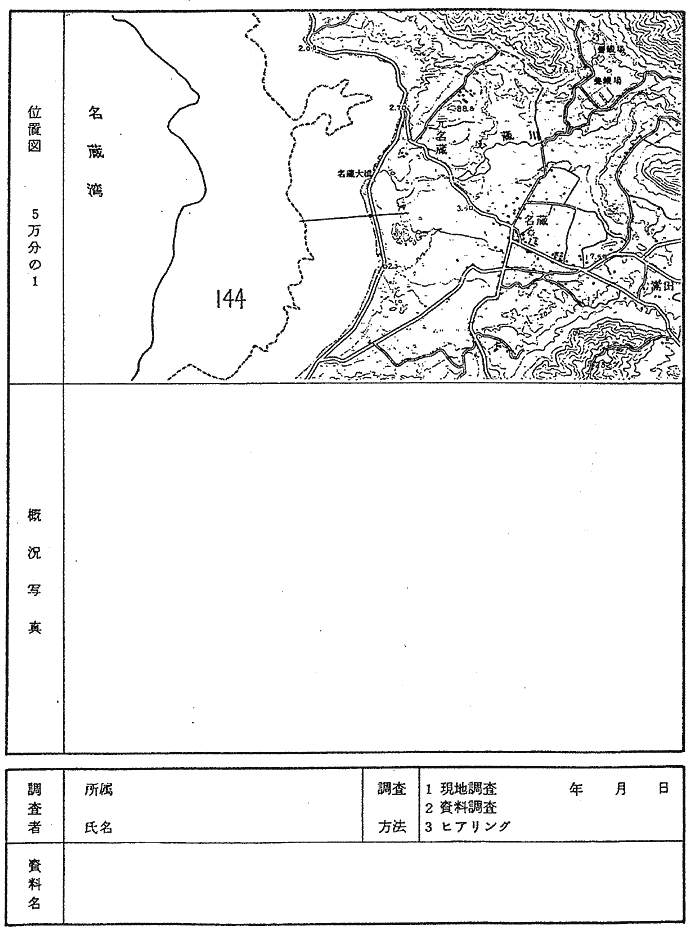 |
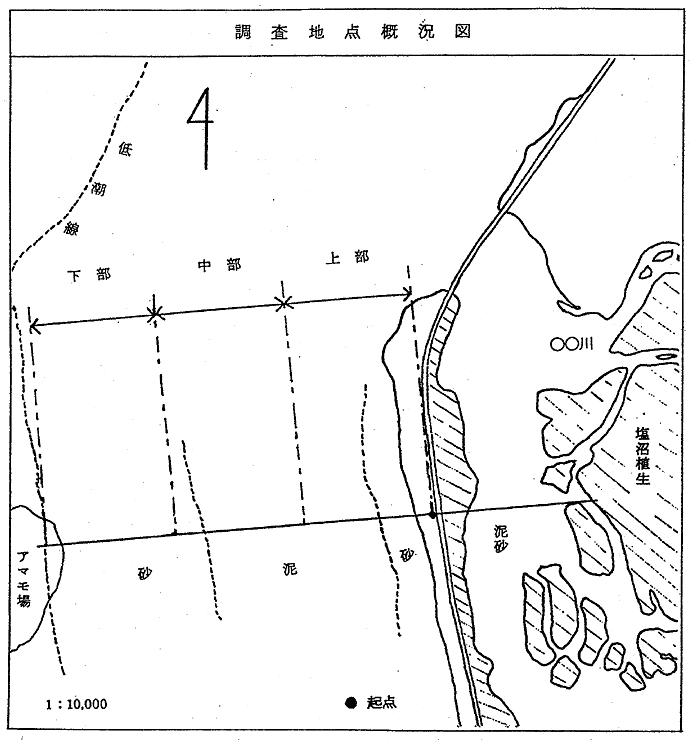 |
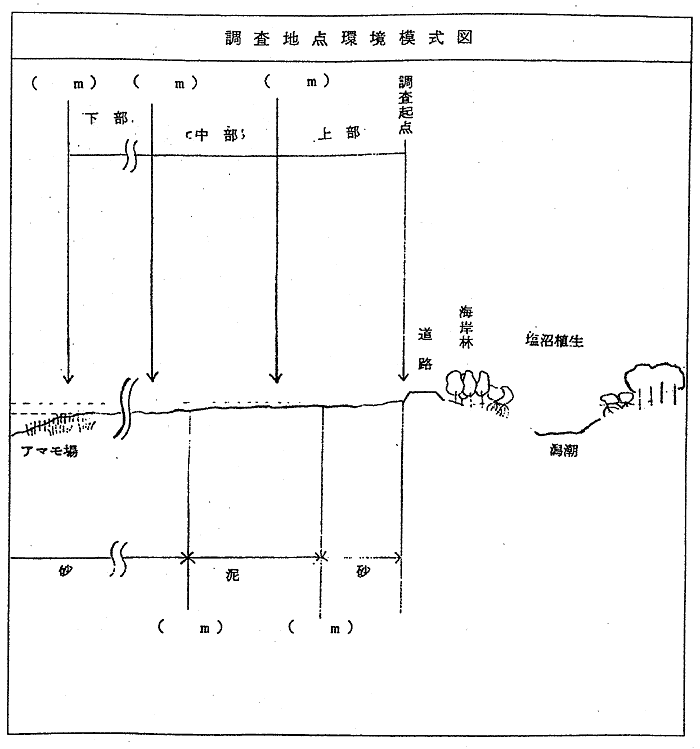 |
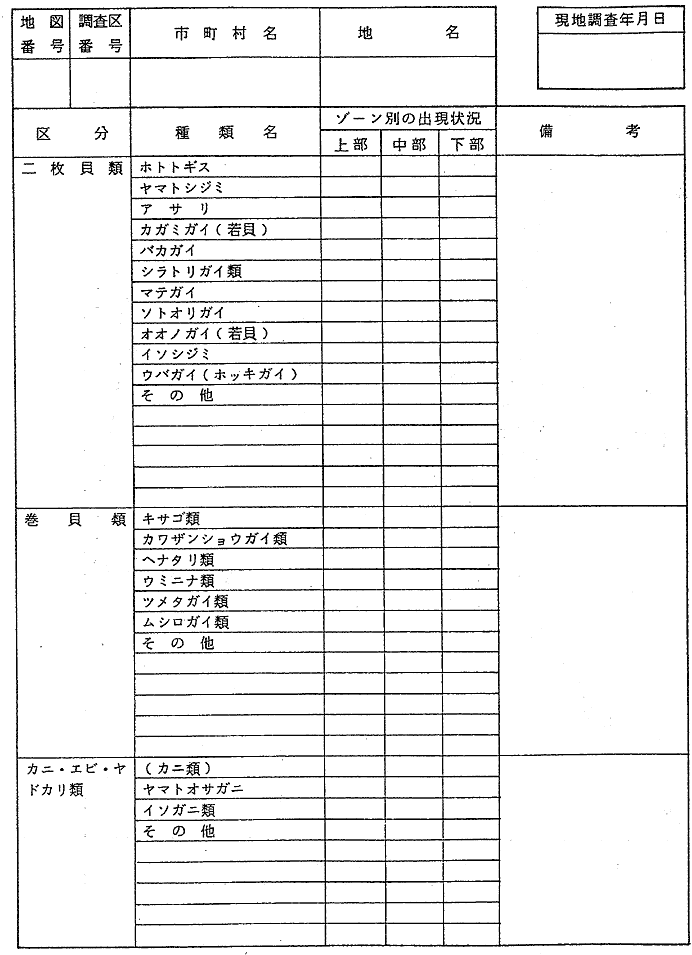 |
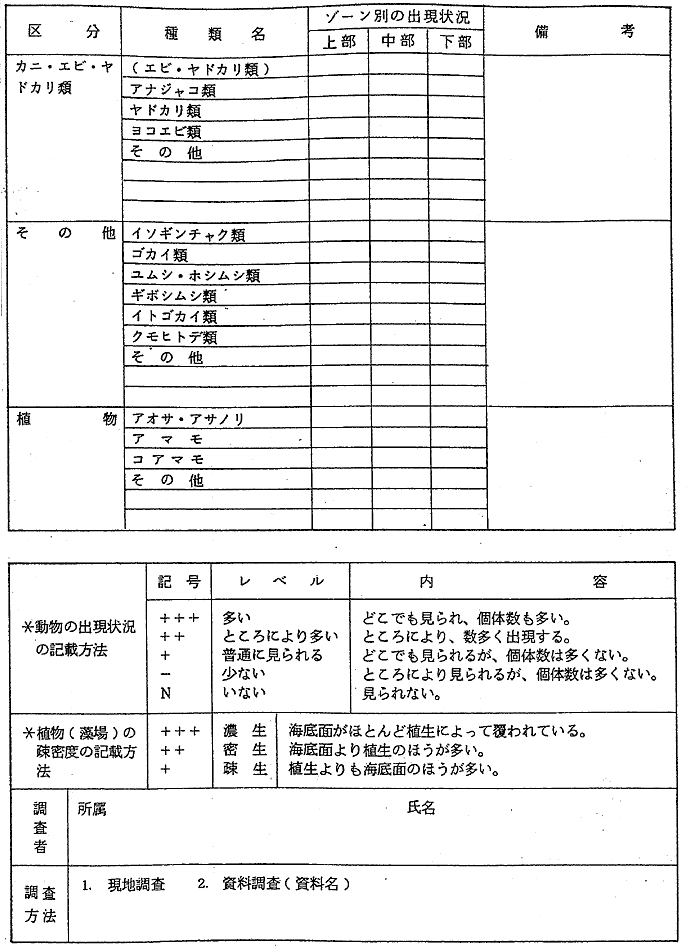 |
底生生物調査票
(調査表記入上の注意)
・干潟生物調査の各標本区ごとに作成する。
・原則として現地調査による観察結果を記入する。ただし、季節的要因等により現地調査では確認できなかった生物で、既存の知見により生息が確認されており、当該干潟の生物相の記載上欠かせないと判断されるものについては、資料調査によりその生息状況を記入する。
なおこの場合、「種類名」「出現状況」は()書きとし、資料調査によるデータであることを明示する。
・「地図番号」「調査区番号」「地名」は「干潟分布調査」での該当番号、地名をそれぞれ記入する。
1 「種類名」には、記載されている種(類)以外に出現状況のレベルが+以上のものが出現した場合、その種名を「その他」以下に記入する。
2 「出現状況」は、各ゾーンにおけるそれぞれの種の出現状況を、観察点での観察結果を総合し記入する。
なお、あらかじめ記載されている種類については、必ず観察結果を記入する。
・動物の出現状況は次により記入する。
+++ : 多い ++ : ところにより多い + : 普通に見られる
- : 少ない N : いない
・植物の出現状況は次により記入する。
+++ : 濃生 ++ : 密生 + : 疎生
3 「備考」には、当該種の生息状況について特記すべき事項があれば記入する。
4 「調査方法」には、底生生物にかかる調査方法で該当するものに○印を付し、既存資料のデータを用いた場合は、報告書等の資料名を下欄に記述する。