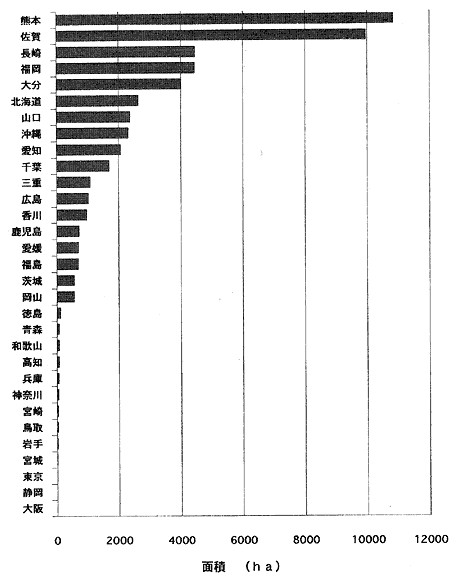
4. 考 察
・調査手法の問題点
調査対象区が全国にまたがる委託調査を実施する場合に、問題になるのは調査の精度である。実際のデータを解析してみて、精度の違いが各所にみられた。同じ規模、タイプ、底質が類似した干潟で生物構成種数が大きく異なる例が散見された。36の調査対象生物群のうち、一般に知られていない種群であるイトゴカイ類、ユムシ、ホシムシ類、キボシムシ類などの出現記録が少なかった。とくに、イトゴカイ類は全国的に分布するが、ゴカイ類と混同し、含められた可能性が強い。二枚貝では水産上の有用種以外の種でデータに含まれない種類があった。これを避けるためには、識別のためのマニュアルをつける必要がある。
1,000haに達する大規模な干潟と数haの小規模干潟では現地調査、とくに定量調査に費やす労苦には多大な差がでる。精度にも違いがでてくる可能性が高い。
全国的な干潟生物相の調査の場合、現地調査で、より定性的な面(種類数、優占種など)を、より精度を高くしていく必要があると考える。
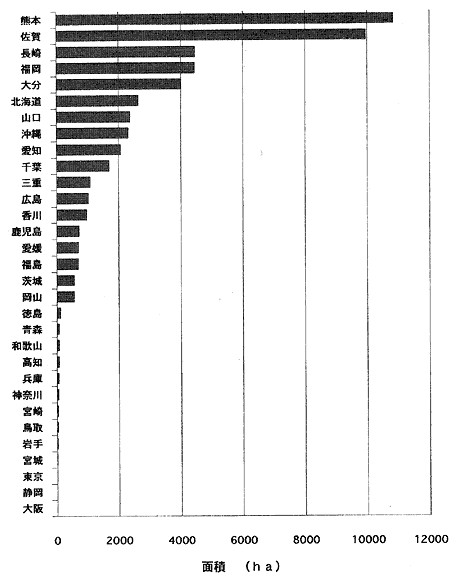
図2県別現存干潟面積
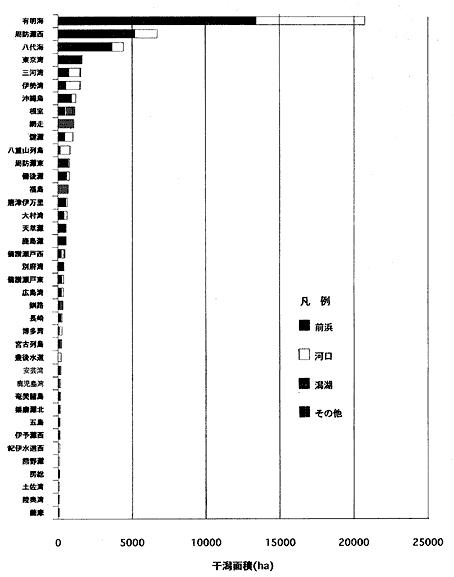
図3海域別タイプ別現存干潟面積
(上位39海域を掲載)
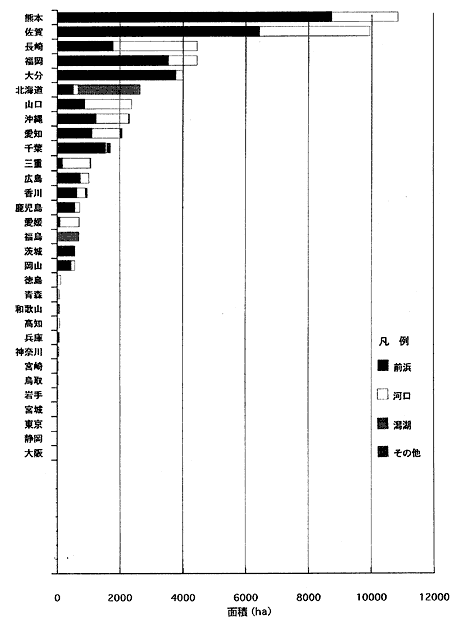
図4県別タイプ別現存干潟面積
表3県別タイプ別消滅干潟面積表*(ha)
|
県 |
コード |
前 浜 |
河 口 |
潟 湖 |
その他 |
計 |
|||||
|
現存 |
消滅 |
現存 |
消滅 |
現存 |
消滅 |
現存 |
消滅 |
現存 |
消滅 |
||
|
北海道 |
1 |
515 |
0 |
152 |
114 |
1980 |
5 |
0 |
0 |
2766 |
119 |
|
計 |
|
30812 |
1845 |
15408 |
2298 |
2062 |
10 |
145 |
1 |
52436 |
4154 |
*干潟タイプが複数示されている場合は複数のタイプに各々同面積が加算されている。
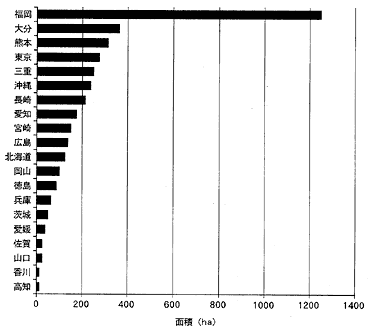
図5県別消滅干潟面積
表4 標本区干潟生物種類数順位表
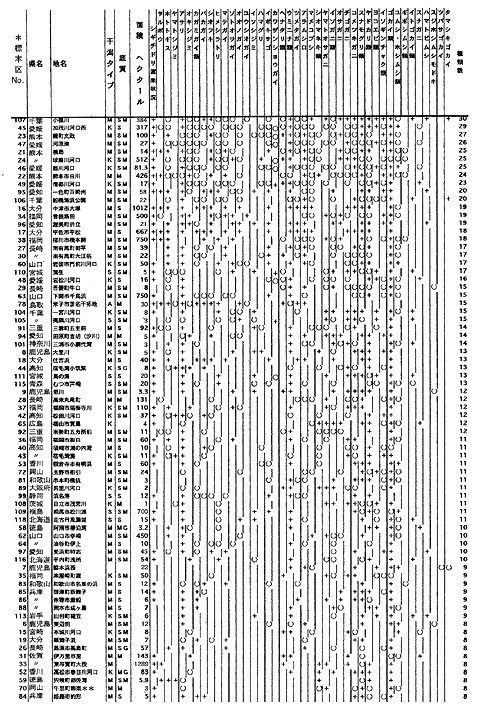
表4 標本区干潟生物種類数順位表(つづき)
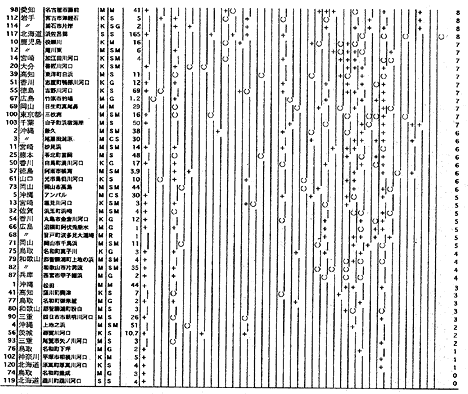
|
*
|
標本区No.は標本区に南から順に番号をつけた。なお、現存干潟番号との対応は図7に示した。
|
+:多いもしくは普通にみられる、鳥類の場合"渡来する"。 ○:少ないが分布する。 |
|
** |
沖出し幅95mで、現存干潟として記録されない干潟であるが、周辺に適地がなく県東部を代表する干潟として、調査した。標本区としたのは、師楽港奥部の西半分の干潟である。 |
干潟タイプ M:前浜 K:河ロ S:潟湖 底 質 S:砂 SM:砂泥 M:泥 G:礫 |
表5 標本区干潟面積順位表(上位56)
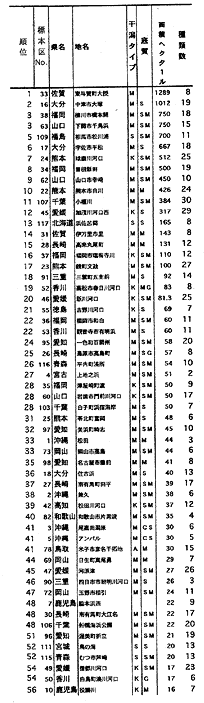 |
図6干潟面積と種類との関係 (図中の番号は標本区No.) |
|
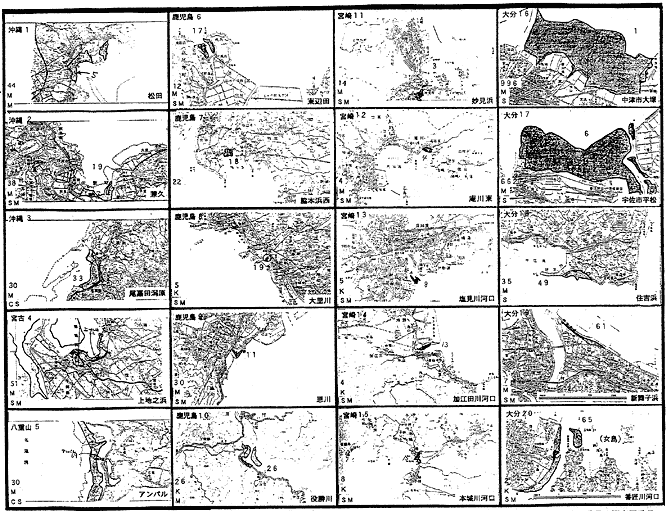 |
|
|
標本区番号 |
|
|
面積(ha) |
|
|
干潟タイプ |
|
|
底質 |
|
|
千潟タイプ M:前浜 K:河ロ S:潟湖 |
図7 標本区全国干潟地形図一1 |
図中の番号は調査区番号 |
|
底 質 S:砂 SM:砂泥 M:泥 G:礫 |
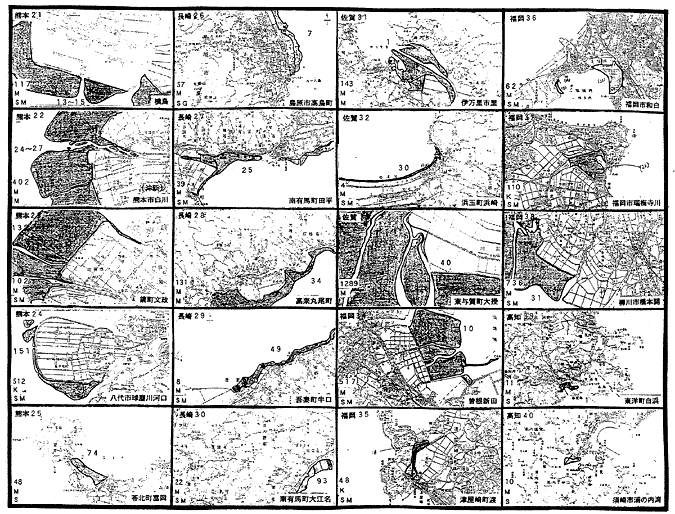
図7 標本区全国干潟地形図−2
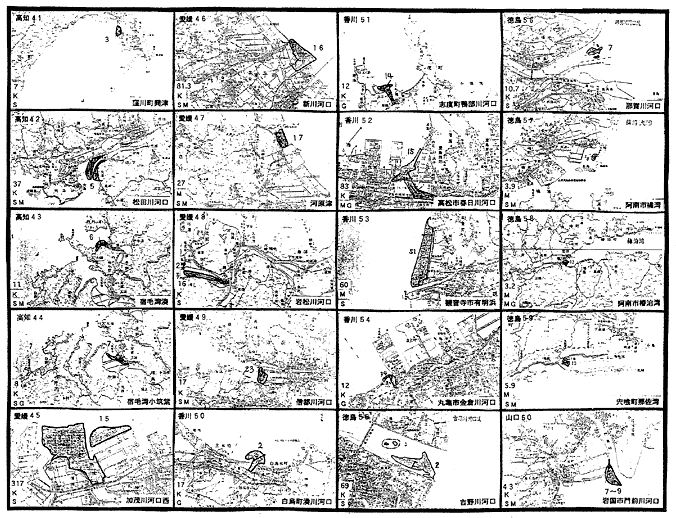
図7 標本区全国干潟地形図−3
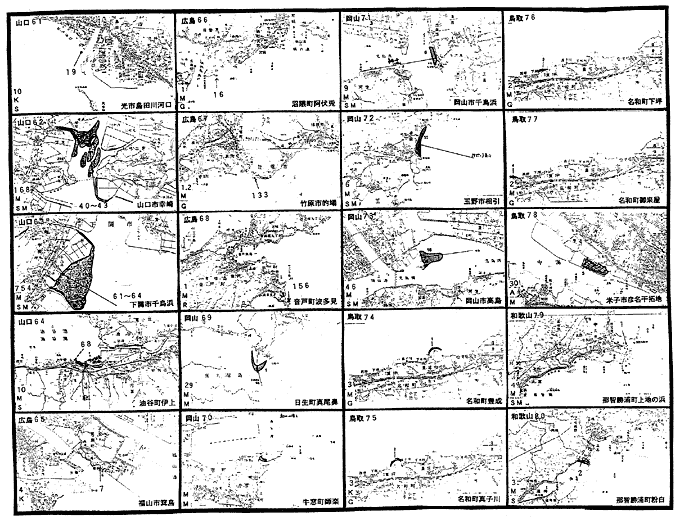
図7 標本区全国干潟地形図−4
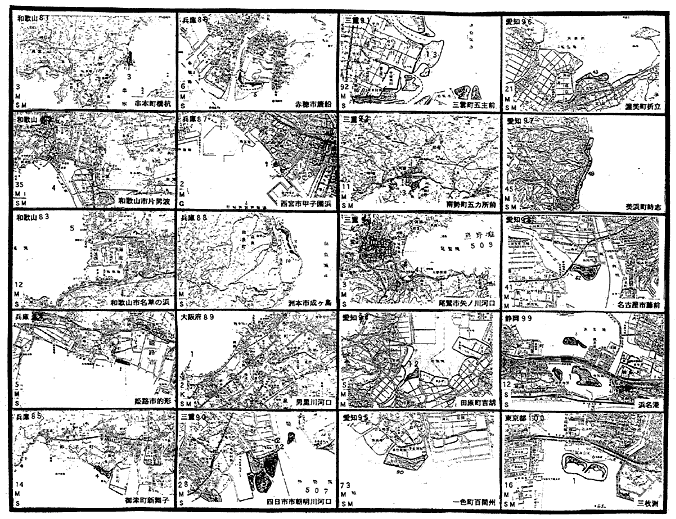
図7 標本区全国干潟地形図−5
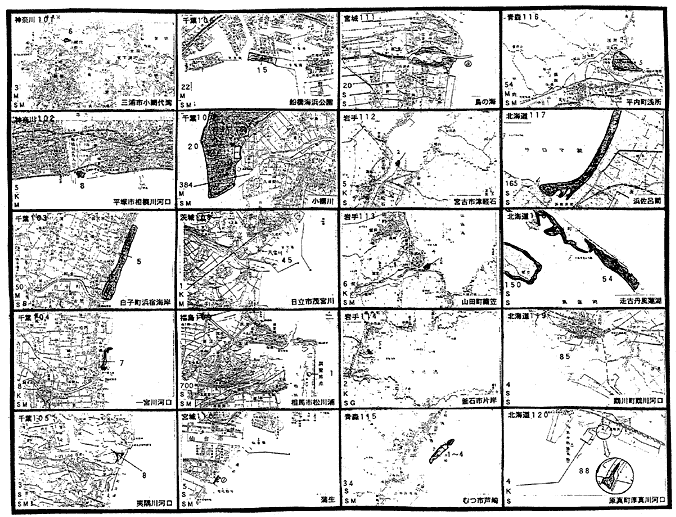
図7 標本区全国干潟地形図−6