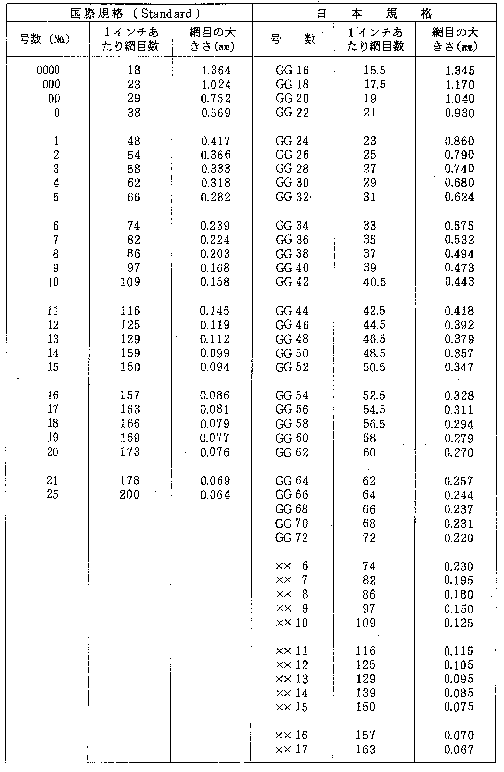
�@�R�|13�@�C��������v�j
�P�@�����̖ړI
�����̐�������݂��킪���̉��݈�̌����c�����邽�߁A�v�����N�g���A�ꐶ�����A�t���������ɂ��Ē�������B�i���j
�Q�@�������{��
�����s���{���Ɉϑ����Ď��{����B
�R�@�������{����
�_������̓����珺�a54�N�R��31���܂łƂ���B
�S�@�������e
�������鎖���͎��̂Ƃ���Ƃ���B
(1)�@�v�����N�g��
(2)�@�ꐶ����
(3)�@�t������
(4)�@��@���@��
(5)�@�ԁ@�@�@�@��
�T�@�������@
�����̃f�[�^�����W���A�ʍ��u�R�[�h�ԍ��ꗗ�v�ɂ��敪���ꂽ�C�悲�Ƃɐ�������B
�������@�̏ڍׂ͕ʎ��P�u�C����������{�v�́v�ɂ��B
�U�@�������ʂ̂Ƃ�܂Ƃ�
����҂́A�������ʂ����L�̐}�\�ɂƂ�܂Ƃ߂�B
(1)�@�̏W�n�_�ʒu�}�A�C����萶�����z�}�A�咰�ۑ���_�}�A�Ԓ������C��}�i�ȉ��u�����}�v�Ƒ��̂���B�j
�A�@�̏W�n�_�ʒu�}
�v�����N�g���A�ꐶ�����A�t�������Ɋւ���f�[�^�̓���ꂽ�n�_�ʒu���A�ʎ��Q�u�̏W�n�_�ʒu�}�v�ɂȂ炢���y�n���@���s��1�^20���n���}�ɕ\������B
�C�@�C����萶�����z�}
�V�Y�N�K�C�A�`���m�n�i�K�C�A���c�o�l�X�s�I�ACapitella�@Capitata�A�����T�L�C�K�C�̕��z���m�肳�ꂽ�n��y�ђꐶ�����̑S���������Ȃ������������邱�Ƃ��m�F���ꂽ�n��i�ȉ��u��������v�Ƃ����B�j��ʎ��R�u�C����萶�����z�}�v�ɂȂ炢���y�n���@���s��1�^20���n���}�ɕ\������B
�E�@�咰�ۑ���_�}
�咰�یQ���̑���_�̈ʒu�y�ё��茋�ʂ�ʎ��S�u�咰�ۑ���_�}�v�ɂȂ炢���y�n���@���s��1�^20���n���}�ɕ\������B
�G�@�Ԓ������C��}
�Ԓ��̔��������C����A�ʎ��T�u�Ԓ������C��}�v�ɂȂ炢�A���y�n���@���s��1�^20���n���}�ɕ\������B
(2)�@�v�����N�g���f�[�^�\
�v�����N�g���Ɋւ���f�[�^��ʎ��U�u�v�����N�g���f�[�^�\�v�ɐ�������B
(3)�@�ꐶ�����f�[�^�\
�ꐶ�����Ɋւ���f�[�^��ʎ��V�u�ꐶ�����f�[�^�\�v�ɐ�������B
(4)�@�t�������f�[�^�\
�t�������Ɋւ���f�[�^��ʎ��W�u�t�������f�[�^�\�v�ɐ�������B
(5)�@�咰�ۃf�[�^�\
�咰�ۂɊւ���f�[�^��ʎ��X�u�咰�ۃf�[�^�\�v�ɐ�������B
(6)�@�Ԓ������\
�Ԓ��̔����Ɋւ���f�[�^��ʎ�10�u�Ԓ������\�v�ɐ�������B
�V�@�������ʂ̕�
����҂́A�������ʂ��Ƃ�܂Ƃ߁A��150���y�ђ����}���P�����A���ꂼ��ʎ�11�u���쐬�v�́v�A�ʎ�12�u�����}���쐬�v�́v�ɂ��쐬���A���a54�N�R��31���܂łɊ������R�ی�ǒ����Ē�o����B
�@�@(�ʎ��P) �C����������{�v��
�P�D�ʁ@�@��
��Q�R���ۑS��b�����C��������́A���̎��{�v�̂ɏ]���čs���B
�Q�D���W�����͈̔�
�������ɂ����āA���W�A�������ׂ������̎����́A�킪���̊C�ݐ����炨���ނ˂Tkm�͈̔͂̊C��̂��̂Ɍ��邱�ƂƂ���B�������A���C�A���p�Ɋւ�����̂͂��̂��ׂĂ����W�̑ΏۂƂ���B
(1)�@�v�����N�g��
48�N�x����52�N�x�܂ł̂T�P�N�Ԃ̃f�[�^�����W��������B
(2)�@�ꐶ����
���D�ꓙ�ɐ������鐶���Ɋւ�����̂ł����āA48�N�x����52�N�x�܂ł̂T�P�N�ԂɁA�̓D��܂��͕��`�g�@�ɂ��̏W���ꂽ���̂̃f�[�^�����W�A��������B
(3)�@�t������
�u�C�A��ݓ��l�H���ɕt�����Ă��鐶���Ɋւ�����̂ŁA48�N�x����52�N�x�܂ł̂T�P�N�Ԃɕ��`�g�@�A�ώ@���ɂ��L�^���ꂽ�f�[�^�����W�A��������B
(4)�@�咰��
�u�����p���搅�����茋�ʁv�A�u��v�����g�����������ʁv�A���̑��������A52�N�x�P�N�Ԃ̃f�[�^�����W��������B
(5)�@�ԁ@��
48�N�x����52�N�x�܂ł̂T�P�N�Ԃɔ��������Ԓ��ɂ��āA���̃f�[�^�����W�A��������B�i���j
�R�D�f�[�^�̎戵��
(1)�@�����Ƃ��ē�����̓��ꑪ��_�i���͍̏W�n�_�A�ȉ������j�ɂ����鑪�茋�ʂ́A�P�f�[�^�Ƃ��Ď戵���B
(2)�@������ɓ��ꑪ��_�łQ���̈ȏ㑪�肵�Ă���ꍇ�́A�������܂Ƃ߂ĂP�f�[�^�Ƃ��Ď戵���Ă��������Ȃ��B���̏ꍇ�A���ϒl�������ē��Y����_�̑���l�Ƃ���B
(3)�@�����Ɍ����A���ꑪ��_�łȂ��ꍇ�ł��A�f�[�^�̐��i�ɂ���ē��ꑪ��_�Ƃ݂Ȃ�����͈͓��̂Q�ȏ�̑���_�œ�����ɑ��肵�Ă���ꍇ�́A�������܂Ƃ߂āA�P�f�[�^�Ƃ��Ď戵���Ă��������Ȃ��B
���̏ꍇ�A���ϒl�������ē��Y����_�̑���l�Ƃ���B
�S�D�f�[�[�̐����i���j
(1)�@�v�����N�g��
���W���ꂽ�f�[�^�͕ʎ��U�u�v�����N�g���f�[�^�\�v�Ɏ��̂Ƃ��萮������ƂƂ��ɁA�̏W�n�_�̈ʒu��ʎ��Q�u�̏W�n�_�ʒu�}�v�ɂȂ炢�\������B
�A�@�̏W�n�_�̈ʒu
�e�̏W�n�_���Ƃɍ̏W�n�_�̊T���̈ʒu���킩��悤�ɁA�̏W�n�_����t���B
�i��A�����p�A�p�����A������͌��A�����C�݁j
�C�@�̏W�N����
���Y�f�[�^������ꂽ�N����
�E�@�D���
���Y�f�[�^�ɋL�ڂ���Ă���v�����N�g���̂��������A�A�����ꂼ��D�肷����̂P�`�R��̊w���B
�G�@�ȉ��Ɍf���鎖���ɂ��ẮA���Y�f�[�^���画������ꍇ�̂݃f�[�^�\�ɐ�������B
(�A)�@���b�ʁiml�^l�j
(�C)�@�̐��i�@�^ml�j
(�E)�@�̏W���@
�@���Y�f�[�^���A�v�����N�g���l�b�g�ɂ���Ă�����̂��A�̐��ɂ���Ă�����̂��̕ʁB
�v�����N�g���l�b�g�ɂ���Ă���ꍇ�̓l�b�g�̌^���B
(�G)�@�l�b�g�̖Ԗ�
�v�����N�g���l�b�g���g�p���Ă���ꍇ�́A�l�b�g�̖Ԗڂ̑傫���B�Ԗڂ̑傫���́A�\�P�̍����ɋ敪����B
�I�@���Y�f�[�^�̏o�T
���Y�f�[�^�����\����Ă���L�^�̏ꍇ�͕����ԍ��i�ʎ�11�u���쐬�v�́v�Ɍ�q�j�B
���\����Ă��Ȃ��L�^�̏ꍇ�̓f�[�^�ۗL�Җ��i���͕ۗL�@�֖��j�B
�@�\�|�P�@�v�����N�g���l�b�g�̖Ԗ�
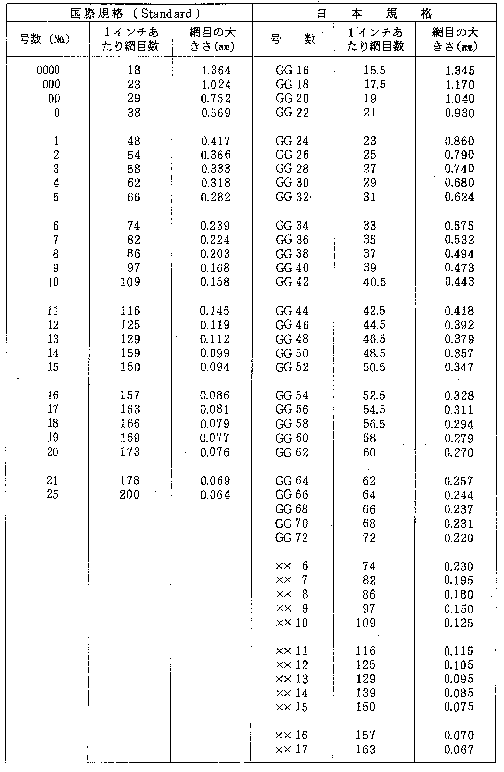
(2)�@�ꐶ����
���W���ꂽ�f�[�^�́A�ʎ��V�u�ꐶ�����f�[�^�\�v�Ɏ��̂Ƃ��萮������ƂƂ��ɁA�̏W�n�_�̈ʒu��ʎ��Q�u�̏W�n�_�ʒu�}�v�ɂȂ炢�\������B
�܂��A�V�Y�N�K�C�A�`���m�n�i�K�C�A���c�o�l�X�s�I�ACapitella�@Caoitata�S��̕��z��y�сu��������v��ʎ��R�u�C����萶�����z�}�v�ɂȂ炢�\������B
�A�@�̏W�n�_�̈ʒu
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
�C�@�̏W�N����
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
�E�@�D���
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B�������a����������̂ɂ��ẮA�w���y�јa���B
�G�@�ȉ��Ɍf���鎖���ɂ��ẮA���Y�f�[�^���画������ꍇ�ɂ̂݃f�[�^�\�ɐ�������B
(�A)�@�̏W�n�_�̐��[���͒���
���Y�f�[�^������ꂽ�ꏊ�̐��[���͒��ʁB
(�C)�@�ꎿ�̊T��
�̎悳�ꂽ�ꎿ�́A�\�Q�ɏ]���ċ敪����B
�\�|�Q�莿�̊T�v
|
�I ���@�@�I �� ���@�@�D �D |
(�E)�@�̏W�@��̎��
���Y�f�[�^���̓D��ɂ���Ă�����̂��A���`�g�ɂ���Ă�����̂��̕ʁB�̓D��ɂ���Ă���ꍇ�ɂ́A�G�N�}���o�[�W�^�A�X�~�X�}�c�L���^�C���^���A�̓D��̌^���B
(�G)�@�̏W�@��̑傫��
�̏W�@��i�̓D��y�ѕ��`�g�j�̑傫���i���R�~�^�ecm�j
(�I)�@���Y�̏W�n�_�ɂ�����V�Y�N�K�C�A�`���m�n�i�K�C�A���c�o�l�X�s�I�ACapitella Capitata�̐����̗L��
(�J)�@�����Q�ʎ��d�ʁA�̐��y�ь��̐�
�L�ށA�����ށA�b�k�ށA���їޓ��A�����Q�ʂ̎��d�ʁig�^�u�j�A�̐��i�@�^�u�j�y�т��̔䗦�B
���Y�f�[�^���Q�ȏ�̃T���v���̕��ϒl�ł���ꍇ�ɂ͌��̐��B
�I�@���Y�f�[�^�̏o�T
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
(3)�@�t������
���W���ꂽ�f�[�^�́A�ʎ��W�u�t�������f�[�^�\�v�Ɏ��̂Ƃ��萮������ƂƂ��ɁA�̏W�n�_ �̈ʒu��ʎ��Q�u�̏W�n�_�ʒu�}�v�ɂȂ炢�\������B
�܂��A�����T�L�C�K�C�̕��z�ɂ��āA�ʎ��R�u�C����萶�����z�}�v�ɂȂ炢�\������B
�A�@�̏W�n�_�̈ʒu
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
�C�@�̏W�N����
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
�E�@�D���
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B�������A�a����������̂ɂ��Ă͊w���y�јa���B
�G�@�ȉ��Ɍf���鎖���ɂ��ẮA���Y�f�[�^���画������ꍇ�ɂ̂݃f�[�^�\�ɐ�������B
(�A)�@�t���ꏊ
�������t�����Ă���ꏊ�i��@�u�C�A�R���N���[�g��݁A�e�g���|�b�g���j
(�C)�@�̏W���@
���Y�f�[�^�����`�g�ɂ���Ă�����̂��A�t���ɂ���Ă�����̂��A���̑��̊ώ@�ɂ� ���Ă�����̂��̕ʁB
(�E)�@���`�g�̑傫��
���`�g�A�t�����g�p���Ă���ꍇ�́A���̑傫���i���R�~�^�ecm�j
(�G)�@���Y�̏W�n�_�ɂ����郀���T�L�C�K�C�̕t���̗L��
(�I)�@�����Q�ʎ�ސ��A�핢�x�A���d�ʁA�̐�
�t�W�c�{�ށA�L�ށA�J���U�V�S�J�C�ށA�C���ޓ������Q�ʂ̎�ސ��A�핢�x�A���d�ʁig�^�u�j�A�̐��i �^�u�j�B
���Y�f�[�^���Q�ȏ�̃T���v���̕��ϒl�ł���ꍇ�ɂ͌��̐��B
�Ȃ��A�핢�x�͕\�R�ɂ��敪����B
�\�|�R�핢�x�敪�\
| �L�� | ��@���@�x�@��@�� |
| �T �S �R �Q �P �{ |
80�`100�����������B�@�@�@�̐��͔C�� 60�`80�����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� 40�`60�����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� 20�`40�����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� 20���ȉ����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� ����߂Ă킸�����������B�@�̐��͂����Ȃ� |
�I�@���Y�f�[�^�̏o�T
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
(4)�@�咰��
���W���ꂽ�f�[�^�́A�ʎ��X�u�咰�ۃf�[�^�\�v�Ɏ��̂Ƃ��萮������ƂƂ��ɑ���_�̈ʒu��ʎ��S�u�咰�ۑ���_�}�v�ɂȂ炢�\������B
�A�@����_�̈ʒu
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
�C�@����N����
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
�E�@�咰�یQ��
���Y����_�ɂ�����咰�یQ���i�l�o�m�^100ml�j�B
�Ȃ��A���Y����_�ɂ����ē�����ɂQ���̈ȏ㑪������Ă���ꍇ�́A���ϒl�A�ő�l�A�ŏ��l�A���̐��B
�G�@���Y�f�[�^�̏o�T
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
(5)�@�ԁ@��
���W���ꂽ�f�[�^�́A�ʎ�10�u�Ԓ������\�v�Ɏ��̂Ƃ��萮������ƂƂ��ɐԒ������ꏊ ��ʎ��T�u�Ԓ������C��}�v�ɂȂ炢�\������B
�A�@�����ꏊ
�Ԓ������������ꏊ�̊T���̈ʒu���킩��悤�ɁA�����ꏊ�ɖ��̂�t���B�i��@�����p�p �����A������͌����j
�C�@�����N����
�Ԓ��̔������m�F�����N�����y�ѐԒ����F�߂��Ȃ��Ȃ����N�����B
�E�@�p������
�Ԓ����p�����Ă��������B
�G�@�Ԓ��̎��
�Ԓ������������v�����N�g���̎�ށB
�Ԓ��̎�ނ͕\�S�ɂ��敪����B
�\�|�S�Ԓ��̎��
|
�Q�ږё��� |
�I�@���Y�f�[�^�̏o�T
�v�����N�g���̏ꍇ�ɏ�����B
(�ʎ��Q)�@�@�@�@�@�@�́@�W�@�n�@�_�@�ʁ@�u�@�}
(�̏W�n�_�ʒu�}��)
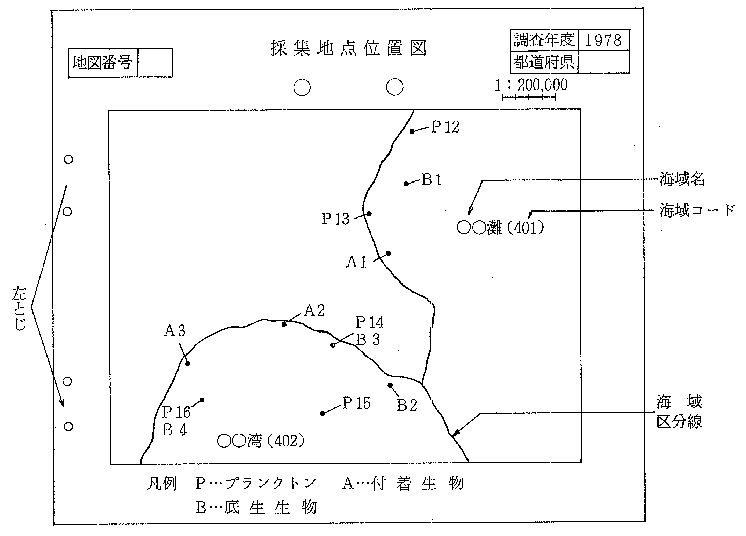
(�̏W�n�_�ʒu�}�쐬��̒��Ӂj�i���j
�P�D�̏W�n�_�ʒu�}�ɂ́A�K�����y�n���@���s��1�^20���n���}���g�p����B
���ʐ}�A�҂���}���͎g�p���Ȃ����ƁB
�Q�D1�^20���n���}�ɂ́A�s���{���P�ʂœ�������k�����ցu�n�}�ԍ��v��łB(�B�}(�ȉ��u�n�}�ԍ��}�v�Ƃ����B�j�Q�Ɓj
�R�D�̏W�n�_�ʒu�}��̂悤�ɒn���}�̗]���̏���̈ʒu�ɁA�u�^�C�g���v�A�u�n�}�ԍ��v�A�u�����N�\�v�i����j�A�u�s���{���v���L������B
�S�D���Y�n���}���ɂQ�ȏ�̊C�悪������ꍇ�ɂ́A��0.5mm�̍����i�ȉ��u�C��敪���v�Ƃ����B�j�ŊC����敪���A���ꂼ��̊C��ɁA�ʍ��u�R�[�h�ԍ��ꗗ�v���I��ŊY������C�於�A�C��R�[�h���L������B
�T�D�v�����N�g���A�ꐶ�����A�t�������̍̏W�n�_�����ɂ��\������B
(1)�@�̏W�n�_�͍��ۓ_�i�E�j�ł��̈ʒu�������B
(2)�@���ۓ_�̘e�Ƀv�����N�g���͂o�A�ꐶ�����͂a�A�t�������͂`�̋L����t���A�s���{�����Ƃɒʂ��ԍ��i�ȉ��u�̏W�n�_�ԍ��v�Ƃ����B�j��t���B
�i��j�o1�A�o2�A�o3�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�v�����N�g��
�@�@�@�a1�A�a2�A�a3�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�ꐶ����
�@�@�@�`1�A�`2�A�`3�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�t������
(3)�@����C��ɂ���̏W�n�_�̍̏W�n�_�ԍ��͘A�ԂƂ���B
(4)�@����n�_�Ńv�����N�g���A�ꐶ�����A�t�������������ɍ̏W����Ă���ꍇ�́A���ۓ_�͓���̂��̂Ƃ��A�̏W�n�_�ԍ��L����B
�U�D�̏W�n�_�ʒ��}��̂悤�ɁA�n���}�̗]���̏���̈ʒu�ɍ̏W�n�_�ʒu�}�̖}����L������B
�i�ʎ��R�j�@�C�@��@���@��@���@���@���@�z�@�}
�i�C����萶�����z�}��j
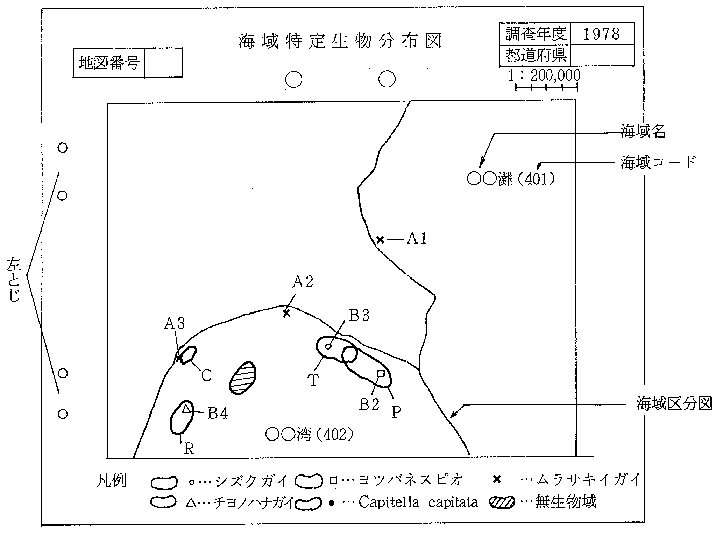
�i�C����萶�����z�}�쐬��̒��Ӂj
�P�D�C����萶�����z�}�ɂ͕K�����y�n���@���s��1�^20���n���}���g�p����B
���ʐ}�A�҂���}���͎g�p���Ȃ����ƁB
�Q�D�C����萶�����z�}��̂悤�ɒn���}�̗]���̏���̈ʒu�Ɂu�^�C�g���v�A�u�n�}�ԍ��v�A�u�����N�x�v�i����j�A�u�s���{���v���L������B
�R�D���Y�n���}���ɂQ�ȏ�̊C�悪������ꍇ�ɂ́A��0.5mm�̍����ŊC��敪���������A���ꂼ��
�̊C��ɕʍ��u�R�[�h�ԍ��ꗗ�v���I��ŊY������C�於�A�C��R�[�h���L�l����B
�S�D���������画�������V�Y�N�K�C�A�`���m�n�i�K�C�A���c�o�l�X�s�I�@Capitella�@Capitata�̕��z��y�і����������0.5mm�̍����ł�����A���̂悤�ɕ\������B
 �c�c�V�Y�N�K�C
�c�c�V�Y�N�K�C
 �c�c�`���m�n�i�K�C
�c�c�`���m�n�i�K�C
 �c�c���c�o�l�X�s�I
�c�c���c�o�l�X�s�I
 �c�cCapitella Capitata
�c�cCapitella Capitata
 �c�c��������
�c�c��������
�T�D�ꐶ�����f�[�^�\�y�ѕt�������f�[�^�\���A��L�S��̒ꐶ�����y�у����T�L�C�K�C���̏W����Ă���n�_������ꍇ�ɂ́A���̒n�_�̈ʒu�����̕����Ŏ����ƂƂ��ɁA���Y�f�[�^�\�Ɏ�����Ă���̓_�n�_�ԍ���t�L����B
���c�c�V�Y�N�K�C
���c�c�`���m�n�i�K�C
���c�c���c�o�l�X�s�I
���c�cCapitella�@Capitata
�~�c�c�����T�L�C�K�C
�U�D�C����萶�����z�}��̂悤�ɁA�n���}�̗]���̏���̈ʒu�ɁA���Y���z�}�̖}����L������B
(�ʎ��S)�@�@�@��@���@�ہ@���@��@�_�@�}
(�咰�ۑ���_�}��)
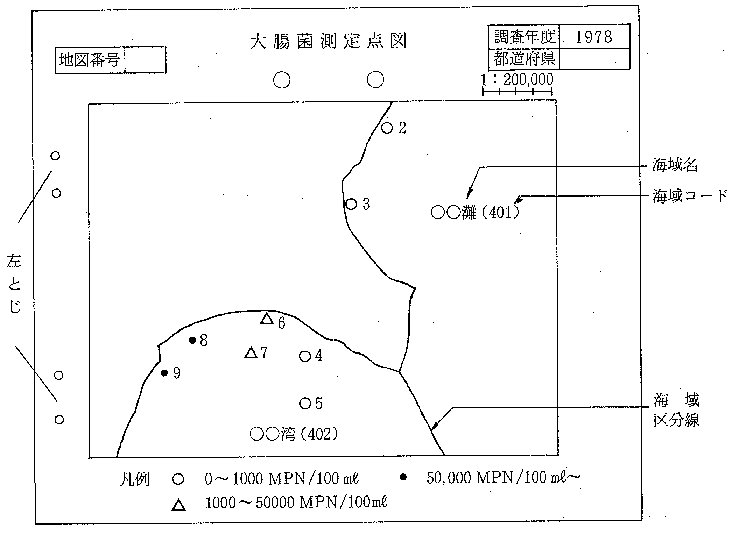
(�咰�ۑ���_�}�쐬��̒���)
�P�D�咰�ۑ���_�}�ɂ́A�K�����y�n���@���s��1�^20���n���}���g�p����B
���ʐ}�A�҂���}���͎g�p���Ȃ����ƁB
�Q�D�咰�ۑ���_�}��̂悤�ɒn���}�̗]���̏���̈ʒu�Ɂu�^�C�g���v�A�u�n�}�ԍ��v�A�u�����N�x�v(����)�A�u�s���{���v���L������B
�R�D���Y�n���}���ɂQ�ȏ�̊C�悪������ꍇ�ɂ́A��0.5mm�̍����ŊC��敪���������A���ꂼ��̊C��ɕʍ��u�R�[�h�ԍ��ꗗ�v���I��ŊY������C�於�A�C��R�[�h���L������B
�S�D�咰�ۂ̑���_�����ɂ��\������B
(1)�@�咰�ۂ̑���_�́A����(���A���A��)�ł��̈ʒu�������B�����͓��Y����_�ɂ�����咰��
�Q��(���W�f�[�^���̍ő�l)�ɂ���Ď��̂Ƃ���敪����B
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1,000�l�o�m�^100ml�ȉ�
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1,000�`50,000�l�o�m�^100ml
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@50,000�l�o�m�@100ml�����������
(2) ����_�̕����̘e�ɁA�s���{�����Ƃ̒ʂ��ԍ�(�ȉ��u����_�ԍ��v�Ƃ����B)��t���B
(3) ����C��ɂ��鑪��_�̑���_�ԍ��͘A�ԂƂ���B
�T�D�咰�ۑ���_�}��̂悤�ɁA�n���}�̗]���̏���̈ʒu�ɁA���Y����_�}�̖}����L������B
(�ʎ��T) �@�� �� �� �� �C �� �}
(�Ԓ������C��}��)
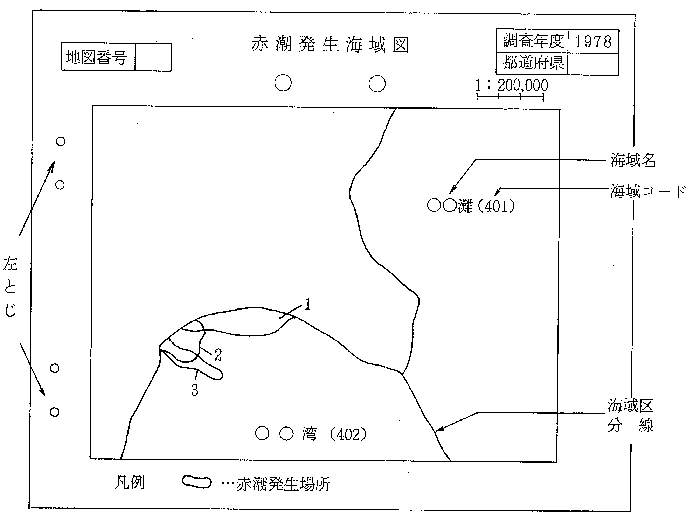
(�Ԓ������C��}�A�쐬��̒���)2
�P�D�Ԓ������C��}�ɂ́A�K�����y�n���@���s��1�^20���n���}���g�p����B
�Q�D�Ԓ������C��}�̂悤�ɒn���}�̗]���̏���̈ʒu�Ɂu�^�C�g���v�A�u�n�}�ԍ��v�A�u�����N�x�v(����)�A�u�s���{���v���L������B
�R�D���Y�n���}���ɂQ�ȏ�̊C�悪������ꍇ�ɂ́A��0.5mm�̍����ŊC��敪���������A���ꂼ��̊C��ɕʍ��u�R�[�h�ԍ��ꗗ�v���I��ŊY������C�於�A�C��R�[�h���L������B
�S�D���������画�����������ŁA���a52�N�x�P�N�Ԃɔ��������Ԓ������ꏊ����0.5mm�̍����ł�����B
�T�D�Ԓ������ꏊ�̘e�Ɂu�����ԍ��v(�ʎ�10�u�Ԓ������\�v�Ɍ�q)��t���B
�U�D�Ԓ������ꏊ���Q���ȏ�̒n���}�ɂ킽��ꍇ�́A�����ԍ����W���邷�ׂĂ̒n���}�ɋL����
��B
�V�D�Ԓ������C��}��̂悤�ɁA�n���}�̗]���̏���̈ʒu�ɁA���Y�C��}�̖}����L������B
(�ʎ��U)�@�v�����N�g���f�[�^�\
(�v�����N�g���f�[�^�\�l��)
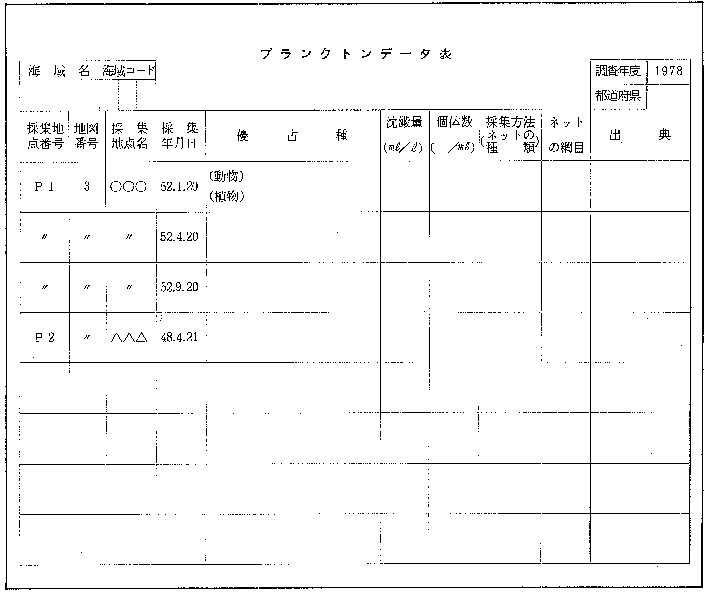
(�v�����N�g���f�[�^�\�L����̒���)
�P�D�f�[�^�\�̗l���͑O�łɌf������̂Ƃ��A�a�T���R��110kg�㑤�Q�c�������Ƃ���B
�Q�D�f�[�^�\�͊C�悲�Ƃɍ쐬���A�̏W�n�_�ԍ��̎Ⴂ���ɋL������B�f�[�^�̗ʂ������ꍇ�ɂ́A�f�[�^�\�͉����ɂ킽���Ă����������Ȃ��B
�R�D�u�C�於�v�u�C��R�[�h�v�ɂ́A�ʍ��u�R�[�h�ԍ��ꗗ�v���Y���̂��̂��L�l����B
�S�D�u�����N�x�v�u�s���{���v�ɂ́A�Y���̂��̂��L������B
�T�D�ȉ��P�̏W�n�_�̂P�f�[�^���ƂɎ��̂Ƃ���ɂ���B
(1)�@�u�̏W�n�_�ԍ��v�ɂ́A�̏W�n�_�ʒu�}�ƑΏƂł���ԍ����L������B
(2)�@�u�n�}�ԍ��v�ɂ́A���Y�̏W�n�_��������A1�^20���n���}�̔ԍ����L������B
(3)�@�u�̏W�n�_���v�ȉ��ɂ��ẮA�ʎ��P�u�C����������{�v�́v�́u4.�f�[�^�̐����v���Q�l�Ƃ��ċL������B
(�ʎ��V) �@�� �� �� �� �f �[ �^ �\
(�ꐶ�����f�[�^�\�l��)
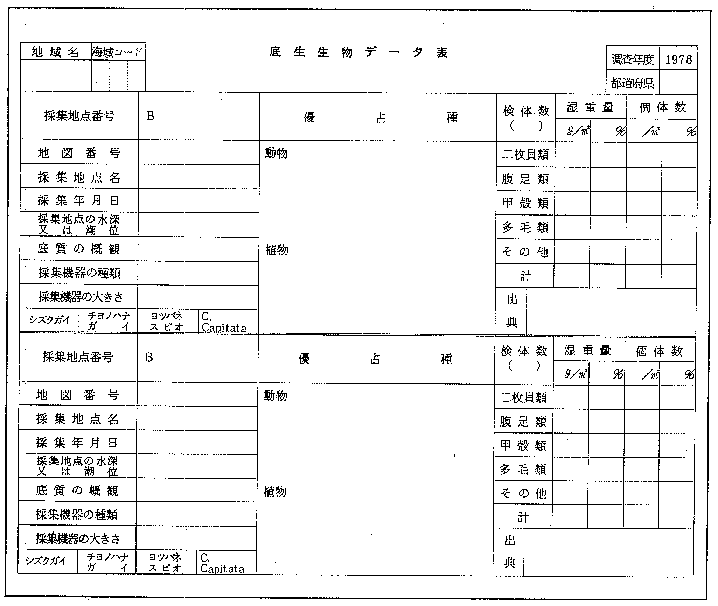
��1.�@�u�v�����N�g���f�[�^�\�L����̒��Ӂv�ɏ����ċL������B
��2.�@�u�V�Y�N�K�C�E�`���m�n�i�K�C�E���c�o�l�X�s�I�EC.Capitata�v�ɂ́A���Y�̏W�n�_�ɂ����č̏W����Ă���ꍇ�A�Y��������̂����ň͂ށB
(�ʎ��W)�@�@�@�@�t�@���@���@���@�f�@�[�@�^�@�\
(�t�������f�[�^�\�l��)
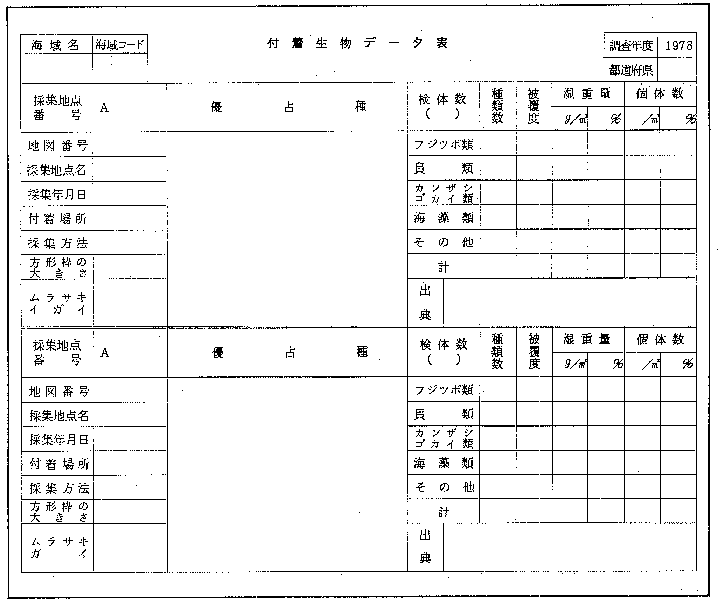
��1.�@�u�v�����N�g���f�[�^�\�L����̒��Ӂv�ɏ����ċL������B
(�ʎ��X)�@�@�@�@��@���@�ہ@�f�@�[�@�^�@�\
(�咰�ۃf�[�^�\�l��)
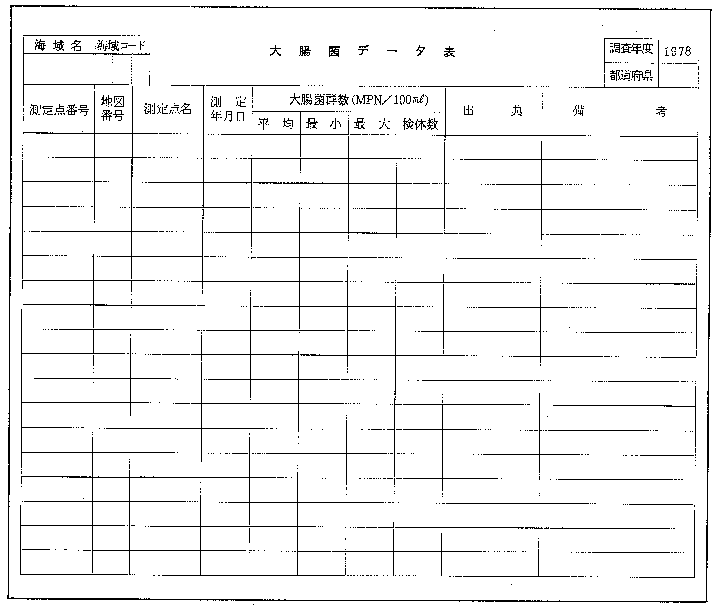
(�咰�ۃf�[�^�\�L����̒���)
�P�D�f�[�^�\�̗l���͑O�łɌf������̂Ƃ��A�a�T����110kg�㑤�Q�c�������Ƃ���B
�Q�D�f�[�^�\�͊C�悲�Ƃɍ쐬���A����_�ԍ��̎Ⴂ���ɋL������B�f�[�^�̗ʂ������ꍇ�ɂ̓f�[�^�\�͉����ɂ킽���Ă����������Ȃ��B
�R�D�u�C�於�v�A�u�C��R�[�h�v�ɂ́A�ʍ��u�R�[�h�ԍ��ꗗ�v���Y���̂��̂��L������B
�S�D�u�����N�x�v�A�u�s���{���v�ɂ́A�Y���̂��̂��L������B
�T�D�ȉ��P����_�̂P�f�[�^���ƂɎ��̂Ƃ���ɂ���B
(1)�@�u����_�ԍ��v�ɂ́A�咰�ۑ���_�}�ƑΏƂł���ԍ����L������B
(2)�@�u�n�}�ԍ��v�ɂ́A���Y����_��������A1�^20���n���}�̔ԍ����L������B
(3)�@�u����_���v�ȉ��ɂ��ẮA�ʎ��P�u�C����������{�v�́v�́u4.�f�[�^�̐����v���Q�l�Ƃ��ċL������B
(�ʎ��P�O)�@�@�@�ԁ@���@���@���@��@���@�\
(�Ԓ������\�l��)
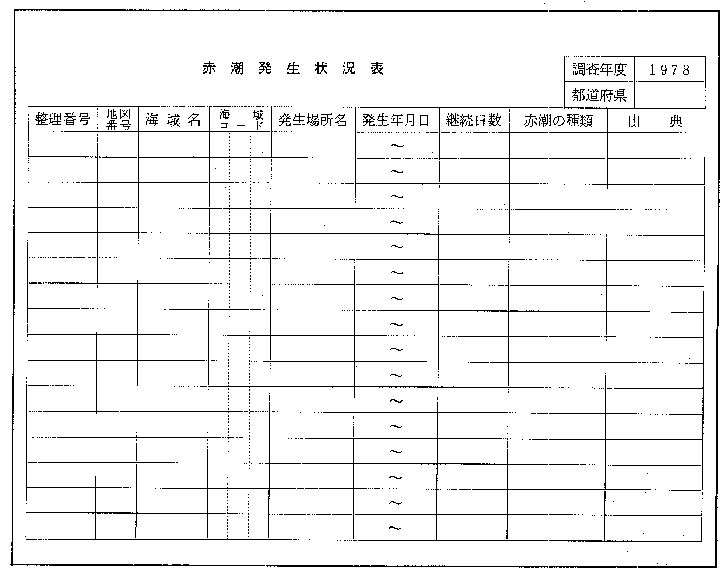
(�Ԓ������\�L����̒���)
�P�D�Ԓ������\�̗l���́A�O���Ɍf������̂Ƃ��A�a�T���R��110kg�㑤�Q�c�������Ƃ���B
�Q�D�Ԓ������\�́A�s���{�����Ƃɍ쐬����B�f�[�^�̗ʂ������ꍇ�ɂ́A�\�͉����ɂ킽���Ă����������Ȃ��B
�R�D�u�����N�x�v�u�s���{���v�ɂ͊Y���̂��̂��L������B
�S�D�Ԓ������\�ɂ́A�Ԓ��̔����P�����Ƃɔ����N�����̑������Ɏ��̂Ƃ���L�l����B
(1)�@�u�����ԍ��v�ɂ́A�Ԓ��̔����P�����ƂɂP����̒ʂ��ԍ����L������B
(2)�@�u�n�}�ԍ��v�ɂ́A���Y�����ꏊ��������1�^20���n���}�̔ԍ����L������B
(3)�@�u�C�於�v�u�C��R�[�h�v�ɂ́A���Y�����ꏊ��������C�於�A�C��R�[�h���A�ʍ��u�R�[�h�ԍ��ꗗ�v���I��ŊY���̂��̂��L������B�����ꏊ���Q�ȏ�̊C��ɂ킽��ꍇ�́A�C�於�A�C��R�[�h�L����B
(4)�@�u�����ꏊ���v�ȉ��ɂ��ẮA�ʎ��P�u�C����������{�v�́v���Q�l�Ƃ��ċL������B
���P�D�������́A���R���鎑�������ł����Ċ����f�[�^���ЍL�����W����悢�B���n�m�F�����͑S���K�v�Ƃ��Ȃ��B
���Q�D�Ԓ��Ɋւ��ẮA�f�[�^���W��48�`52�N�̂T�P�N���ɂ��Ď��{���邪�A�Ԓ������C��}��52�N�̃f�[�^�݂̂��g���č쐬����B
���R�D�v�����N�g���A�ꐶ�����A�t�������̊e�f�[�^�\�쐬�̏ꍇ�A�L�ڎ����̈ꕔ���������Ă���f�[�^�ł����Ă��A�A�@�̏W�n�_�̈ʒu�A�C�@�̏W�N�����A�E�@�D���̋L�ڂ�����A�G�@�ȉ��̃f�[�^���������Ă��Ă��A�K���f�[�^�\���쐬���邱�ƁB
���S�D�̏W�n�_�ʒu�}(�o�X�|20)���ɎG�ɂȂ�ꍇ�́A�v�����N�g���A�ꐶ�����A�t�������ʂɈʒu�}���쐬���Ă��������Ȃ��B���̏ꍇ�A���Ɋւ���ʒu�}�ł��邩�K�����L���邱�ƁB
| �@�L�� | �@��@���@�x�@��@�� |
| �@�T �@�S �@�R �@�Q �@�P �@�{ |
�@80�`100�����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� �@60�`80�����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� �@40�`60�����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� �@20�`40�����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� �@20���ȉ����������B�@�@�@�@�̐��͔C�� �@����߂Ă킸�����������B�@�̐��͂����Ȃ��B |
���T�D�C�悲�Ƃ̃f�[�^�\
�C�悲�ƂɎ��̏��Ńf�[�^�\���f�ڂ���B
(1)�@�v�����N�g���f�[�^�\�@(�̏W�n�_�ԍ��̏�)
(2)�@�ꐶ�����f�[�^�\�@�@�@(�@�@�@�V�@�@�@�@)
(3)�@�t�������f�[�^�\�@�@�@(�@�@�@�V�@�@�@�@)
(4)�@�咰�ۃf�[�^�\�@�@�@�@(����_�ԍ��̏�)
���U�D�Ԓ������\
�Ԓ������\���ԍ����Ɍf�ڂ���B
���V�D�������X�g
�������Ŏg�p���������ɂ��āA���̕\�ɂȂ炢�Ƃ�܂Ƃ߂�B