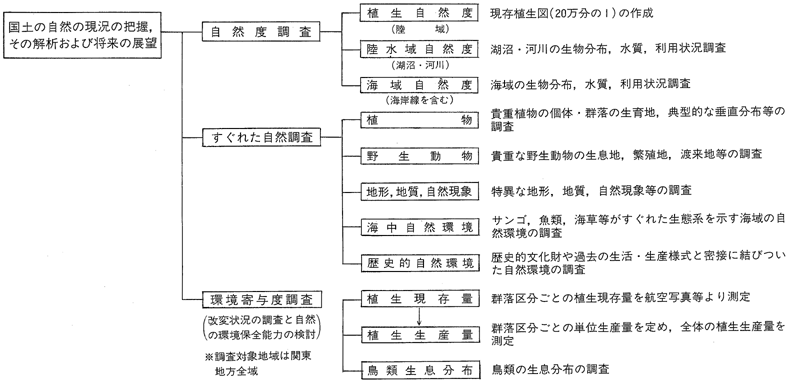
|
自然環境保全基礎調査の解説 |
||
|
|
||
|
この調査は、「自然環境保全法」第5条の「国はおおむね5年ごとに、地形・地質・植生および野生動物に関する調査、その他自然環境保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行なうようつとめるものとする」との規定に基づきおこなわれるもので、正式には自然環境保全基礎調査、一般に「緑の国勢調査」と呼ばれているものである。 第1回調査は、昭和48年度に実施され、その結果は、20万分の1の「現存植生図」、「植生自然度図」、「すぐれた自然図」および自然環境保全調査報告書等にとりまとめられ、49、50年度の2か年にわたり公表された。 第2回基礎調査は、53、54年度の2か年にわたり実施され、その結果は、5万分の1の「現存植生図」、20万分の1の「動植物分布図」および、各調査項目別の都道府県版や全国版の調査報告書にとりまとめられるとともに、調査全体の主要点を解説した第2回自然環境保全基礎調査報告書等にとりまとめられ、55、56年度にわたり公表された。 この「日本の自然環境」(自然環境アトラス)は、これら調査の結果を総合的に利用してつくられたものであり、この「緑の国勢調査」はわが国の自然環境の現況を総合的に知ることのできる一大調査である。
この2回にわたる「緑の国勢調査」の骨子は、つぎのようにまとめられる。
第1回自然環境保全調査骨子 |
||
|
|
|
第2回自然環境保全基礎調査骨子 |
|
|
|
1.基礎調査の目的と目標 この調査の目的は、1全国の植生、野生動物、地形、地質等、あるいは、これらが生息、存在する陸域、陸水域、海域の自然の状態を調査し、わが国における自然環境の現状を的確に把握する。2調査はおおむね5年ごとに実施し、その積み重ねによって長期的な視点から自然の時系列的な改変状況を把握する。3調査の結果を記録、保存するとともに、それらを公開することによって、自然環境のデータバンクとしての役割を果たす。4自然環境保全地域、自然公園、鳥獣保護区、保安林、天然記念物、近郊緑地保全区域等各種の自然保護計画、あるいは、環境アセスメントの実施、開発計画の立案に際しての基礎資料を提供することにある。 しかしながら、全国土にわたる、あるいは周辺海域の生物的環境や地質・地形的環境を調査・記録し、それらを集計解析して、わが国の自然環境の実態を容易に知ることができるようにするのは、大変困難なことである。そこで、ここ当面(今後20年間程度を見込む)は、行政の基礎資料としての必要性と現実に可能な調査能力とを考え合わせると、次のような点が目標とされるべきであろう。 (1)自然保護上重要な動植物に関する選定および評価基準を確立し、それに基づいた動植物リストを作成し、リストアップされた動植物の生息地と生息状態について把握されている。 (2)自然環境の基本情報図として、常に最新(5年以内)の縮尺5万分の1の植生図が整備されている。 (3)広域に生息する野生動物の分布および主要な動物の生息密度が把握されている。 (4)都市およびその周辺地域において、地域住民の快適な生活環境を維持するために必要な自然環境について明らかにした上で、それらの現状について把握されている。 (5)海岸、河川、湖沼の自然環境がどの程度人為的に改変されているかについて把握されている。また、これらのうち、人為により改変されていない、自然状態のままの地域のリストを作成し、保持する。 (6)すぐれた自然景観、古来自然への人間の働きかけにより形成されたわが国の風土を特徴づける歴史的自然環境や田園景観について把握している。 (7)以上の諸情報を体系的総合的に整理し、わが国における自然環境保全上重要な地域が明らかにされている。また、これらのデータが、行政機関だけでなく、国民一般が利用できるように公開されている。
2.第1回自然環境保全調査の概要 調査は、「自然度調査」、「すぐれた自然調査」、「環境寄与度調査」の3つの柱から成っており、それぞれの調査の目的および内容は以下のとおりである。 (1)自然度調査 国土を陸域、陸水域(湖沼・河川)、海域(海岸線とその地先海面)の三つの領域に区分し、自然環境の現況を調査し、その自然性を判定する。自然度とは、自然は人間の手の入り具合によって極めて自然性の高いものから自然性の低いものに至るまで、種々の階層に分かれて存在するという認識に立ち、それぞれの階層を示すために用いた概念であり、自然度調査はこの国土の自然の改変の度合を調査することを目的としている。 1 植生自然度 陸域については、植生を調査して自然度の判定をおこなう。このために、現存植生図を全国土にわたり作成し、これに用いられた凡例を人手の加わっている度合により10段階に分類する。このため、20万分の1の植物社会学的現存植生図を作成し、この植生図を元に植生に加えられた人間活動の影響を判定しその地域の自然度(植生自然度)とする。 2 陸水域自然度 陸水域は、湖沼と河川に分類される。湖沼については全国の代表的な64湖沼を選定し、(a)湖沼概要 (b)受水区域概要 (c)湖岸線の利用・改変状況 (d)水質等の理化学的性状 (e)生物分布についてデータを集める。また、河川については全国約40河川につき、(a)河川概要 (b)水質等の理化学的性状 (c)生物分布についてデータを集める。これらの資料をもとに、調査対象となった陸水域の自然性を判定する。 3 海域自然度 海域については、(a)水質(透明度およびC.O.D) (b)海岸線の利用・改変状況 (c)生物分布(貝類・海草類などの地区別分布および漁獲量)につき、各都道府県の沿岸地先海域全域につきデータを収集する。これらの資料をもとに、全国の海域の自然性を判定する。 (2)すぐれた自然調査 「すぐれた自然」の調査は、植物、野生動物、地形・地質・自然現象、海中自然環境、歴史的自然環境など5つの項目について、全国を対象として稀少性、固有性、特異性という視点から、すぐれた自然がどこにどのような状態で残されているかを調査する。 1 植物 植物については、(a)貴重な個体植物(b)貴重な群落に分けて調査する。(a)については、(ア)日本特産または地方特産(イ)稀産種(ウ)世界または日本における南限または北限(エ)その他重要な種について調査をおこなう。(b)については、(ア)各種の群落がまとまっている地域、典型的な垂直分布をなし、貴重と認められるもの(イ)自然性、稀少性の高いもの(ウ)その他重要なものについて調査する。 2 野生動物 野生動物については、(a)日本特産種(b)稀産種(c)世界または日本において南限または北限種(d)その他重要な個体群である哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類(淡水産)、昆虫類の生息地(繁殖地を含む)、渡来地(鳥類)をプロットし、生息状況等について調査する。 3 地形・地質・自然現象 地形・地質・自然現象については、環境庁が示した事例のうちから(a)典型的なもの(b)稀少なもの(c)学術的に貴重なもの(d)その他重要なものにつき調査する。 4 海中自然環境 海中自然環境の調査は、対象区域を当該都道府県地先海域のうち、主として水深20メートル以下の浅海、潮間帯を対象に、熱帯魚、サンゴ、海草、その他これらに類する動植物および海中地形等の自然環境がすぐれた状態を維持している海域であって、海域の水質が汚染されていないこと、海中地形に変化があり、海中動植物が豊富で、かつその種類が多いこと等の基準に合致したものを調査する。 5 歴史的自然環境 遺跡、歴史的建造物等の歴史的文化財や、過去の生活生産様式と密接に結びつき、これらと一体をなす歴史的風土としての自然環境を形成しているもの、たとえば歴史的文化財と一体となった自然林等のすぐれた自然環境を調査する。 (3)環境寄与度調査 環境寄与度調査は、人間活動が著しく、しかも各種の環境タイプが見られる広域的なモデル地域として関東地方を対象とし、緑の量がどの位あるかという植生現存量と、その緑が年間あたり有機物をどれだけ生産しているかという植生生産量を調査する。これは植生が人間環境の保全にどの程度の寄与をしているかを検討する基礎的なデータを整備する目的でおこなった調査である。また、あわせて、鳥類生息分布調査をおこなう。
3.第2回自然環境保全基礎調査の概要 調査は、「陸域」、「陸水域」、「海域」の地域に分けておこなわれており、各地域の自然環境を調査するため、10の調査が柱となっている。調査は2年度にわたりおこなわれたが、53年度に実施された調査は、「特定植物群落調査」、「動物分布調査」、「海岸調査」、「干潟・藻場・サンゴ礁分布調査」、「海域環境調査」、「海域生物調査」の6調査であり、54年度に実施されたものは「植生調査」、「表土改変状況調査」、「湖沼調査」、「河川調査」の4調査である。それぞれの調査の目的および内容は以下のとおりである。 (1)植生調査 植生図は、自然の保護、管理、復元のための生態学的処方箋としてまた、国土計画、地域開発、産業立地等のための自然診断図として重要な基礎図であり、各種の保護、開発のマスタープラン作成に不可欠な資料として重要である。 この調査は、全国の植生の現況をより詳細に把握するとともに、地域レベルの計画に対応できる植生図を全国的に整備するためのものである。国土の約2分の1の地域について、現地調査および空中写真の判読等により、縮尺の5万分の1の現存植生図を作成する。 (2)特定植物群落調査 この調査は、わが国における植物群落のうちで、学術上重要なもの、保護を必要とするものなどを、つぎに示す選定基準により都道府県ごとに選定し、その生育地および生息状況について調査する。 特定植物群落選定基準 A……原生林もしくはそれに近い自然林 B……国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群 C……比較的普通にみられるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群 D……砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの E……郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの F……過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないもの。 G……乱獲その他人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群。 H……その他、学術上重要な植物群落または個体群。 (3)動物分布調査 この調査は、わが国に生息する野生動物の生息状況を把握するため、哺乳類、鳥類、両生類・は虫類、淡水魚類、昆虫類を対象として、その分布の把握を中心としている。それぞれの調査内容はつぎのとおりである。 1 哺乳類 わが国に生息する大型および中型獣8種(ニホンザル、シカ、ツキノワグマ、ヒグマ、イノシシ、キツネ、タヌキ、アナグマ)の分布について調査する。 2 鳥類 わが国で繁殖の知られている約250種の鳥類を対象として、繁殖期における分布について調査をする。 日本野鳥の会の協力により、2,225地点の調査コースにおいて現地観察を実施した。また、1,100地点における繁殖状況の資料を収集した。 3 両生類・は虫類 絶滅のおそれのある種、学術上重要な種等つぎに示す種を対象として、生息地(分布)および生息状況を調査する。
両生類・は虫類調査対象種 〈両生類〉
〈は虫類〉
4 淡水魚類 絶滅のおそれのある種、学術上重要な種等つぎに示す種を対象として、生息地(分布)および生息状況を調査する。
淡水魚類調査対象種
(注)イトヨは陸封型と降海型のものを区別する。
5 昆虫類 絶滅のおそれのある種、学術上重要な種等の生息地(分布)および生息状況を調査する。 調査の対象となった昆虫は、つぎに示す指標昆虫類10種および選定基準により都道府県ごとに選定された特定昆虫類(都道府県ごとに50〜100種程度)である。
指標昆虫類調査対象種
特定昆虫類調査対象種選定基準 A……日本国内では、そこにしか産しない種 例 ミヤジマトンボ(広島県宮島) イイジマルリボシヤンマ(北海道釧路) ヒメチャマダラセセリ(北海道アポイ岳) B……分布域が国内の若干の地域に限定されている種 例 ミヤマモンキチョウ ルーミスシジミ C……比較的普通種であっても、北限・南限等分布限界になる産地にみられる種 例 広島県におけるナガサキアゲハ 静岡県におけるクロコノマチョウ D……当該地域において絶滅の危機にひんしている種 E……近年当該地域において絶滅したと考えられる種 F……業者およびマニアなどの乱獲のため、当該地域での個体数の著しい減少が心配される種 G……環境指標として適当であると考えられる種
(4)表土改変状況調査 この調査は、関東地方(1都6県、島しょ部は除く)における表土の改変状況を昭和20年頃、35年頃、50年頃の戦後の3時期において調査することにより時系列的に表土の改変の実態を明らかにしようとするものである。 調査方法は、空中写真の判読を主に、その他資料をも活用し、基準地域メッシュ(約1×1km)ごとに、つぎに示す表土区分を判定する。 表土区分
(5)湖沼調査 天然湖沼の自然性の消失を監視し、その保全を図るために、全国の天然湖沼487を対象にして、湖沼概要、水質の総合指標でありそれ自体価値の高いレクリエーション資源でもある透明度、湖沼の改変状況等を調査したものである。また、代表的な61湖沼については魚類相についても調査する。 (6)河川調査 河川の自然性の現況および利用の状況を把握するために、全国の112の1級河川および沖縄県浦内川の幹川を対象として、魚類の生息状況および河川の改変状況等について調査する。また、集水域全体が原生状態を保っている河川(「原生流域」)は、わが国ではごくわずかに残されているにすぎないと思われるため、早急に保全対策を講じる必要から、これらの地域のうち1000ha以上の大規模なものの摘出をおこなう。 (7)海岸調査 海岸が人為によりどのように改変されてきているかをみるために、海岸汀線および海岸陸域の自然状態を調査する。 (8)干潟・藻場・サンゴ礁分布調査 干潟・藻場・サンゴ礁のわが国における分布状況を把握するため、位置、面積、タイプ、環境の現況等について調査する。 干潟は、1945年以後に、藻場・サンゴ礁は、1973年以降に人為的に消滅したものについても、調査対象とし、消滅面積、時期、理由、現況土地利用等について調査する。 (9)海域環境調査 生物の生息状況からみた、わが国の沿岸域の現状を把握するために、あらかじめ区分した91の海域ごとに、プランクトン、底生生物、付着生物、大腸菌、赤潮の発生状況について調査する。 (10)海域生物調査 わが国の海岸域における生物の生息状況および生息環境を今後5年ごとにモニタリングするため、潮上帯(飛沫帯)および潮間帯に生息する生物を調査する。 |