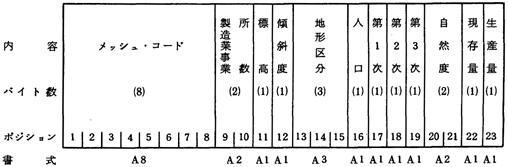
7.自然環境と社会環境の要因分析
前章6の環境寄与度調査は、わが国でも最も人口が集中し、人間活動の活発な関東地方に焦点を合わせ、とりあえず植生現存量、植生生産量及び鳥類生息種類数の調査を行った。ここではこのデータに合わせて植生自然度その他の自然的要因及びいくつかの社会的要因を取りあげ、これらの要因間の相関関係を分析することによって、自然と人間活動との係りあいをさぐる試みを行おうとするものである。
関東地方-茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
以上の1都6県約32,000km2分析対象地域として設定する。
分析のための要因設定に当っては、データの有無等の理由から自然的要因として、植生自然度、植生現存量、植生生産量、標高、傾斜度、地形区分が選定され、社会的要因としては人口、産業別就業人口(第1次、第2次、第3次)及び製造業事業所数が選択された。
各データは、分析のためにつぎのような処理を行った。
a 植生自然度
|
ランク |
分 類 基 準 |
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 |
市街地、造成地、裸地 畑地、水田、緑の多い住宅地 果樹園、桑園、茶畑など シバなどの背丈の低い草原 ササ、ススキなどの背丈の高い草原 |
6 7 8 9 10 |
植林地、造林地など ミズナラ、クリ、コナラなどの二次林 ブナ、シイ、カシなどの再生林 エゾマツ、トドマツ、ブナなどの自然林 自然草原、湿原 |
b 植生現存量
|
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 6 |
t/ha 2以下 3~ 5 6~15 16~30 31~99 100以上 |
c 植生生産量
|
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 |
t/ha/year 2.0以下 2.1~ 6.0 6.1~11.0 11.1~16.0 16.1以上 |
d 標 高
等経緯度法による一辺約1kmの標準地域メッシュ対角線の交点の標高を読み取る(資料:国土地理院「5万分の1地形図」)。
|
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
100m未満 100~ 200 200~ 400 400~ 700 700~1,000 1,000~1,500 1,500~2,000 2,000以上 水 面 |
e 傾 斜 度
上記標準地域メッシュにおいて、最高点と最低点を読みとり起伏量を算出し、それがメッシュの辺長(約1km)に対して作る勾配をもって傾斜度αを定義した。すなわち、
tanα=起伏量/辺長
である。なお傾斜度のランク分類に際しては、土地分類図の基準に拠った(資料:同上)。
|
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
3°未満 3°~ 8° 8°~ 15° 15°~ 20° 20°~ 30° 30°~ 40° 40°以上 水 面 |
f 地 形 区 分
標準地域メッシュ内において占有面積の多いものを代表地形とした(資料:茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県については国土庁「20万分の1土地分類図」、東京都・神奈川県については国土地理院「2万5千分の1土地条件図」)。
|
ランク |
分 類 基 準 |
||
|
大分類 |
中分類 |
小分類 |
|
|
110 120 130 140 210 220 230 240 310 320 330 411 412 413 414 421 422 423 424 431 510 520 530 610 710 888 |
山 地
火 山 地
丘 陵 地
台 地
低 地
人口改変地 水 面 データなし |
大起伏山地 中起伏山地 小起伏山地 山麓地 大起伏火山地 中起伏火山地 小起伏火山地 火山山麓地 大起伏丘陵地 小起伏丘陵地 火山性丘陵地 砂礫台地 砂礫台地 砂礫台地 砂礫台地 ローム台地・段丘 ローム台地・段丘 ローム台地・段丘 ローム台地・段丘 岩石台地 扇状地性低地 三角洲性低地 自然堤防、砂洲 埋立地、干拓地
|
上 位 中 位 下 位 混 合 * 上 位 中 位 下 位 混 合 *
|
* 「混合」は上中下位の判別が困難なもの
g 人 口
総理府統計局の作成した「国土総合実態統計(地域メッシュ統計)」の人口階級区分に従う場合、分析対象地域内で人口階級分布に大きな偏りが発生する。人口は社会環境因子の代表的なものである。そこで、さまざまな相関集計にたえられるよう、人口階級別分布を平均化し、そのうえで上記総理府区分との対応が可能なように各ランクの分類基準を設定した(資料:総理府「昭和45年国土総合実態統計」)。
|
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
0人 100人未満 100~ 200人 200~ 500 500~ 1,000 1,000~ 2,000 2,000~ 5,000 5,000~ 10,000 10,000以上 |
h 第1次産業就業人口
gに同じ
|
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
0人 15人未満 15~ 30人 30~ 50 50~ 100 100~ 150 150~ 200 200人以上 |
i 第2次産業就業人口
gに同じ
|
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
0人 20人未満 20~ 50人 50~ 100 100~ 200 200~ 500 500~1,000 1,000~2,500 2,500人以上 |
j 第3次産業就業人口
gに同じ。ランク、分類基準はiに同じ。
k 製造業事業所数
階級区分については、g~jと全く同じような配慮を行った(資料:総理府「昭和44年事業所統計調査」)。
(注)人口・産業別就業人口は、総理府「地域メッシュ統計磁気テープ」よりテープ・コピーを行い、欠落部分を「地域メッシュ統計プリント」より補完した。また、製造事業所数は、地域メッシュ統計プリントよりカード化を行った。
|
ランク |
分 類 基 準 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
0 1 2 3,4 5,6 7,8,9 10~19 20~49 50~99 100以上 水 面 データなし |
a ブロッキング
40レコード/ブロック、80バイト/レコード
b レコード形式
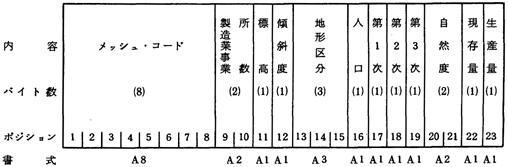 |
(注)製造業事業所数以下のフィールドにセットされる値はすべてランク値である。
選定された諸要因のうち、地形区分及び植生自然度は数値的に分析が可能なものではなく、従って他の要因についても、これらに合わせるためランク分けして相関分析を行った。要因間の関連の強さを測定するためにここではクラマーの関連係数Crを使用した。
地形区分及び植生自然度以外の要因は数値的なものからなっており、例えば人口集積と植生現存量との要因分析では回帰分析を使うなどしている。
|
クラマーの関連係数(Cramer's coefficient of contingency) この係数はs×tの相関数(s>t)において |
|
|
Cr = φ2/(t-1) = (x2/n) / (t-1) |
|
|
で定義される。これは定義によって無関連のとき0、完全関連において1の値をとる。即ち、係数が1に近い程、両要因間の関連が強いといえる。本分析では、クラマー係数のオーダーを他のコンティンチェンジエンシィ係数のそれとあわせる意味から、平方根をとっている。 |
|
植生に関する要因(自然度、現存量、生産量)と自然環境あるいは社会環境の各要因との関連を逐次把握するに先立ち、まず抽出した全要因(11要因)の相互関連の総括的な考察を試みた。関連性の指標としてはクラマーの関連係数を用いた。これによって各要因相互の関連性の相対的評価が可能となる。係数算出の結果は表40のとおりである。人口と第2次あるいは第3次産業就業人口、現存量と生産量などの関連がもっとも強くなっている。全般的に類似的性格の要因間での関連性が強くなっていることが理解される。これにたいして製造業事業所数と標高、傾斜度、第1次産業就業人口などとの関連、あるいは生産量と第1次産業就業人口との関連などが低くなっている。このように関連性の強弱に着目するとおよそ三つのクラスター(要因のグループ)が抽出される(図35)。いずれのクラスターも類似的性格の要因から構成されており、それらは自然環境植生関連クラスター、自然環境地形関連クラスター、社会環境人口関連クラスターなどと名づけることができる。
表41は11要因を植生的環境、地形的環境、社会的環境とに分類したとき、それぞれの環境にたいして11要因が持っている関連の強さあるいは説明力を把握したものである(作表にあたっては適宜関連係数を相加平均した)。この表によれば、まず植生的環境要因では現存量が自然環境と社会環境のいずれにも関連性が強いといえる。地形的環境要因では標高が自然環境にたいして強い関連性をもつが、社会環境にたいしては地形区分がまさっている。また社会環境要因のうちで自然環境、社会環境への影響度を把握するときはいずれも人口が有効である。人間の活動形態にかかわる指標(産業別就業人口、製造業事業所数)は、人口に比べれば関連性が弱い。また自然環境のうち人口と強く関連するものは地形的環境ではなく植生的環境である。自然度、現存量、生産量という植生的環境の把握の可能性は人口がもっとも秘めているといえよう。
環境における11要因相互の関連のなかで、開発と緑(植生)との関連にしぼって検討するとき、現存量と人口に着目する必要があろう(表40)。というのは、開発行為などによる社会環境の状態変化は、植生環境の面では植生現存量の変化として現象し、他方緑の量の多寡は社会環境要因のうちでは人口によってもたらされるからである。しかし後者の場合、植生との関連性は社会環境要因としての人口よりも、標高、地形区分など地形的環境の方が事実上強く、より説明力をもっていると考えられる点は留意を要する。
植生的環境における3要因のなかで、自然度を用いる分析では10段階の自然度に加えて、これらを適宜組み合わせたマクロな相観的植生のカテゴリーを考え、理解を深める手だてとした。このカテゴリーを仮りに植生分類とよぶとすれば以下のようになる。
|
植 生 分 類 |
1 緑 地(率) |
:自然度2~10の植生 |
(全メッシュに占める比率) |
|
2 草 地(率) |
:自然度2,4,5,10の植生 |
( 〃 ) |
|
|
3 農 地(率) |
:自然度2,3の植生 |
( 〃 ) |
|
|
4 天然林地(率) |
:自然度7~9の植生 |
( 〃 ) |
|
|
5 植 林 地(率) |
:自然度6の植生 |
( 〃 ) |
|
|
6 自然植生(率) |
:自然度9、10の植生 |
( 〃 ) |
|
|
7 可住地(率)Ⅰ |
:自然度1~3の植生 |
( 〃 ) |
|
|
8 可住地(率)Ⅱ |
:自然度1~5の植生 |
( 〃 ) |
現存量は自然度6、7、8、9など木本性の植生地域と自然度2、4、5など草本性の植生地域とで大小二分される(図36)。木本性の自然度のなかでは自然度9の自然林の現存量の高さが目立つ。植林地域(自然度6)は二次林地域(自然度7)をやや上回っている。自然度3の果樹園、桑園、茶園などは木本性の植生でありながら、その現存量は草本性のものに近い。自然度ランクがしめすとおり人為的な生長抑制が強いのであろう。
自然度と生産量の関連は図37となる。生産緑地として人為的に生産量拡大を意図する地域(自然度2、3、6)では高い数値をしめし、林地(同7~9)をほぼ上回っている。したがって自然度と現存量にみられるような自然度の高まりに対応した現存量の増加傾向はここではうすい。自然度10の自然植生は、現存量では自然度1の市街地につぐ低い数値でありながら、生産量では自然度ランク内で最高値となっている。これは生産原単位の高い自然植生の群落の立地によるものであろうが、農地、植林地の生産量よりもはるかに上回っており検討を要する問題である。
現存量と生産量との関連は図38のように、相互にほぼ指数関数的な増加傾向をしめしている。しかしこれらの数値的関連は生産量各ランクの階級値をもとに算出した平均的な結果であって、厳密にいえば現存量と生産量との対応ではばらつきが大きい。例えば現存量50~100tあたりで生産量の落ち込みがみられるが、これはこの区間で優勢な分布をする自然度7~9の林地植生が自然度2、4の草本性の植生に比して現存量でははるかに上回っているが(図36前掲)、生産量では逆転していることによるものであろう。また、ともに人為介入の強いものとして自然度6(植林地)や2(農地)があげられるが、これらは生産量ではほぼ近似しているが(図37前掲)、現存量では格段の差がある(図36前掲)。このように現存量、生産量とも人為の影響が強く、なかでも生産量では農地や植林地などがまったく意図的に生長制御されるものであるため、実際の相関性は端的には把握しがたい面がある。
ⅰ)自然度と標高
自然度と標高との関連は図39のとおりである。
自然度10の地域を除けば、標高は自然度の高まりにつれて増加している。しかも増加は段階的であるのが特徴である。すなわち自然度は標高によって自然度1~3、同4~7、同8、9の3階層に分割されよう。自然度1~3はその平均的標高が100m以下の地域を中心に分布するいわば低標高地的自然度である。自然度4~7は500mを中心に分布する中標高地的自然度、自然度8~9は1000m以上の高標高地的な自然度といえよう。自然度10の標高が特異であるのは、該当する植生の群落が標高1500m以上(13.1%)あるいは100m以下(73.8%)という両極端の地域に分かれて立地していることによるものであろう。
植生分類と標高との関連は表42に示したような結果である。この表をグラフ化したものが図40である。
緑被地率の伸びはほぼ500mまでで100%近くを占めてしまい、それより高い所ではほぼ一定している。草地、農地あるいは可住地など草本性の植生域は500m付近でいずれも10%前後に落ち込んでいる。300~500mにかけての天然林地率の減少は、この地域での木本性の植生では植林が優勢に分布することによろう。標高300mまでの地域では植林地よりも二次林を主とする林地が優勢である。自然植生は500mあたりまでは上下変動があるが、これを超えると安定的な増加をみせはじめ、1000mあたりからとくに顕著な増加となっている。全般的にみれば、標高500m付近がこれらの植生分類にとって、分布の伸びの大きな特徴をしめす屈折点となっていることが注目されよう(緑被地率・植林地率、草地率、可住地率Ⅰ・Ⅱなど)。
ⅱ)自然度と傾斜度
自然度と傾斜度との関連は図41にあらわされている。自然度と標高との関連でみられたように傾斜度も自然度の上昇につれて高くなる。この増加現象も段階的であり、平担地的自然度、緩傾斜地的自然度、急傾斜地的自然度の3区分がおおむね考えられる。平担地的自然度は1~3、緩傾斜地的自然度は4~8、急傾斜地的自然度は9となる。自然度8,9などの良好な自然は居住性の乏しい(開発のおよびにくい)傾斜地域に残存していることが推察される。これにたいして自然度10では臨海部や河川沿いなどの平担地に多くみられるために、立地の平均的傾斜度は低くなっており、自然度9の自然林とは同じ自然植生でも対照的な立地をみせている。
植生分類と傾斜度の関連は表43もしくは図42のとおりである。緑被地率は10度をこえるとほぼ全域をおおう。植林地は15~20度の地域で分布のピークをしめし、それ以上の傾斜となると非植林地である天然林地にとってかわる。総じて植生分類と傾斜度では15~20度が分布の屈折点として特徴的である(緑被地率、草地率、農地率、植林地率、可住地率Ⅰ・Ⅱなど)。
ⅲ)自然度と地形区分
自然度及び植生分類と地形区分との関連は表44、表45のクロス集計であらわされている。一般に人口の定住は台地、低地、人工改変地に集中するが(本調査対象地域ではこの3地域で91.9%の人口を占める)、これらの地域ではいずれも木本性の植生に乏しい。とくに天然林地(自然度7~9)が貧弱であり、人々の日常生活圏における緑との接触度は希薄である。また自然度9、10の自然植生は山地よりも火山地(日光、草津・白根)において高い分布率をしめしている。
ⅰ)自然度と人口
自然度と人口との関連は図43のとおりである。自然度4、5、10等の特異な地域もあるが、総じて人口の増加は自然度の低下と相関関係にあるといえる。自然度4、5の草地では、それより低位にあたる自然度2、3の農地よりも人口が上回っているのが注目される。また自然度7の二次林地の人口は6の植林地におけるそれよりも多少高い。自然度10の地域は最高自然度にもかかわらず、その人口の多さがめだつ。“自然度と地形的環境(標高、傾斜度、地形区分)との関連”でも推察されたように、自然植生のなかでも多層構成の植生(自然度9)は高地や急傾斜地などきびしい居住環境のなかで立地しているのにたいして、単層構成の植生(自然度10)は高地と低地とに立地を分けている。とくに低地では埋立地や河川流域などにあって人口集落や工場と近接・混在した立地となっており、そのために人口は高い数値となったのであろう。
植生分類と人口との関連は表46あるいは図44に示したとおりである。緑被地率は人口の増加にともない確実に低下しており、人口4000人/km2あたりで50%に減少する。農地率は人口の高密地域から低密地域にかけて増加してゆくが、500~1000人/km2の地域をピークにして以後減少しはじめ、天然林地や植林地にとってかわる。天然林地率、植林地率をみると、人口のきわめて希薄な地域(0~100人/km2)では植林が天然林地を上回っているが、100人あたりでほぼ等しくなり、以後高密な地域にかけて同様な分布構成をしめしている。とくに天然林地についてみれば、人口が500人/km2を超えると10%の確保も困難になることが理解される。ちなみに都市規模だけでいえば、平均人口密度500人/km2は盛岡、秋田、山形、鳥取などが該当する。また関東1都6県149市のうちの約80%にあたる119市においてその平均人口密度は500人/km2を上回っている。以上の結果を敷衍すれば大都市近効はもちろん、地方の中核的な都市であっても、都市林あるいは郷土林としての大規模な林地の確保は容易でないことが示唆される。
ⅱ)自然度と産業別就業人口
自然度と産業別就業人口との関連は図45及び図46に示したとおりである。前者は自然度別就業人口の実数値であり、後者はこれを自然度別の就業人口構成比にあらためたものである。第1次産業就業人口では自然度2、3の農地で人口の実数が高くなっているが、構成比でみれば自然度8の地域が上回っている。第2次産業就業人口では実数はまちまちであるが、構成比をとるといずれの自然度においてもほぼ40%と一定しており、自然度の高まりによる構成比の減少傾向はみられない。工場の内陸部進出、食料品や製材など第1次産業と密接な業種工場の立地あるいは通勤圏の拡大なども原因していると推察されるがつまびらかでない。第3次産業就業人口でも同様なことが指摘できる。すなわち自然度増加による構成比の減少傾向は少ない。高位自然度地域でも第3次人口比が高いのはサービス業をはじめとする観光レクリェーション産業の立地によるものであろうか。
ⅲ)自然度と製造業事業所数
自然度と製造業事業所数の関連は図47に示したとおりであり、ほぼ第2次産業就業人口との関連(図45、図46前掲)と対応している。自然度4、5の地域は人口あるいは第2次、第3次産業就業人口などの点でいずれも自然度2、3の農地を上回っていた。製造業事業所数についても、やはり、このような関係がみられる。つまりこの地域は自然度の観点からすれば特異な地域といえよう。この地域を具体的に地図上でみれば高標高の山地にももちろんみられるが、低標高地域におけるゴルフ場などのレクリェーション地あるいは平担低地の堤内地などにも存在しており、集落や工場などと混在している。農業を除いた開発的指標(人口、就業人口、製造業事業所数)が高くなるのはこうした理由によるものであろう。
ⅰ)現存量と標高
現存量と標高との関連は図48のとおりであり、現存量の増加は標高の高まりに対応している。とくに標高1,500~2,000mにかけての現存量の伸びが顕著であり約2倍となっている。この地域では現存量の多い木本性の群落が優勢であり、かつ植林よりも非植林性の林地の分布が高くなることなどによるものであろう。しかし現存量の多い植生構造への変化が多少みられるにせよ、この高い伸び率には疑問が残る。今後の詳細な検討がまたれる。
ⅱ)現存量と傾斜度
現存量と傾斜度の関連は図49にみられるような指数曲線的な伸びとなっている。傾斜が急になるにつれて現存量の伸びは縮小されるものの依然量的に増加している。急傾斜地は高標高の地域に多く、現存量と標高との関連でみられた1,000~2,000m間の伸びと対応したものであろう。
ⅲ)現存量と地形区分
現存量と地形区分では表47のようにクロス集計と地形区分別の平均現存量で関連をみた。臨海部から内陸山岳部にいたる一般的な地形変化のパターン(人工改変地→低地→台地→丘陵地→山地・火山地)に対応して現存量も増加する。台地、低地、人工改変地は人口の集中地域であり、住民の日常生活圏における緑との接触はきわめて乏しいものとなろう。火山地では山地よりも現存量が高くなっているが、これは植生の自然立地条件の相異によるものか、あるいは人為による土地利用規制の相異によるものか、今後の詳細な検討が必要である。
ⅰ)現存量と人口
現存量と人口は図50でしめされるような指数曲線的な関連になる。人口が過密になれば現存量は確実に減少するといった、人口と緑とのトレード・オフ関係を明確にあらわしている。こうした現実をみると人口の集中した都市部に緑を復元する困難さが推察される。同時に、現存量の低下率では人口の増加につれて緩和されていることから次のような指摘もできよう。つまり緑(現存量)の破壊が人口の定住によるものと仮定すれば、0~100人/km2の人口希薄地域では人口1人につき34.6tの緑が破壊されることになるが、5,000~10,000人/km2の高密地域では0.1tにすぎないということてある(回帰式による)。いわば同じ人口1人でも所有する潜在的な緑の破壊力は地域によって相異するわけで、緑におおわれた山地といえどもその破壊速度は高いので楽観は許されない。
ⅱ)現存量と産業別就業人口
現存量と産業別就業人口も、互いによく似た指数曲線的分布に従っている(図51)。ここでも人口との関連でみられたように、就業人口と現存量とはトレード・オフの関係にある。
図52は現存量と第1次産業就業人口構成比との関連を人口密度ランク別にいくつか抽出してグラフ化したものである。この表によれば、同数の人口密度をもった地域でも、現存量はその第1次産業就業人口(あるいは第2第3次産業の合計就業人口)の規模によって微妙に変動しているのがわかる。現存量が最大となる構成比は各人口密度ランクでまちまちであるが、その位置がいずれも各ランクのもつ構成比の変動域の中間にある点では共通している。しかもこの最大現存量となるそれぞれの構成比の位置は、人口密度ランクの高位化にともなって左に移動し、その値が小さくなる傾向がうかがえる。現存量のこうした傾向は、第1次産業では相対的に多くの土地を必要とするといった、産業別による空間依存性の強弱と関連があろう。しかし同じ第1次産業でも林業と農業とでは依存する土地に生育する植生の現存量に格段の差があり(自然度2の農地では16.8t/ha、同6の植林地では66.6t/ha、図36前掲)、第2次、第3次産業それぞれについても土地の依存性には同様の格差があろう。また人間の定住の場としての集落の立地形態、周囲の緑地環境、土地利用状況などについても地域によってまちまちであり、現存量も多様に変化しよう。したがって図52にみられる傾向もその因果は複雑であり、性急には判断しがたい。
ⅲ)現存量と製造業事業所数
現存量は人口、就業人口など開発行為をあらわす指標と同様に、製造業事業所数の増加によっても減少する傾向がある(図53)。
なかでも事業所数が0~10の間での現存量の急激な減少が顕著である。
図54は現存量と製造業事業所数との関連を4ランクの人口密度別にみたものである。この表によれば、人口密度500~1,000人/km2の地域を除いて、ほぼ右下がりの傾向をみることができる。すなわち厳密ではないまでも人口密度2,000人/km2以上の高密人口地域では、同じ人口密度であっても事業所数が多い(工場が多い)地域ほど現存量は低下していることが推察されて興味深い。
ⅰ)生産量と標高
生産量と標高は図55にみられるような関連にある。標高400~700m(階級値550m)間で生産量はピークとなっている。これは400~700m地域では生産量の高い自然度6の植林地がもっとも多く分布することによるものと考えられる(自然度6:63.5%、同7:28.1%、その他:8.4%)。
ⅱ)生産量と傾斜度
生産量と傾斜度は図56に示したような関係をもっている。15~20°間で生産量はピークをしめしているが、これは自然度6の植林がもっとも優勢に分布するところであり、この生産量の高さは植林地によるものと考えられる(自然度6:44.6%、同7:29.7%、その他:25.7%)。
ⅲ)生産量と地形区分
生産量と地形区分との関連は表48に示したとおりである。現存量では台地、低地になると大幅な減少がみられたが、生産量では落ち込み方が緩慢である。それは生産量の高い農地が広く分布しているからであろう。また現存量では山地よりも火山地が上回っていたが、生産量では逆転している。山地では火山地に比して生産量の多い植林の分布が2倍ほど高く(山地:38.2%、火山地:19.7%)ここでも植林地率が大きく影響しているものと考えられる。
ⅰ)生産量と人口
生産量と人口との関連は図57にしめされている。人口100人/km2あたりまでは多少の生産量の上下変動がみられるが、ほぼ現存量と人口との関連と同様に、人口の増加は生産量の低下をともなっている。回帰分析によれば、2,000人/km2で1t/ha/yearすなわち1メッシュあたり2,000人の増加で生産量100tの減少、あるいは人口密度1(人/km2)の増加で生産量は50kgの減少ということになろう(回線回帰式)。
ⅱ)生産量と産業別就業人口
生産量と産業別就業人口との関連は図58であらわされている。この関連は現存量と産業別就業人口でみられるほど明瞭なトレード・オフの関係はない。とくに0~200人/km2にかけての生産量の動向は各産業でまちまちである。
図59は生産量と第1次産業就業人口構成比との関連を人口密度のランク別にいくつか抽出してグラフ化したものである。これによって同じ人口密度地域での就業人口構成による生産量変動の有無をみた。この表によれば人口5,000~10,000人/km2の地域では変動が大きいが、1~2,000人/km2までの3ランクの地域では小さい。しかしいずれも構成比の上昇に伴って生産量も増加するという右上がりの傾向をもっているといえる。すなわち生産量は、同程度の人口密度の地域であっても第1次産業就業人口の構成比が高くなるほど多くなることになる。これは多分、第1次産業では植生のなかでも生産量の高い空間(農地、植林地)に強く依存していることが影響しているものであろう。
ⅲ)生産量と製造業事業所数
生産量と製造事業所数では現存量とそれとの関連に類似しており、事業所の増加は生産量の指数曲線的な減少傾向をともなっている(図60)。しかし事業所の低密度立地地域における現存量の急激な勾配(図53)にたいして、生産量ではやや緩慢となっている。人為的に生産量の増大をはかる農地や植林地が、人口の密集地域と非密集地域との間に介在して生産量の減少の急勾配を緩和しているためであろう。
社会環境要因のなかで植生との関連を把握する場合には人口が有効であり、またそれぞれの植生量(緑被地率、林地率、現存量、生産量など)と人口との関連では、人口が増加すればほぼ一様に植生量が減少するという傾向があきらかとなった。そこで最後に、自然環境、社会環境の各要因それぞれの区分地域における人口と植生量との関連を定住人口1人当りという単位量であらわすことによって、日常生活圏における住民と緑との接触の問題を考える際の参考としたい。表49が算出結果である。人口についてはいうまでもないが、標高では0~99m、傾斜度では0.0~2.9度、地形区分でいえば台地、低地、人工改変地などの人口集中地域において、1人当りの植生量が僅小であることが歴然である。
自然環境と社会環境の関連性について以上のような分析は、あくまで予備的分析の段階にとどまるものである。今後の研究にとって残された課題として、研究の内的構造と研究のもつスコープの2点から問題提起的に述べると以下のごとくであろう。
まず前者については、1自然度といった研究上の中枢概念をなんらかの方法によって距離尺度の上に展開することである。そして、2緑を中心とした自然環境に対する影響要因について理論的・経験的な研究を蓄積していくこと、3今回の調査が、植生生産量を除いて、ストック変数を中心にした1時点のクロス・セクション分析の形をとっているが、これに時間的要素とフロー変数を加えてより一層精緻化すること、などが望まれるのである。
次に、後者については、1自然環境因子と社会環境因子の因果関係の構造について、仮説的にモデルを構築し実際の検討に付すこと、そして、2このような分析をふまえながら、人間にとって本当の暮しやすさとは何か、その中で緑を中心とした自然環境のはたす役割について考察と評価を加えていくこと、が必要になろう。