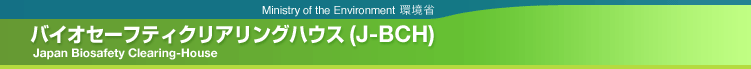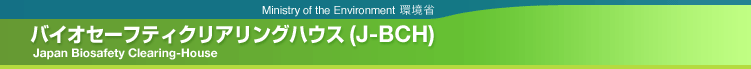この補足議定書の締約国は、
生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(以下「議定書」という。)の締約国として、
環境及び開発に関するリオ宣言の原則13を考慮し、
環境及び開発に関するリオ宣言の原則15に規定する予防的な取組方法を再確認し、
損害がある場合又は損害の可能性が高い場合における適当な対応措置について議定書に適合するよう定めることの必要性を認識し、
議定書第二十七条の規定を想起して、
次のとおり協定した。
第一条 目的
この補足議定書は、改変された生物に関する責任及び救済の分野における国際的な規則及び手続を定めることにより、人の健康に対する危険も考慮しつつ、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に寄与することを目的とする。
第二条 用語
1 生物の多様性に関する条約(以下「条約」という。)第二条及び議定書第三条に定める用語は、この補足議定書について適用する。
2 さらに、この補足議定書の適用上、
(a) 「議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議」とは、議定書の締約国の会合としての役割を果たす条約の締約国会議をいう。
(b) 「損害」とは、生物の多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響(人の健康に対する危険も考慮したもの)であって、次のいずれの要件も満たすものをいう。
(i) 測定することができる悪影響であること、又は人に起因する他の変化及び自然の変化を考慮して権限のある当局が認める科学的に確立された基準が存在する場合には、当該基準を考慮して観察することができる悪影響であること。
(ii) 3に規定する著しい悪影響であること。
(c) 「管理者」とは、改変された生物を直接又は間接に管理する者をいい、 適当な場合には、国内法令によって決定するところに従い、特に、許可を受けた者、改変された生物を市場取引に付した者、開発者、生産者、通告をした者、輸出者、輸入者、運送者又は供給者を含むことができる
(d) 「対応措置」とは、次のことを行うための合理的な行為をいう。
(i) 状況に応じ、損害を防止し、最小限にし、封じ込め、緩和し、又は他の方法で回避すること。
(ii) 次の優先順位によりとられる行為を通じて生物の多様性を復元すること。
(a) 損害が発生する前に存在した状態又はこれに相当する最も近い状態に生物の多様性を復元すること。
(b) 権限のある当局がaに定める復元が可能でないと決定する場合には、生物の多様性の喪失について、特に、同一の場所又は適当な場合にはこれに代替する場所において、同一又は他の目的で利用される生物の多様性の他の構成要素によって当該喪失を埋め合わせることにより、生物の多様性を復元すること。
3 「著しい」悪影響は、次のような要素に基づいて決定される。
(a) 合理的な期間内に自然に回復することがない変化として理解される長期的又は恒久的な変化
(b) 生物の多様性の構成要素に悪影響を及ぼす質的又は量的な変化の程度
(c) 生物の多様性の構成要素が財及びサービスを提供する能力の低下
(d) 人の健康に及ぼす悪影響(議定書の文脈におけるもの)の程度
第三条 適用範囲
1 この補足議定書は、国境を越える移動に起源を有する改変された生物から生ずる損害について適用する。当該改変された生物は、次のものとする。
(a) 食料若しくは飼料として直接利用し、又は加工することを目的とするもの
(b) 拡散防止措置の下での利用を目的とするもの。
(c) 環境への意図的な導入を目的とするもの。
2 この補足議定書は、意図的な国境を越える移動に関しては、1に定める改変された生物の認められた利用から生ずる損害について適用する。
3 この補足議定書は、議定書第十七条に規定する意図的でない国境を越える移動から生ずる損害及び議定書第二十五条に規定する不法な国境を越える移動から生ずる損害についても適用する。
4 この補足議定書は、改変された生物の国境を越える移動が自国の管轄内へ行われた締約国については、この補足議定書が当該締約国について効力を生じた後に開始した当該国境を越える移動から生ずる損害について適用する。
5 この補足議定書は、締約国の管轄の下にある区域において生じた損害について適用する。
6 締約国は、自国の管轄の下において生ずる損害に対処するために自国の国内法令に定める基準を用いることができる。
7 この補足議定書を実施する国内法令は、非締約国からの改変された生物の国境を越える移動から生ずる損害についても適用する。
第四条 因果関係
損害と問題となる改変された生物との間の因果関係は、国内法令に従って確定される。
第五条 対応措置
1 締約国は、損害が生ずる場合には、一又は二以上の適当な管理者に対し、権限のある当局の求めに応じて次のことを行うよう要求する。
(a) 権限のある当局に直ちに報告すること。
(b) 損害を評価すること。
(c) 適当な対応措置をとること。
2 権限のある当局は、次のことを行う。
(a) 損害を引き起こした管理者を特定すること。
(b) 損害を評価すること。
(c) 管理者がとるべき対応措置を決定すること。
3 時宜を得た対応措置がとられない場合には損害が生ずる可能性が高いことを関連情報(利用可能な科学的な情報及びバイオセーフティに関する情報交換センターにおいて利用可能な情報を含む。)が示すときは、管理者は、当該損害を回避するために適当な対応措置をとることを要求される。
4 権限のある当局は、特に管理者が適当な対応措置をとることができなかった場合を含め、適当な対応措置をとることができる。
5 権限のある当局は、損害の評価及び4に規定する適当な対応措置の実施により生じ、又はこれらに付随する費用及び経費を管理者から回収する権利を有する。もっとも、締約国は、自国の国内法令において、管理者がそれらの費用及び経費を負担することを要求されない場合について定めることができる。
6 管理者に対し対応措置をとることを要求する権限のある当局の決定は、理由を示すべきである。当該決定は、当該管理者に通告すべきである。国内法令は、救済措置(当該決定の行政上又は司法上の見直しのための機会を含む。)について定める。権限のある当局は、また、国内法令に従い、利用可能な救済措置について当該管理者に通知する。当該救済措置の請求は、国内法令に別段の定めがある場合を除くほか、権限のある当局が適当な状況の下において対応措置をとることを妨げてはならない。
7 締約国は、この条の規定を実施するに当たり、権限のある当局が要求し、又はとる特定の対応措置を決定するため、適当な場合には、民事上の責任に関する自国の国内法令において対応措置について既に定められているか否かについて評価することができる。
8 対応措置については、国内法令に従って実施する。
第六条 免責
1 締約国は、自国の国内法令において、次の場合における免責について定めることができる。
(a) 天災又は不可抗力の場合
(b) 戦争又は国内争乱の場合
2 締約国は、自国の国内法令において、適当と認めるその他の場合における免責又は責任の緩和について定めることができる。
第七条 期限
締約国は、自国の国内法令において、次の事項について定めることができる。
(a) 相対的又は絶対的な期限(対応措置に関連する行為に係るものを含む。)
(b) 期限を適用する期間の開始
第八条 限度額
締約国は、自国の国内法令において、対応措置に関連する費用及び経費の回収に係る限度額について定めることができる。
第九条 求償の権利
この補足議定書は、管理者が他の者に対して有する求償又は補償についての権利を限定し、又は制限するものではない。
第十条 金銭上の保証
1 締約国は、自国の国内法令において金銭上の保証について定める権利を保持する。
2 締約国は、議定書前文の第九段落から第十一段落までの規定を考慮しつつ、国際法に基づく自国の権利及び義務に反しない方法で1に規定する権利を行使する。
3 この補足議定書の効力発生の後最初に開催される議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の会合は、事務局に対し、特に次の事項を対象とする包括的な研究を行うことを要請する。
(a) 金銭上の保証の仕組みの態様
(b) 金銭上の保証の仕組みの環境上、経済上及び社会上の影響(特に開発途上国に対するもの)の評価
(c) 金銭上の保証を提供する適当な主体の特定
第十一条 国際的に不法な行為についての国家の責任
この補足議定書は、国際的に不法な行為についての国家の責任に関する一般国際法の規則に基づく国家の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
第十二条 履行及び民事上の責任との関係
1 締約国は、自国の国内法令において、損害に対処するための規則及び手続について定める。締約国は、この義務を履行するため、この補足議定書に従って対応措置について定めるものとし、適当な場合には、次のいずれかのことを行うことができる。
(a) 自国の既存の国内法令(適用可能な場合には、民事上の責任に関する規則及び手続であって、一般的なものを含む。)を適用すること。
(b) 民事上の責任に関する規則及び手続であって、特に当該義務を履行するためのものを適用し、又は定めること。
(c) (a)に規定する国内法令を適用し、かつ、(b)に規定する規則及び手続を適用し、又は定めること。
2 締約国は、民事上の責任に関する自国の国内法令において第二条2(b)に定義する損害に関連する物的又は人的な損害についての適当な規則及び手続を定めることを目指して、次のいずれかのことを行う。
(a) 民事上の責任に関する自国の既存の法令であって、一般的なものを引き続き適用すること。
(b) 民事上の責任に関する法令であって、特に当該規則及び手続を定めるためのものを制定の上適用し、又は引き続き適用すること。
(c) (a)に規定する法令を引き続き適用し、かつ、(b)に規定する法令を制定の上適用し、又は引き続き適用すること。
3 締約国は、1(b)若しくは(c)又は2(b)若しくは(c)に定める民事上の責任に関する法令を制定する際は、状況に応じて、特に次の要素を取り扱う。
(a) 損害
(b) 責任の基準(厳格責任、過失に基づく責任等)
(c) 適当な場合における責任の所在の特定
(d) 請求を行う権利
第十三条 評価及び再検討
議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この補足議定書の効力発生の五年後に及びその後は五年ごとに、この補足議定書の有効性についての再検討を行う。ただし、当該再検討の必要性を示す情報が締約国によって提供されている場合に限る。当該再検討は、この補足議定書の締約国が別段の決定を行わない限り、議定書第三十五条に規定する議定書の評価及び再検討の文脈において行う。最初の再検討は、第十条及び前条の規定の有効性についての再検討を含む。
第十四条 議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議
1 議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、条約第三十二条2の規定に従うことを条件として、この補足議定書の締約国の会合としての役割を果たす。
2 議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この補足議定書の実施状況を定期的に検討し、及びその権限の範囲内でこの補足議定書の効果的な実施を促進するために必要な決定を行う。議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この補足議定書により与えられる任務を遂行し、並びに議定書第二十九条4(a)及び(f)の規定により与えられる任務に必要な変更を加えたものを遂行する。
第十五条 事務局
条約第二十四条の規定によって設置された事務局は、この補足議定書の事務局としての役割を果たす。
第十六条 条約及び議定書との関係
1 この補足議定書は、議定書を補足するものとし、議定書を修正し、又は改正するものではない。
2 この補足議定書は、この補足議定書の締約国の条約及び議定書に基づく権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
3 条約及び議定書は、この補足議定書に別段の定めがある場合を除くほか、この補足議定書について準用する。
4 この補足議定書は、国際法に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。ただし、3の規定の適用を妨げるものではない。
第十七条 署名
この補足議定書は、二千十一年三月七日から二千十二年三月六日まで、ニューヨークにある国際連合本部において、議定書の締約国による署名のために開放しておく。
第十八条 効力発生
1 この補足議定書は、議定書の締約国である国又は地域的な経済統合のための機関による四十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。
2 この補足議定書は、1に規定する四十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の後にこれを批准し、受諾し、若しくは承認し、又はこれに加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、当該国若しくは機関が批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を寄託した日の後九十日目の日又は議定書が当該国若しくは機関について効力を生ずる日のいずれか遅い日に効力を生ずる。
3 地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、1及び2の規定の適用上、当該機関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない。
第十九条 留保
この補足議定書には、いかなる留保も付することができない。
第二十条 脱退
1 締約国は、この補足議定書が自国について効力を生じた日から二年を経過した後いつでも、寄託者に対して書面による脱退の通告を行うことにより、この補足議定書から脱退することができる。
2 1の脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した日の後一年を経過した日又はそれよりも遅い日であって脱退の通告において指定される日に効力を生ずる。
3 議定書第三十九条の規定に従って議定書から脱退する締約国は、この補足議定書からも脱退したものとみなす。
第二十一条 正文
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの補足議定書の原本は、国際連合事務総長に寄託する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの補足議定書に署名した。
二千十年十月十五日に名古屋で作成した。
|